Experience Note
留学体験記

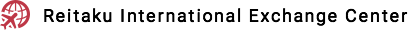
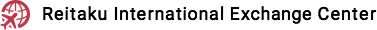

留学体験記
HOME 留学体験記
一足先に留学を経験した麗澤大学の先輩たちが、留学先でのさまざまな体験談を語ってくれた「留学体験記」。
先輩の生の声を、是非参考にしてみてください。

私は5週間、オーストラリアのゴールドコーストという場所にある、ラングポーツ語学学校へ留学に行きました。今回の留学は私にとって初めてのもので、ホームステイを通してオーストラリアのライフスタイルを学ぶことができました。大学入学前から、留学に行きたいという思いがあり、積極的に説明会に参加し、経験者である先輩や友達から話を聞き、オーストラリアへ留学することを決意しました。海外には何度か旅行で訪れたことがありましたが、5週間という長期間、異国の地で、見ず知らずの人と生活することには少し不安もありました。しかし、私はとてもフレンドリーなホストファミリーに恵まれ、快適な生活を送ることができました。この留学を通して得た様々な体験を紹介します。
私がオーストラリアに到着してすぐ感じたことは、「暑い!」ということでした。日本は真冬で、私は長袖を着て飛行機に乗っていたため、到着後はすぐ半袖に着替えたくなりました。日本は湿気が多くじめじめしていますが、オーストラリアの気候は乾燥しており、比較的過ごしやすく感じました。空気もカラッとしていて気持ちよく、気温の割には快適な日が多かったです。到着後1週間は良い天気が続いていましたが、その後、なんと50年ぶりに、サイクロンがゴールドコーストを直撃しました。強風と豪雨に見舞われ、学校は休校、バスやトラムは計画運休となりました。
特に驚いたのは、私のホームステイ先で停電が発生し、1週間も電気のない生活を送ることになったことです。電気が使えないため、ろうそくや懐中電灯の明かりを頼りに過ごし、シャワーもお湯が出ず、冷水のみでした。家がガスコンロだったため、なんとか料理はできましたが、インターネットも使えず、不便な日々が続きました。日本では長期間の停電を経験したことがなかったので、この復旧の遅さには驚きました。バスやトラムも数日間運休していたため、徒歩で1時間以上かけて学校へ行くこともありました。サイクロンの影響で砂浜が削られ、海にはしばらく入ることもできませんでした。学校では、休校になった授業を午後に振替で行ってくれました。この期間は辛かったものの、とても貴重な経験になりました。自然災害の中でも冷静に行動し、生活する力が身についたと思います。
一週間後の週末には、友達と一緒に1泊2日でシドニー旅行に出かけました。念願だったオペラハウスやハーバーブリッジ、ロックスのマーケット、シドニー湾のディナークルーズを楽しみました。クルーズでは夕焼けをバックにオペラハウスやブリッジの写真を撮ることができ、素敵な思い出になりました。海から見るシドニーの街並みはとても美しく、日常では味わえない特別な時間でした。翌日は、早朝にホテルのプールで泳ぎ、その後は、有名なボンダイビーチで海水浴やショッピングを楽しみました。短い滞在でしたが、計画的に動いたおかげで、大満足の旅行となりました。
ホームステイでは、お父さん、お母さん、娘さん、娘さんの彼氏、犬、猫、そしてブラジル人の女の子と一緒に暮らしました。特に厳しいルールはなく、快適でした。朝食は自分で準備し、昼食は持参したり、日本から持ってきたカップヌードルを食べたりして、節約しました。夕食は毎晩手料理をいただき、とても美味しかったです。家の鍵も渡されていたので、帰宅時間も自由でした。ホストファミリーはとても親切で、困ったことがあればすぐに助けてくれたので、安心して毎日を過ごすことができました。同居していたブラジル人の女の子とはとても仲良くなり、学校の初日には彼女が校内を案内してくれました。毎朝一緒に登校し、夜には「TimTam Time」と称してお菓子を食べながら、恋バナや映画の話をしたのも楽しい思い出です。彼女とは今でも連絡を取り合っており、またいつか会いたいと思っています。その後、ニューカレドニア人の男の子や、帰国前日にやってきたスイス人の女の子とも出会い、計3人のホームメイトと交流することができました。異なる文化や価値観に触れながら生活する中で、自分の視野も大きく広がりました。英語でのコミュニケーションが自然にできるようになり、語学力の向上も実感できました。
ラングポーツ語学学校は、バスで約20分の場所にありました。最寄りのバス停は1時間に1本と少し不便でしたが、徒歩で通学することも可能でした。初日に行われたレベル分けテストにより、自分の英語力に合ったクラスで学ぶことができ、ついていけないという不安はありませんでした。私はボキャブラリーの授業を選択し、カンバセーションクラスも受講しました。毎週月曜日にはテストがあり、8割以上の得点でクラスが昇級する仕組みです。金曜日には卒業式があり、盛大に盛り上がります。私は人と話すのが好きなので、積極的にクラスメイトと交流し、多くの友達を作ることができました。授業の雰囲気は和やかで、先生も優しく、分からないところは丁寧に教えてくれました。
学校では無料・有料含めさまざまなアクティビティが用意されており、私はコアラを抱っこして写真を撮ったり、カンガルーやクロコダイルを見られるCurrumbin Wildlife Sanctuary、水族館兼テーマパークのSea Worldでショーやアトラクションを楽しんだり、サーフレッスンにも参加しました。クラスメイトたちとBBQをしたり、友達の家のプールで遊んだり、Pubやナイトクラブに出かけたりと、充実した週末を過ごしました。また、小学校のころからの友達ともゴールドコーストで再会し、ブリスベンへは一人旅にも出かけました。二宮和也主演のドラマ『ブラックペアン』の撮影地である、クイーンズランド州内のロケ地も訪れ、ファンとしてとても嬉しい体験でした。自由時間も多く、自分で計画して行動することが多かったため、自主性や判断力も身についたと思います。
最初は不安だった留学生活も、5週間はあっという間に過ぎてしまい、もっとオーストラリアにいたいという気持ちが強く残りました。同時に、自分の語学力がまだまだであると痛感し、今後さらに英語の勉強に励みたいという意欲も湧きました。必ずまたオーストラリアに行きたいと思います。この5週間で得た経験や出会いは、私の人生においてかけがえのない財産です。これからもこの留学経験を大切にし、さまざまな場面で活かしていきたいです。

本当に行って良かったし、この決断をしたことが正解だったと胸を張って言えます。人生で1番の経験、景色、出会い、思い出がそこには信じられないくらい沢山ありました。自信を持ってこの留学プログラムを全ての人にオススメしたいし、もう一度この留学プログラムが今後あるのなら、また挑戦したいという気持ちにさせてくれる、そんな留学でした。
この留学を知ったのは、麗澤大学の留学フェアに友人が誘ってくれたからです。元々留学に興味はあったものの、高いお金がかかるし、色々な面での怖さもあり、行動には移せていなかったので、話だけでもと思い、参加しました。そこで、このセブ島留学プログラムを知り、他の留学プログラムよりも挑戦しやすい価格であるということ、マンツーマンのレッスンが主流であるということ、そして期間が1ヶ月であること、特にその3点が決め手となり、この留学に行くことを決めました。初めての海外、初めての留学ということもあり、自分で行きたいとは言っていたものの、楽しみより不安な気持ちや怖さが圧倒的に大きかったです。この留学では、自分自身の『結局口だけ立派な部分』だったり、『言うだけ言ってちゃんと行動に移せない意思の弱さ』を本気で変えたくて、自立したくて、分からないことは100%理解できるまで担当の方に聞いて、留学へ行く前からしっかりと準備をしてきました。ちゃんと意味のある留学にしたかったので、留学へ行く理由、留学へ行って学びたいこと、留学中の目標などをしっかり決めてノートに書き、留学に備えました。
ついに出発日、空港に着いて、同じ麗澤生たちの顔を見て、楽しみな気持ちと、ちゃんと意味のあるものに出来るか不安な気持ちが混ざっていたような感情でした。セブについて初日、正直に言うと「帰りたい。」この気持ちがほとんどを占めていました。新しい環境が慣れなかったり、ご飯や匂いが体に合わないと感じることが多かったりと、やはり日本との生活の差を感じてしまっていたからです。他にも、現地の方や先生が何を言っているのか聞き取れないことが多く、それがとても悔しかったです。でもそんなマイナスな気持ちで、ただただ「どうしよう、やだ帰りたい。」などと思っても何も意味が無いと思ったので、私は改めて“なぜこの留学に来たのか”をノートに書いていた自分の考えを見て考え直し、留学中のルーティンをいくつか考えました。それは、毎日何にいくら使ったのかをレシートを貼ってまとめること、1日の授業でやったことを毎日30分以上は絶対に復習をすること、毎日英語と日本語で日記を書くことなど、とにかく自分をこの留学で成長させるために出来ることを自分自身で考え、沢山行いました。そうしてフィリピンでの生活をしていく日が多くなるにつれ、フィリピンの方たちの温かさ、日本には無いフィリピンの良さなどに気づくようになりました。例えば、近くのサムギョプサル屋さんにはスタッフの数が日本と比べ物にならないほど多くいたので、記念に写真を撮りたいと思い、会計の際そのことを伝えました。すると、誰1人躊躇することなく、写真1枚のために皆が盛り上がってくれました。日本では、まず周りの上司やお客さんの目を気にして、すぐにそんな対応はできないと思います。その丁寧さが日本のいい所かもしれませんが、逆にこのフレンドリーであたたかいところがフィリピンの良さだと感じました。
次にQQEnglishの良さについてお話します。まず、先生が面白くて優しく、授業が全て充実していて、楽しかったです。マンツーマンの授業では、分からないことがあった時に質問すると、絶対分かるようになるまで細かく教えてくれます。また、自分の学びたいことが何かを伝えると、それに沿った授業をしてくれます。私はコミュニケーションスキルを上げたかったので、それを伝えたところ、フリートークなどを踏まえた授業にしてくださいました。グループレッスンでは、私の担当だった先生はどちらも明るい先生で、どのトピックでも毎回とても楽しい授業でした。私のグループは、同じ大学ではない方とも一緒だったのですが、先生がフレンドリーで明るかったおかげで、同じ大学でない子とも仲良くなり、楽しく授業を行うことが出来ました。
授業以外の面に関して、カフェテリアのご飯は日本食に似たものがほとんどを占めていて、とても美味しかったです。特に月曜日の朝ごはんのラザニアとパンケーキがとてもおいしいので、毎週月曜日の楽しみでした。オススメです。お風呂のシャワーもあたたかく、カプセルでの生活もとても快適でした。14階にあるコモンスペースでは、勉強をするだけでなく、色々な方との出会いの場所でした。同じ日本人でも出身地が違っていて、話が盛りあがったり、違う国籍の方と話したり、コモンスペースがあったからこその出会いが多くあったので、感謝しています。そしてQQEnglishでは、多くのイベントがあって、それも新しい出会いや経験の1つで、とても楽しかったです。1ヶ月のみの留学でしたが、卒業式では、お世話になった先生からのメッセージ、楽しいゲームなどがあり、皆が盛り上げてくれてとても感動したし、改めてQQEnglishに来てよかったなと実感しました。
この留学へ行く前、学校の説明会での話や私の両親、インターネットには、「フィリピンは危ない」「スリに気をつけて」などの言葉がありました。ですが、1ヶ月フィリピンに行って私が実際に感じた、実際に自分の目で見た感じた経験や景色は、全然そんなことは無かったです。街の方が気軽にすれ違う度に話しかけてくれる、SNSや周りの人が言っていた話とは全然違って、優しく迎え入れてくれるような、本当に温かい国でした。そこで学んだのは、SNSや周りの人の言葉を信じるよりも、やはり実際に自分の目で見て、体で心で感じた自分自身の考えや経験を信じるべきだということです。それは、他の人の話を聞かない、信じないということではなく、自分の強い意志を持っておくことが大切だということです。それをこの留学で学ぶことが出来ました。この留学で、ロシア・ベトナム・ウクライナ・韓国・台湾・アルゼンチン・香港などの色々な国籍の方との出会いを通し、もっと色々な国々に興味を持つようになりました。この留学に来ていなかったら、見られなかった景色、出会えていなかった人たち、感じることの出来なかった感情が沢山ありました。新しい出会いがあるのが、初めましての人と話すのが、ただ道を歩いてるだけなのに「Japanese?」から始まるあのコミュニケーションが好きで、たった1ヶ月だけかもしれないけれど、その全てが私を大きく変えてくれました。飛行機でたった5時間飛んだだけで、こんな新しい世界があるということをとても興味深く思ったし、もっと色々な世界をこの目で見て、実際にもっと色々感じたいと思いました。
この留学を経て、たった1ヶ月だったかもしれないけれど、本当に世の中には沢山の人がいて、色々な人がいて、それぞれに個性があり、個々の考えを持っているということに改めて気づくことが出来ました。留学に行かせてくれて、日本からずっとサポートしてくれていた両親への感謝の気持ちや、留学したからこそ学べたこと、他の全てのこともしっかりと胸に刻んで、今のこの熱い気持ちを忘れずに、この先生活していきます。この留学は、間違いなく私の人生で一番濃くて、迫力があって楽しくて、沢山の出会いが嬉しくて、別れがすごく悲しくて、素敵な経験ができた1ヶ月になりました。素敵なきっかけをくれた全ての人に感謝をしたいです。ありがとうございます。またいつかどこかで、皆に出会えますように。

【初めに】
私がセブ留学に参加することを決めたのは、募集が延長されたときでした。元々興味はあったものの、締切が迫っていて一人で行く勇気がありませんでした。しかし、応募期間が延びたことを知り、友達を誘ったところ、彼女も行きたいと言ってくれました。これは英語を伸ばす絶好のチャンスだと思い、友達と一緒に応募することにしました。
【渡航前準備】
渡航までの準備は思ったより大変でした。まずは必要な書類を揃えることから始まりました。航空券の支払い、海外保険の加入、レベルチェック、パスポートの取得、eTravel登録など、やることは山ほどありました。特に今回が初めての海外渡航だったので、しっかりとお金を支払えているか、必要なものが欠けていないか、とても不安でした。また、留学前に大学で受けたTOEICの結果は、点数は前回より上がっていましたが、他の学部の子と比べるとかなり低いものでした。このままだとまずいと思い、少しでも留学先で話せるよう、出発前に英語の復習をしました。特に英単語の学習に力を入れました。
【到着と初日】
初日の集合時間が始発で間に合わない時間だったため、前日の夜に友達と合流し、そのまま朝一緒に成田空港へ向かいました。フライトは約4時間半で、音楽を聴いたり、友達とおしゃべりしたりしているうちにあっという間に到着しました。空港ではガイドの方が迎えに来てくれていたので、初めての土地での不安が少し和らぎました。空港から寮までのバス移動中、周りの風景に目を奪われました。見慣れない住宅や野良犬、ヤギ、牛などの動物、そして現地の人々の姿があり、とてもわくわくしました。
QQEnglishに着くと、早速飲み物を買いにカフェへ行きました。初めは英語での注文の仕方がわからず、指差しで注文しましたが、店員さんが優しく教えてくれたおかげで、無事に購入できました。お金もペソだったので、何度か店員さんに助けてもらいました。
1日目の夜には、同じ大学の女子で顧問ルームに集まり、顔合わせをしました。一人一人自己紹介をしながら交流を深めました。初対面の人がたくさんいて、とても緊張したのですが、話しかけてくれる人や面白い話をしてくれる人がいて、すぐに和むことができました。皆さんとても温かく明るい方ばかりで、これからの生活がとても楽しみになりました。
【授業内容】
2日目から授業が始まりました。授業は1対1の形式とグループワークがあり、すべて英会で行われました。QQEnglishでは、多様なカリキュラムが用意されており、ビジネス英語、日常会話、基礎英語などが選べます。私は基礎英語を学びました。授業は非常に充実していて、先生方は熱心で親しみやすい方ばかりでした。彼らの指導のもと、日々の学びが楽しく、あっという間に時間が過ぎていく感覚がありました。特にマンツーマンのレッスンでは、自分のペースで学ぶことができ、疑問点をその場で解消できるのがとても良かったです。講師はとてもフレンドリーで、私の緊張を和らげるために話しやすい雰囲気を作ってくれました。自己紹介の後、趣味や仕事について話すことで、英語でのコミュニケーションに自信を持つことができました。授業を重ねるうちに、授業に関係ない会話が増え、会話の重要性や海外の人に自分の英語が伝わる嬉しさを実感しました。その結果、授業がますます楽しくなりました。グループワークでは、同じ大学の人たちと英語で会話したり、身体を使って表現したりすることで、交流を深めることができました。
【友人との交流】
QQEnglishでの生活を通じて、多くの友達ができました。他大学の学生やタイ人、台湾人、ベトナム人、中国人、韓国人など、普段交流できない人たちとたくさんお話することができ、貴重な体験をさせていただきました。みんなで韓国料理を食べに行ったり、TOPsというとても綺麗な場所に行ったり、みんなでTikTokを撮るなど、今までにない国際交流を楽しむことができました。特に、アンジョワールド、シラオガーデン、カワサン、そしてジンベイザメツアーは、セブ留学の中で素敵な思い出として心に残っています。ジンベイザメツアーでは、朝の2時に寮を出発し、バスでオスロブまで向かいました。初めて生で見るジンベイザメの迫力に圧倒され、一緒に海を泳ぐという新鮮な体験に心が躍りました。海から上がった後は、車でカワサンフォールズへ移動しました。カワサンでの思い出は、まさに冒険に満ちた素晴らしい体験でした。まずはジップラインを楽しみながら下山し、その後は川を歩いたり、崖からジャンプしたり、みんなで仰向けになって連なり、川に流されるという普段では味わえないアクティビティに挑戦しました。崖のジャンプは4メートル、7メートル、10メートルと段階的に高くなり、最終的に10メートルから飛び降りた瞬間には「もう何でもできる!」という自信が湧いてきました。自分の成長を実感できた瞬間でもありました。また、地元の人々とも触れ合い、彼らの温かいおもてなしを感じることができたのも、良い思い出の一つです。
【自己成長】
4週間の受講を経て、私の英語力は向上しました。たった1ヶ月間で、スピーキングは会話が成り立つ程度になり、特に毎日英語を聞いていたことでリスニング力も以前より向上しました。また、授業中の先生との英会話を最大限に活かし、短時間で効率的に学ぶことができたと感じています。この研修を通じて、言語スキルの向上だけでなく、自己成長も実感しました。最初は不安や緊張が強かったですが、積極的に行動することで少しずつ自信を持てるようになりました。特に、グループワークでの英語でのディスカッションを通じて、自分の意見をしっかり伝える力が身についたと感じています。また、ある1人の先生から英語の本をいただきました。その本のタイトルは「The Strength In Our Scars」で、自己の経験や感情を通して、傷や困難が私たちの人生にどのような意味を持つのかが書かれた一冊です。私は、先生がこの本を私に贈ってくださった理由をしっかり理解し、英語の勉強も兼ねてこの本を大切に読もうと思います。
【最後に】
QQEnglishでの体験は、私にとって非常に有意義なものでした。英語力の向上だけでなく、異文化理解や自己学習の大切さを学ぶことができました。異なるバックグラウンドを持つ人々とコミュニケーションを取ることで、柔軟な思考が育まれました。また、多国間交流を通じて、交流を続けていきたい友達や貴重な思い出をたくさん作ることができました。これからも英語学習を続けていく中で、QQEnglishでの経験を活かし、さらなる成長を目指していきたいと思います。セブ島での短期語学研修の経験は、私にとってかけがえのない宝物です。麗澤大学18名、このメンバーで行けて本当に良かったです。ありがとうございました。

私は2025年3月、台湾の国立屏東大学で日本語の教育実習に参加しました。今回は麗澤大学からの実習生が私1人だけでした。1か月間も海外で生活することは初めてのことだったので、不安な気持ちもありましたが、現地の学生とたくさん交流できるチャンスだと思いました。実際に行ってみると、現地の先生や学生たちがとても温かく接してくれました。
授業外の時間も日本語学科の学生たちと関わることが多く、台湾に到着してすぐに学生が夜ご飯に誘ってくれました。空港に迎えに来てくれたバディと私以外に1人だけいる別のキャンパスの日本人留学生とみんなで行きました。初日から声をかけてもらえて安心したし、日本人の留学生とも仲良くなれて、その後も一緒にご飯を食べに行くようになりました。日本語学科の学生はとても親切で、初めて行く教室に案内してくれたり、食事に誘ってくれたりしました。私が1人で火車に乗る時、電車の乗り方を教えてもらったこともありました。大学の外で会った時も「西村さん、こんにちは。」と声をかけてくれる学生が多く、とても嬉しかったです。別の学科向けの授業に行った時も1人でいると声をかけてくれ、その授業について教えてくれる学生もいました。
授業の内容は日本語の説明が多く、私でも理解しやすかったです。ほとんどの授業を学生の席で一緒に受けて、グループワークや会話練習をしたり、テストを解いてみたりしました。日本人の実習生として、みんなの前に出て教科書を読んだり、学生の発表に対してフィードバックしたりすることもありました。元々は日本語の授業の内容や教え方を学びに行くものだと思っていましたが、日本語の授業というだけでなく、台湾の学生とのコミュニケーションの取り方にも関心を持ちました。日本語を教えるということは、多くの場合日本人ではない人を相手にするので、日本人の感覚で授業やグループワークをすると、スムーズに進まない可能性があると感じました。後半になると教壇実習が2回あり、自分で教案を考えて、先生として1コマ分授業をしました。2回とも1年生の授業で、内容は文法でした。国際学科の授業でもよくプレゼンはしますが、いつもグループで準備して話す時間も数分なのに対して、1回で50分以上の授業を作らなくてはいけないので、スライドもたくさんのページ数を用意しました。当日はとても緊張しましたが、学生たちはみんな協力的で、私が問いかけると積極的に答えてくれたので、安堵しました。実習の前には先生に相談する時間を取っていただいて、授業の流れや重要なポイントを教えていただきました。教壇実習以外にも、困った時は先生方にたくさん相談に乗っていただきました。
教育実習の内容は屏東大学の授業だけでなく、先生に現地の幼稚園や高校にも連れて行っていただき、授業を見学するだけでなく、発表を聞く機会もありました。訪問した幼稚園は日本語や英語の教育がされていて、園児たちは中国語を使わずに先生や友達とコミュニケーションを取っていました。また、みんな日本語と英語の名前があり、先生に呼ばれるときもその呼び方だったので驚きました。幼稚園生たちの授業を一通り見学した後、男子校の学生との交流がありました。少人数のグループに分かれて自由に会話をしました。私たちのグループでは、お互いに日本語と中国語・台湾語を教え合いました。高校生たちは英語もとても上手に話していて、全体的にコミュニケーションを取りやすかったです。別の日には、高雄にある高校で、日本語学科の学生のプレゼンを聞きました。とても長い日本語の台本を覚えていて、質疑応答もしていたことに感心しました。
滞在していた場所は4人部屋の寮で、私以外の3人はみんな台湾人の学生でした。3人ともとても優しくて、寮生活で必要なことについて教えてくれたり、生活に必要な物を貸してくれたりしました。彼女たちは日本語学科の学生ではなく、日本語を話さないので、会話する時はまず中国語で話して、お互いに上手く伝わらないと英語にしてみたり、翻訳機を使ったりしました。しかし、私は中国語を勉強していて、せっかくの機会なので、頑張ってできるだけ中国語で話すようにしました。私は中国語専攻ではなく、中国語の授業は週に何時間かしか受けていませんが、自分の持っている知識でなんとか考えつく言葉を使い、言いたいことが伝わった時や相手の言ったことがわかった時は、毎回嬉しかったです。私は普段、麗澤大学には実家から通っているので、寮で生活することも初めてでした。慣れない環境で、授業を受けながら自分のことは自分でやらなくてはいけないし、洗濯やシャワーは使える時間が決まっているので、その時間に合わせて行動することが私にとっては大変でした。ごみ捨て場にはたくさんのごみ箱があり、分別のルールが決まっていました。また、洗濯機・乾燥機は、どちらも1回10元かかり、両替機がないので、いつも洗濯用の10元硬貨を確保することに必死になっていました。どうしても用意できなかった時、寮の入り口の自動販売機で何か買ってお釣りを使おうと考えて行ってみると、自動販売機も小銭しか入らず困っていましたが、受付の職員の方に両替してもらって洗濯機を回すことができました。受付の方たちもとても親切で、寮の中を案内してもらったり、タクシーを呼んでもらったりしました。
スケジュールは授業でびっしりと埋まっているわけではなく、1日1コマの日や全休の日もありました。授業が忙しすぎないおかげで、部屋でゆっくり休んだり、屏東大学でできた友達と出かけたりしやすかったです。土日休みは、日本語学科やバディの学生に案内してもらい、遊びに行くこともありました。屏東ではたばこ工場跡地の博物館や勝利星村という観光地に連れて行ってもらいました。私の行きたいところやみんなのおすすめのお店などたくさんの場所に行くことができました。先生にも食事に連れて行っていただいたりおすすめの場所を教えていただいたりしました。屏東だけでなく、高雄や台南の観光をした日もありました。普段は利用しない火車に乗って移動しました。目的地に到着すると、屏東とは違う雰囲気で、観光地らしさがありました。高雄では日本語を話す観光客を見かけることも多く、お互いに写真を撮り合ったりしました。屏東ではほとんど日本人と接する機会がないので、少し安心感がありました。高雄出身の友だちとお店で買い物をしたり、人気の飲食店を巡ったりしました。記念にプリクラも撮りました。台南までは1人で行きましたが、北部に住んでいる台湾人の親戚と合流して、色々な場所を案内してもらいました。有名な建築物を見たり、おしゃれなカフェでスイーツを食べたりして、普段会えないお互いの家族の話もしました。台湾の親戚たちは遠くに住んでいて中々会えないので、休日を合わせて会うことができて嬉しかったです。
私は今回の教育実習で、いつもより多くの日本語の授業を受け、日本語教育について考え、今まで以上に日本語教育に関心を持つようになりました。将来、日本語を教える職業に就くことも視野に入れて、今後の大学生活ではもっと日本語の授業を取ってみようと思いました。1か月間台湾で過ごしてみて、絶対にまた台湾に行こうと思いました。

2025年3月9日から22日の2週間で開催された淡江大学春期中国語研修に参加しました。きっかけは専攻の先生から紹介で、同じ専攻の友人も行くと聞いたので参加を決めました。今回の留学について、私は2年次の目標である台湾長期留学に向けての前勉強程度の気持ちで臨んでいました。説明会の時点でも、旅行に毛が生えたくらいと聞いていたので、かなり軽い気持ちで参加しましたが、想像以上の経験を得ることができました。そんな2週間で私が体験したこと、感じたことについて書いていこうと思います。
まず留学までのおおまかな流れとして、12月頭に留学の申し込みと航空券の予約をし、2回の説明会に参加、クラス分けのオンラインテスト、そして出発日の数日前から生活や気候など予想のつかない中、パッキングを始めました。幸い、麗澤大学からは1年生7人での参加だったので、お互い協力しながら準備をすることができました。当日は朝早い便だったので、前日から羽田空港で待機し、そして特に問題なく、4時間ほどで台北松山空港に到着しました。到着後は空港内のカウンターで寮に支払うお金と、自分たちで使うお金を両替しました。両替後、私たちは自分たちで空港から寮まで行く必要がありました。そのため、地下鉄で寮の最寄り駅まで向かいました。地下鉄のシステムにおいては、日本と大きな差はなかったので分かりやすかったです。寮は駅から歩いて10分ほどで到着して、すぐ入寮等の手続きをしました。手続きの担当は、この留学中に私たちを支えてくれる4人のカウンセラーさんだったのですが、全員日本語を話すことができたので、個人的にとても心強かったです。また、駅や街中の看板に日本語が書いてあったりするので、日本人にとって台湾はとても有り難い環境であると感じました。そのおかげもあって、到着してから中国語を一切話さずとも入寮の手続きまで終えることができました。
次に授業についてです。到着した翌日の午前中、クラス分けテストとして、淡江大学の先生と中国語で5分程の口頭試問を行いました。口頭試問とはいってもフランクな雰囲気で、ほとんど雑談のような印象でした。この口頭試問と出発前に受けたオンラインでのテストでクラス分けがされたのだと思います。その後、お昼を挟んでから早速クラスごとに分かれて、顔合わせと自己紹介がありました。クラスは参加者50人を4つのクラスに分けていて、それぞれのクラスに先生とカウンセラーさんがつきます。そして本格的に授業が始まったのは次の日からで、平日は毎日9時から17時まで中国語の授業を受けます。日によって午後の授業内容は文化授業になったり、台北観光だったりと変化はあるのですが、基本的に座学の授業があればずっと中国語漬けでした。そして個人的な意見として、私が入ったクラスのレベルはかなり高く、先生は補足以外で日本語は話さないうえ、既に基本的な会話はできるという人が多く、正直なところプレッシャーが大きかったです。今まで大学に入ってから1年間、自分なりに勉強してきたつもりでしたが、実際に話すとなるとさまざまな問題点が見えてきて、勉強の足りなさを実感しました。ただ、先生もクラスメイトも誰かが困っていたら、解決するまで寄り添ってサポートしてくれるので、このような不安に思う点は日が経つごとに減っていって、修了式の日には、このクラスに入ることができて良かったと思えるようになりました。また、授業の細かい内容として、話す力を試すことが多かったです。台湾での経験談やこれからやりたいこと、自分の将来についてなどを書き出して、みんなの前で説明するという内容は毎日取り組んでいました。その他には、先生から台湾で有名な音楽などを教えてもらったり、Kahootを使って遊んだりと授業において堅い雰囲気になることは一度も無かったです。そして、前に少し書きましたが、午後の授業は曜日によって内容が決められていて、火曜日と木曜日は文化授業が行われます。台湾伝統の提灯や京劇の面、ちまき香包などを作りました。水曜日は、カウンセラーさんたちが考えてくれたプランで台北巡りをします。私たちは博物館や科学館、夜市などに連れて行ってもらって観光を楽しみました。
最後に食事についてです。今回の留学では、学食のようなシステムは無く、朝ご飯から夜ご飯まで全て自分たちで探すことになっていたので、たくさんの場所で台湾特有の食文化を楽しむことができました。台湾の食文化について、私が思う日本と大きく違う点は2つありました。1つは朝ご飯についてです。台湾は朝早くから開いているご飯屋さんが多く、朝ご飯専用のお店も多くありました。クラスメイトも朝ご飯を買ってきて、授業前に食べている人が多かったです。私たちのクラスでは蛋餅というお餅のような料理が一番人気で、クラスの半分の人が買ってきた日もありました。蛋餅以外にもいろいろな種類があって、日本では体験できない朝ご飯文化を、台湾に来たときはぜひ体験してみて欲しいです。もう1つはテイクアウト文化です。紹介した朝ご飯に限らず、飲み物から夜ご飯まで、多くのお店でテイクアウトが盛んに行われています。特に夜市に行ったときが印象的で、どのお店もテイクアウトができて、イートインの無いところも多くありました。このような文化の影響か、私も友だちと一緒にご飯や飲み物を持ち歩くことが多く、日本でいう食べ歩きをすることが頻繁にありました。食事について、台湾に行く前段階では、香辛料を使った料理が多く、お腹を壊すかもと聞くことが多かったので注意していましたが、実際はそんなこともなく、留学期間中めいっぱい満喫することができました。
この2週間を振り返ってみて、不安や後悔などの辛いことは少なからずありましたが、それ以上に思い出に残る貴重な経験を得られたと思います。現地に行かなければ分からないことや行ってやっと気づけたことが本当にたくさんあって、外国語を学ぶにあたって、留学は短期だとしても大きな成長になると思います。もし今、留学に行こうか迷っているという人がいるのであれば、ぜひ挑戦してみて欲しいです。

私は2025年3月、淡江大学の短期中国語研修に参加しました。私にとって初めての海外、初めての中国語研修ということもあり、現地での生活や授業などに対する様々な不安と、新しいことにチャレンジできるワクワク感を抱えながら台湾へ渡航しました。最初は不安もありながら参加した研修でしたが、現地で様々な人と出会い、楽しく貴重な時間を過ごし、忘れられないくらい大切な思い出になりました。この体験記では、感想を交えながら、台湾での生活、授業、今後の目標についてまとめていきます。
現地での交通手段として利用したのはMRTとバスです。MRTを使う際には、悠遊カードという、日本のSuicaのようなものにチャージをするか、トークンというコイン型の切符を購入します。悠遊カードはバスに乗車する時だけでなく、買い物の支払いでも利用可能で、とても便利でした。コンビニ等で購入でき、様々なデザインのものがあるため、自分のお気に入りを探すのが楽しかったです。全体的に、運賃は日本に比べて安いと感じました。改札を通りホームに行くと、電光掲示板に次の便の到着までの時間が表示されていて、乗り換えも改札を出ずにできるため、とても利用しやすかったです。また、週末に外出した際には、バスも利用しました。バスにはそれぞれ番号があり、指定のバス停で待つ仕組みです。主要な観光地では観光客向けに日本語のアナウンスもありました。
今回私たちが宿泊したのは、師大会館という施設で、私も含めた麗澤大学生3人と、個人で参加されていた大学生1人の4人部屋でした。初対面で緊張していたのですが、気さくでとても親切な方だったため、すぐに仲良くなることができました。二段ベッドと机、椅子があり、冷蔵庫も利用可能でした。トイレとシャワーは一緒で、バスタブもなかったため、最初はかなり驚きました。
近くには夜市があり、そこで買ったドリンクがとても美味しく、何度も通いました。初めは、中国語で注文してもうまく伝わらず、結局英語で注文してしまっていたのですが、何度もチャレンジし、初めてサイズや氷・砂糖の量まで全て中国語で注文することができた時は、とても嬉しかったです。他にも服やアクセサリーを販売しているお店もたくさんあり、面白かったです。お昼休みには、キャンパス周辺の永康街というグルメ街で食事をしました。餃子や小籠包、蛋餅、牛肉麺など、さまざまな美味しいものを楽しめました。現地の大学生であるカウンセラーの方々が、おすすめのお店をまとめて教えてくださり、お店選びにとても役立ちました。同じプログラムに参加していた初対面の人たちとも一緒に食事をし、いろいろな話をして仲を深めることができました。
週末は授業がなく、自由に観光ができたため、土曜日は九份に観光に行きました。あいにくの雨だったのですが、かなりの観光客で賑わっていました。日曜日には龍山寺と迪化街に出かけました。龍山寺で、おみくじのシステムがわからずに混乱していたら、参拝に来ていた現地の方が詳しく教えてくださり、無事にお参りすることができました。困っている時に助けてくれる人や、気さくに声をかけてくれる人が多く、台湾の人々の優しさや親しみやすさに触れることができ、不安も自然と薄れていきました。
授業は4つのクラスに分かれ、それぞれのレベルに合った授業を受けることになります。到着の翌日午前中にスピーキングテストがあり、その結果をもとにクラスが分けられました。私は、1年間第二外国語の授業で中国語を学びましたが、繁体字は勉強していない上に、まだ知っている単語、文法がかなり少なく、クラス分けのテストでも答えられなかった質問があり、最初はとても不安でした。しかし、実際に授業を受けてみると、先生のジェスチャーを使った文法や単語の解説がとてもわかりやすく、すぐに不安はなくなりました。教わった知識を用いてゲームやアクティビティを行うという形式で、実践して身につけるというのが自分に合っていて覚えやすかったです。また、クラスメイトと協力しながら取り組むものが多かったため、すぐに仲良くなることができ、楽しかったです。授業最終日には、再度テストがあり、私のクラスは、先生と1対1のスピーキングテストと、リスニング・ライティングの筆記テストがありました。最初に受けたテストではわからない問題が多かったのですが、最終日のテストでは、ほとんどの問題に自信を持って答えることができ、高得点を取ることができました。
通常の授業のほかに、最終日のクラスごとの発表に向けた練習の時間もありました。私たちは歌とダンスで、中国語で歌を歌うのは初めてだったし、覚えるのが大変だったけれど、クラスの一体感がさらに増し、楽しく取り組むことができました。週2回ある文化授業は2クラス合同で、台湾の伝統について学び、それに関わるものを作りました。伝統文化の説明も中国語だったのですが、画像や動画を活用して説明してくれるため、理解することができました。日本との違いなども知ることができ、台湾特有の文化が興味深かったです。提灯や香包を作ったり、紐を編んだりしたのですが、京劇に関連したお面の色付けは、それぞれの個性が出ていて、特に面白かったです。
この中国語研修での経験を通して、中国語をもっと学びたいと強く思うようになりました。期間が2週間と短かったため、正直、新しい知識をたくさん身につけることができたと言えるほどではないかもしれませんが、同じく中国語を勉強しているたくさんの仲間と出会い、一緒に授業を受け、現地の人と交流して嬉しい思いや悔しい思いをし、様々な経験ができました。それらが今後の学習への大きなモチベーションになりました。2年生になっても引き続き中国語の授業を受ける予定なので、このプログラムで得た意欲を大切にしながら、学んだ知識を活かし、学習を続けていきたいです。

初体験のドイツ留学ですが、ドイツへは高校の夏休みを利用して1回行ったことがあります。兄が住んでいるミュンヘンで、1か月間の語学学校に通いました。そして今回、ドイツでの1年間をイェーナ大学でFriedrich Schiller UniversitätのATS(外国人用の留学)プログラムに参加し、ドイツの言語を勉強してきました。イェーナを選択したのは、治安が良く住みやすい場所と色々な方から聞き、安心して勉学に励むことができるだろうとの考えで留学する決心をしました。
イェーナに行く2週間前、私は兄が住んでいるミュンヘンを訪れました。ミュンヘンへは2回目で、前回と変わっておらず、迷子になることはありませんでした。ドイツ生活に慣れる為、事前にスーパーマーケットや散策をしてドイツ語の勉強をしました。
2週間が過ぎ、ドイツのICEという新幹線に乗り、約2時間弱でイェーナに到着しました。イェーナに到着した時にはまだ寮に入れなかったので、麗澤大学生が住んでいる寮に1週間ほど宿泊させてもらいました。この期間に、大学・銀行・保険・入寮・ビザなどの契約・申請を長谷川先生と一緒に終えました。長谷川先生はとてもやさしい方で、本当に有難い存在でした。初めての休日には、イェーナの中では規模が大きい公園を散策してみました。その頃はイースターの時期だったので、公園には沢山のイースターエッグがあり、芝生は青いものの冷たい強風が吹き、春を感じることはできませんでしたが、公園から見える山や丘は春を感じさせる淡い緑色の景色でした。
最初の1週間が過ぎ、私はようやく自分の寮部屋に住めるようになりました。寮はシェアハウスで、ドイツ人が2人、シリア人が1人の計4名で、それぞれの部屋と共同のキッチン、トイレ、洗面所があります。私の部屋は他の麗澤大学生の部屋に比べて一回り小さく、少し物を置くだけで手狭になります。しかし、共同キッチンだけは使い勝手の良い広々とした空間でした。
イェーナにも日本人会というコミュニティがあり、そこに1年間参加することにしました。ここでは、日本が好きなドイツ人やその他の外国人と日本人の集まりで、毎週金曜日の午後7時から夜中まで、日本語とドイツ語が混じった会話で沢山の情報を得ることができました。
2週間目には、ようやく前期の講義が始まりました。私が履修した講義はどれも麗澤大学にはない講義で、例えばGegenwartssprache Deutschは『現代語のドイツ語』という、現代のドイツ人がどのように言語を使っているかという講義で、とても勉強になりました。他の講義でも、ドイツ語の文法、ドイツ語でのプレゼン、ドイツ語での小論文などを最初の学期でやりました。一番苦労したのが、ドイツ語での小論文でした。参考文献もドイツ語で読み、理解した上で、小論文をすべてドイツ語で書かなければなりませんでした。
前期が終わると約3ヶ月の夏休みが始まり、私はさっそくミュンヘンへ行きました。ミュンヘンでは、私の好きな作家のミヒャエル・エンデの博物館があり、そこを訪れました。城のような建物の中に図書館と博物館があり、とても感慨深い場所でした。その他にも友達と一緒にライプツィヒの動物園に行ったり、日本から来た友人とドレスデンを散策したり、ハンブルクに住んでいる旧友に会って、私が生まれた病院と住んでいた町を訪れたりもしました。また、日本で出会ったドイツ人家族と鍾乳洞の観光したり、ベルリンへの1人日帰り旅行をしたりと、忙しく充実した夏休みを送ることができました。
夏休み明けは後期の始まりで、前期で受けた講義より少し難しい講義の履修登録をし、受講科目も増やしました。新しい受講科目は、ドイツ語で発声や表現を勉強し、舞台に立つ講義やドイツ現代文学です。前期よりレベルアップした文法講義を履修しました。全て前期とは比較にならないぐらいの勉強量が必要でした。特に前期では簡単な文法が、後期では知っている文法の知識に応用と活用が入ってきました。私はこの文法を理解していたつもりだったのですが、応用編ではなかなか難しく時間がかかりました。先生によっては理解しているだろうと思われていたので、細かい説明や教えがなく、大変苦労しました。講義の中で好きな科目は、『ドイツ語で舞台に立つ』と『表現力を書く』講義でした。『ドイツ語で舞台に立つ』では体を動かし、ドイツ語での発声練習。台本は「自分が好きなセリフを選び演技をする」という、とても面白い講義でした。『表現力を書く』の講義では、先生が毎回お題を出し、それに沿って自分なりの考えでドイツ語を書きます。例えば物語、エッセイ、ファンタジー、読書感想文など、どれも私にとって将来的に必要な講義であったと思いました。
忙しい時期も終え、冬休みが来ました。私はこの冬休みに各地のクリスマスマーケットを訪れ、そこではグリューワインが入ったマグカップや軽食などを買いました。大晦日は友人と一緒に工夫した年越しそばを食べ、ミュンヘンで買ったはちみつワインなどを飲んで年越しをしました。外では年越し花火をしているドイツ人が見えました。冬休み中に、仲良くなったドイツ人と一緒にケーキ作りもしました。
冬休みが終わり、テスト期間と帰国準備の時期になりました。テスト期間中は、大学で知り合った友人と一緒に、大学のカフェで勉強をしました。テスト後はすぐにミュンヘンに行き、Goethe InstitutB2を受験しました。結果はまだ来ていませんが、よい結果であるよう願っています。帰国時期になると、ドイツで契約したものの解約手続きを長谷川先生と一緒に行いました。帰国2週間前には、寮を出てミュンヘンに行き、帰国日まで色々なお土産を買い、忙しくしていました。
今回の留学での私の成長は、親元を離れ自立し、責任を持って生活が出来たことです。また、日本では習う機会が少ないドイツ語の日常会話、規則や契約など、公の書類を目にし、理解した上でサインするなどの重要な機会を得ることができました。麗澤大学とは違う本場でのドイツ語の履修はかなり身につきました。留学で色々な経験が出来たことを麗澤大学やイェーナ大学の先生やスタッフ、両親に大変感謝しています。これらの経験を活かして、将来に繋げたいと考えています。

私は南イリノイ大学で約7か月間生活し、異文化に触れながらさまざまな経験をしました。留学前は、自分の英語力で生活できるのか、差別を受けることはないのかといった不安が大きかったのですが、実際に過ごしてみると、多くのことを学び、成長できる貴重な機会となりました。異文化の中で生活することは決して簡単ではありませんでしたが、その分、多くの学びがあり、自分自身の価値観を広げる大きなきっかけとなりました。今回は、留学を通して感じたことや学んだことをまとめたいと思います。
アメリカに到着して最初に驚いたのは、生活環境の違いです。アメリカは広大な土地があり、道路や建物がとても大きく、街並みも日本とはまったく異なっていました。大学のキャンパスも非常に広く、ボウリング場やジムがあったり、敷地内に池があったりと、日本の大学とは比べものにならない規模でした。勉強や交流の場としてとても便利で、充実した環境が整っていました。キャンパス内には学生が利用できる施設が数多くあり、図書館やカフェテリアもとても広く快適でした。
カーボンデールは田舎町で、お店の数もそれほど多くありませんでした。電車はなく、大学が運営するバスが1時間に1本出ており、それを利用して買い物に行っていました。交通の便はあまり良いとは言えず、車がない私たちにとっては移動が大変でしたが、街全体の治安は比較的良く、平和で過ごしやすい環境でした。また、人々の性格も日本とは大きく異なっていました。道を歩いていると知らない人に話しかけられたり、困っているとすぐに助けてもらえたりしました。とてもフレンドリーな人が多く、見知らぬ人同士でも日常的に会話が生まれていました。最初は戸惑いましたが、次第にこの温かい文化を心地よく感じるようになりました。
学習面では、授業初日にクラス分けテストを受け、英語力に応じたクラスに編成されました。最初は、すべて英語の授業についていけるか不安でしたが、自分のレベルに合った授業を受けられたため、安心して学ぶことができました。タームを重ねるごとに授業の難易度は上がりましたが、それに伴い理解できる単語や話せる表現が増え、自分の成長を実感しました。特に最後のタームでは、授業内容やテストが難しくなりましたが、以前よりスムーズに英語を話せるようになり、大きな自信につながりました。先生方はとてもフレンドリーで、発言しやすい雰囲気を作ってくれました。また、生徒の理解度に応じて授業を進めてくれたため、安心して学ぶことができました。クラスの人数はタームごとに異なり、大人数のクラスと少人数のクラスの両方を経験しました。さまざまな国から来た学生と学ぶことで異文化に触れる機会が増え、自分の国では当たり前だと思っていたことが、他の国では全く異なる考え方を持っていたり、逆に自分が知らなかったことを学ぶことができたり、新しい価値観を知ることができました。また、積極的に意見を発表する生徒が多く、自分も刺激を受け、発言しようという気持ちになりました。
授業は朝9時ごろに始まり、午後2時ごろには終わりました。課題はほぼ毎日ありましたが、放課後の自由時間が多く、学校のイベントや買い物を楽しむことができました。最初のタームでは、新学期の時期ということもあり、スポーツイベントや野外映画、季節ごとのイベントなどが頻繁に開催され、日本の大学では味わえない貴重な体験ができました。また、アメリカ人の学生とも交流し、友達を作る良い機会になりました。私は、周りの人に恵まれ、イベントなどでできたアメリカ人の友達と車で別の州まで遊びにいったり、キャンプをしたり、友達の実家に遊びにいったりと、すごく楽しい思い出を作ることができました。
私は寮で生活していました。寮には留学生が多く、さまざまな国の人と交流し、それぞれの文化を学ぶことができました。共有スペースにはキッチンやテレビ、卓球台があり、一緒に食事を作ったり、遊んだりすることで自然と英語を話す機会が増えました。また、寮では定期的にイベントも開催され、サンクスギビングには教会で食事をしたり、クリスマスパーティーや年越しのカウントダウンを楽しんだりしました。こうしたイベントを通じて多くの友人ができ、忘れられない思い出がたくさんできました。特に、趣味が合う親しい友人ができたことは、私にとって大きかったです。
最初はうまく英語が話せず、自分の考えを伝えるのが難しかったのですが、少しずつ会話を重ねるうちに自然と英語が口から出るようになりました。友人と深い話をする機会が増えるにつれ、英語を話すことへの抵抗がなくなり、スピーキング力が大きく向上したと感じました。私はもともとシャイな性格で、初対面の人と話すのが苦手でした。最初は日本人と過ごすことが多かったのですが、次第にもっと多くの人と交流し、視野を広げたいと思うようになりました。積極的に質問したり会話をしたりすることで、自然と友達が増え、英語を話す機会も増えました。拙い英語でも勇気を出して話してみると、相手はしっかり汲み取ってくれ、優しくサポートしてくれました。間違いを怖がらずに勇気を出して話してみることが大事だと学びました。
一方で、異文化の人々との共同生活には、難しさもありました。私の住んでいた寮は個室でしたが、バスルームは共同で使用する必要がありました。そのため、バスルームの使い方が汚かったり、長時間使用する人がいて、自分が使いたいときに使えなかったりと、不便を感じることもありました。こうした文化の違いに戸惑うこともありましたが、寮文化の違いを理解し合い、柔軟に対応することで、より良い人間関係を築きながら生活していくことが大事だと感じました。また、自己管理能力や時間管理のスキルも向上しました。留学生活では、学業だけでなく生活全般においても自分で決断し、行動することが求められます。このような経験を通じて、自己管理の重要性を改めて実感しました。
7か月間の留学を通じて、英語力だけでなく、多様な文化への理解や適応力も身につけることができました。留学で得た経験を今後の人生に活かし、さらに成長していきたいと思います。

私は3月9日から22日までの2週間、台湾の淡江大学に短期留学をした。大学の校舎は台北にあるキャンパスだった。2週間というかなり短い期間だったが台湾の文化などを体験することができとても有意義に過ごすことができた。
台湾へ出発する前日の3月8日23時30分頃に羽田空港第3ターミナルに到着した。空港内では、3月にもかかわらずイルミネーションを行っており、とてもきれいだった。この時間に寝てしまったら絶対に起きることができないと思ったので、仮眠はしなかった。予定していた時間よりも早く全員集まることができた。先生も空港まで見送りに来てくださり、不安もなく台湾行きの飛行機に搭乗することができてとてもよかった。午前7時55分、私たちの乗る飛行機のフライト時間になり、いよいよ初めての留学が始まると思い、とてもわくわくした。飛行機内では中華風な音楽が流れていたり、キャビンアテンダントのお姉さんもチャイナ服を彷彿とさせるような制服でいたりと、すでに異国情緒が溢れていた。9時頃、機内食が提供された。機内食はカツカレーとシーフードパスタの二種類で私はシーフードパスタを選んだ。朝からパスタは重いと思ったが、美味しかったので満足だった。
数時間のフライトを経て台湾に到着した。現地の天気は曇りで、日本よりも暖かく、とても過ごしやすい気候だった。思っていたよりもスムーズに入国することができた。まずは寮を目指して台北市の東門駅に向かうためにMRTに乗った。MRTの切符は日本のものは全く違うもので、紙ではなくプラスチックでできたコイン型で不思議だった。車内は関東の電車よりも少し狭く、感覚で言えば大阪の御堂筋線のような狭さを感じた。MRTの切符には日本のSuicaのようなものもあり、多種多様な柄があることを知り、後日買いに行った。私が購入した悠游卡はサンリオキャラクターのもので、次回台湾に行った際に役立つと思う。
毎日のスケジュールは、朝9時から夕方17時まで授業を受けるというなかなかにハードなスケジュールで、中国語のクラスは4つに分けられていた。私は穿山甲というクラスで、レベルは上から2番目のクラスだった。授業の内容はこの1年間で学んだ中国語の復習のような感じで、自分の中国語の実力で十分に着いていくことができた。文化授業やグループ活動など、様々な授業があった。文化授業は他のクラスと合同で行われ、台湾の七夕や端午节について、京劇のお面作りや提灯作りなど、様々な台湾の文化について学んだ。この4つの中で私の一番印象に残った授業は、台湾の七夕についてだ。台湾では、七夕は乞巧とも呼ばれており、七夕情人节(チャイニーズバレンタインデー)として親しまれている。織姫と彦星のお話も日本で一般的に知られているものと異なり、とても興味深かった。授業では、台湾の縁結びの神様「月下老人」の赤い糸を作った。思っていたよりも簡単に作ることができ、楽しく作ることができた。この月下老人は台湾で映画化もしており、その映画の予告編を先生が私たちに見せてくれた。機会があれば映画を見てみようと思う。
毎週水曜日には、淡江大学のカウンセラーの皆さんと台北市内を観光するイベントがあり、国立台湾博物館や台北市立天文科学教育館に行った。国立台湾博物館には台湾の動植物や歴史に関するものが数多く展示してあり、とても見応えがあった。館内はとても広くエントランスは洋風な造りになっていて、すごく素敵な空間だった。国立台湾博物館の向かい側にある土銀展示館には、古生物の展示と日本統治時代の銀行の歴史を見学することができる。恐竜と銀行という異色の組み合わせで、なかなかに面白かった。台湾の銀行の通帳風用紙に記帳する体験もあった。カウンセラーの方曰く、音も本物と似ていて、クオリティがすごく高いようだ。見学した後、自由時間を使い、友人たちと西門を観光した。西門にはアニメイトがあり、そこで私の大好きな漫画の繁体字版を購入した。日本の店舗と大差はなかったが、文字が全て中国語で、とても不思議な感じがした。
台湾では飲み物屋が街中いたるところにあり、ゴンチャなどが好きな私にとって天国のような国だと思った。飲み物専門の店なだけあって種類がとても豊富で、飽きが来なく最高だった。台湾の飲み物と言えばタピオカミルクティーが定番だが、個人的には紅茶系のものがさっぱりとした味で飲みやすく、一番お気に入りだ。台湾にはカフェが街のいたるところにあった。私は友人と「猫のいるカフェ」に行った。この日は雨が降っていて、寮から近い場所だったが、歩いて行くには少し辛かった。店内は木の温かみを感じられるような空間だった。店員さんも優しく、注文したサンドイッチと飲み物、どちらもとても美味しくて満足した。お店の猫は、部屋の隅に置いてあるベッドで寝ていた。寝ている姿もとても可愛らしく、どこの国の猫もみんな可愛いのだと実感した。私は台湾で約3匹の猫を見かけた。また、台湾では犬を散歩させている人がとても多いと感じた。リードを付けて散歩している犬、エリザベスカラーを付けた大きな犬、まだ生まれたてのような小さなトイプードル、お店の看板犬をしている犬、ベビーカーに乗せられて溺愛されている犬など、様々な犬がいた。
朝は早起きをして、朝ごはん屋に買いに行った。毎日同じような服だったせいか、最終日にはお店の方に覚えられていて、とても面白かった。夕食は自由なので、毎晩外食という日本では考えられない生活で、とても貴重な経験をしたと思う。番茄牛肉面や鼎泰豊の小籠包など、いかにも台湾らしいものから、モスバーガーなどの日本でも食べられるもの、私の大好きな海底捞で火鍋を食べたりした。みんなで火鍋を食べることが夢だったので、すごく嬉しかった。別の日にお土産を買いに行った際には、昼食として念願の麻辣烫を食べることができた。自分で好きな具やスープを選ぶことができるので、とても楽しかった。ものすごく美味しかったので、日本でも食べに行こうと思う。

私は3月9日〜3月22日までの2週間、台湾・台北の淡江大学・台北キャンパスで中国語を勉強してきました。淡江大学・台北キャンパスは、MRTの淡水信義線という赤色ラインの東門という名前の駅が最寄りになります。東門はご飯屋さんやカフェがたくさんあり、食事には困らない環境でした。ですが、私は自分の中国語に自信がなく、相手に伝わらなかったらどうしようという不安から、台湾に着いて2日・3日くらいはまともな食事にありつけていませんでした。しかし、4日目あたりから、注文を頑張ってみようかなと思い始めたのです。というのも、私と同じクラスの子たちが、朝に「蛋饼」という、台湾では有名な朝ご飯を食べていて、3日間まともな食にありつけていなかったというものあり、それがとても食べたくなったのです。そのお店は台北キャンパスの近くで、朝早くからお昼頃までの営業時間だったので、その日のお昼に、急いでそこに向かったら、営業していたので、頑張って注文しました。「培根蛋饼一个。」とてもつたない短文ですが、これがなんと伝わり、とても嬉しかったのを覚えています。そこからは、授業やそれ以外でも、「とりあえず喋ってみよう。」「間違えても、それはきっと成長の糧になる。」そう思うようになり、自分の思いを発せるようになりました。
しかし、自分から話題を作るのはやはり難しく、自分の言いたいことは伝わっても、次に相手が発した言葉をうまく聞き取れず、会話が続かないということがよくありました。ですが、台湾の方は、ゆっくり話してくれたり、日本語を話してくれたりと、とても優しく接してくれました。特に最初の方は、日本語が全くと言っていいほど聞こえない環境下で不安に思っていたので、日本語を話してくれた時、とても嬉しかったです。もちろん、台湾人の全員が日本語を話せるわけではないので、言葉に詰まったり、言いたい言葉の中国語がわからなかったりした場合には、英語も用いて会話をしました。せっかく台湾に来たのに、日本語ばかりで生活してしまったら中国語が上達しないので、どうしても伝わらない時は、このように対処していました。もしわからない中国語があった場合、翻訳機に頼るのも1つの手段ではありますが、やはりそれに頼りっきりになってしまうと、これもまた自分の中国語の成長の妨げになると思うので、極力使わないことをお勧めします。また、台湾人の方は英語を話せる方が多いのか、中国語がわからない際に英語で話したら、しっかり伝わり、意外にも携帯の翻訳機を使うことはほとんどなかったです。
授業の構成・内容としては、主に会話がメインで、発表も多かったです。私は、皆の前に出て発表するのが苦手だったのですが、数をこなすうちにだんだんと慣れていきました。また、先生やクラスメイトも優しく、わからないところがあれば、教えてもらえたので、なんとか授業についていくことができました。午前は、教科書に沿って新出単語・文法を学習するのが3時間。そして午後の最初2時間は、先生が用意してくれたテーマについて絵を描いたり、文章を書いたりして、発表する、といった形式です。そして、残りの2時間は曜日によって違ったのですが、1つは台湾の歴史や文化について学びながら、それに沿ったものを作るという文化授業がありました。そしてもう1つは、チーム活動という、クラスごとの活動がありました。最後の終業式では、クラスごとの発表があったので、チーム活動では主に発表についての話し合いをしました。チーム活動の時間は、私にとって一番難易度が高かったです。なぜなら、教科ではテーマがあるから、出てくる単語の予測がつくのですが、チーム活動では、最初は特にテーマなどなく、1から自分たちで決めていく必要があり、自分の考えを中国語でクラスの皆に伝えなければいけないのです。それが最初の頃は特に負担に感じていました。特に、レベルの高い子が多かったので、周りはどんどん言葉を発しているのに、自分だけ発言できず、焦った記憶があります。ですが、後半になるにつれて、内容も定まってきて、テーマができてきたので、楽しく授業に参加することができました。
前半の1週間は、期待が大きかったのもあってか、自分が入ったクラス内のレベルの高さ、そして自分の実力の低さに驚き、気持ちの高低に振り回されていました。聞いてはいましたが、留学はメンタル管理も必須だと改めて感じました。私は自分で抱えきれなくなる前にカウンセラーさんや先生に相談しました。大人になっていくにつれて、「自分のことは自分で処理しないといけない」という思いが強くなり、溜め込みがちだったのですが、相談というものは、自分で言葉にすることによって、自己整理ができるし、何よりとても心が軽くなるので、これから留学に行く方も、少しでも不安に思うことがあれば、躊躇わないで、相談することをおすすめします。
1日の授業が終わった後や、土曜・日曜日は自由時間だったため、台湾を観光することができます。私は、台北101や西門、九份にいきました。そのほかにも水曜日の午後には、台北の博物館や、天文館に行く、といった軽い旅があり、楽しく中国語や台湾の文化に触れることができました。
後半の1週間は、環境に慣れてきたということもあり、自発的に中国語を発する機会がより増えたように思えます。クラスでは、周りの子の中国語レベルがかなり高く、積極的に話す子も多かった印象なので、「自分も頑張らないと!」と切磋琢磨できる環境でした。
今回の留学は短期でしたが、中国語の知識はもちろん、台湾のことや人間関係のことまで、かなり多くのことを学びました。また、今回携わってくれた・出会ってくれた全ての人に感謝します。これを見てくださっているあなたも、短期でも長期でもチャンスがあれば、留学に行くことを強くおすすめします。きっと、自身を最大に成長させられる機会になるでしょう。

私は3月、2週間の淡江大学春期中国語研修に参加しました。初めての海外ということもあり、大変貴重な体験になりました。この研修で驚いたことや生活していて必要だったもの、逆に要らなかったものをまとめていきたいと思います。
はじめに、日本と台湾の文化などの違いからくる驚いたことについてです。初の台湾で驚いたことは、電車関連です。電車の切符がコイン型だということです。はじめに改札を通るときはカードと同じようにタッチして、出るときにコイン投入口に入れるシステムでした。また、ドアが閉まるのが日本より若干速く、容赦なく締まりました。空港から師大会館までの電車では、混雑していたこともあり、なかなか入れず、目の前でドアが容赦なく締まり、驚きました。何とか電車に乗った後、驚いたことは交通事情です。駅を出ると、バイクや自転車が非常に多いです。特にバイクは大学前にずらっと並んでいました。土地的にも平たんな道が多く、自転車などで走りやすいのだと思いました。バイク関係でもう一つ驚いたことがあります。それは、師大会館近くの夜市に行った時です。道も狭く、人であふれかえっていたのですが、普通にバイクや車が通っていて、初めは命の危険を感じました。てっきり歩行者天国のようになっていると思ったので、バイクが通ろうとしたとき少し焦りました。
次に驚いたことは、大体のところで日本語が通じることです。事前情報として、日本語が通じるところが多いといわれていましたが、「日本人の外国語を話せる」と「海外の日本語を話せる」には感覚の違いがあると思っていたので、「日本人なのでは?」と疑うぐらい流暢な方が多く、驚きました。
次に商品のセール等についてです。これは事前に聞いていたことではありますが、コンビニやアパレル、ドラックストアなど、いたるところで買1送1の表記があったことです。これは一個買ったら、無料で同じ商品がもらえるという意味ですが、その対象商品が非常に多く、驚きました。特にコスメなど高めの商品も対象になっていました。コンビニではよく飲み物が対象になっていました。次に、レシートが宝くじのようになっていることです。2か月に一回、当選番号が発表せれ、200元から1000元の賞があります。海外の人も受け取ることができます。
最後に驚いたこととして、ごみ収集の違いです。日本では、一般的に地域指定のごみ袋に入れて、指定の日に指定の場所に朝持っていき、朝に収集されます。しかし、台湾では地域によって違うかもしれませんが、私が見たのは、夜に様々な色のごみ袋を持って収集車にぞろぞろと並んでいるところでした。朝ではなく夜、指定の場所に置いておき、収集車が回っていくのではなく、住人たちが収集車にあわせるという、日本とは全く違い、面白かったです。
次に必要だったものについてです。1つ目はポケットティッシュです。夜市での食べ歩きの際などに必要でした。また、台湾のトイレ事情として配管が古く、細いのもあって紙を流せません。使った紙はそばにある大き目のごみ箱に捨てます。さらに、師大会館一階のトイレには、個室に紙は置いておらず、外にトイレットペーパーが置いてあり、そこから必要な分を取ってから入る形式でした。そこから取るのを忘れ、入ってしまった時にもティッシュが必要でした。2つ目はドライヤーです。ドライヤーは部屋に1つ置いてありましたが、スイッチを押していないとオフになってしまう仕様で、非常に使いづらく、日本から持ってこなかったことを非常に後悔しました。3つ目は、ポケットWi-Fiやsimです。Wi-Fiは部屋や大学にもついていましたが、非常に繋がりづらく、ポケットWi-Fiやsimを準備しておくのがいいと思いました。4つ目は、エコバックとビニール袋です。大体の店で袋はもらえるのですが、コンビニなどはもらえないので、エコバックが必要でした。また、コンビニのホットサンドや、夜市ではエコバックよりもビニール袋の方が便利だと思いました。
最後に持ってこなくてもよかったものを紹介してきたいと思います。まず、日本からのお土産です。よくYouTubeなどでは、留学には日本のお土産を持ってきた方がいいと言われていて、折り紙などを持っていきましたが、部屋の人は全員日本人で、淡江大学の生徒と交流する授業などもないので、持ってこなくても大丈夫でした。次に日本食が恋しくなった時用のレトルト味噌汁やカップラーメンなどの日本食です。同じ部屋の人が持ってきていたのですが、2週間という短い期間で日本食が恋しくなるということがほぼなく、減らすのに苦労していました。次にシャンプーです。私は備え付けてあると知ったうえで、そのシャンプーが合わない場合どうしようと思い、持って行きました。しかし、実際は日本と台湾で水の質などが違うためなのか、せっかく持ってきたシャンプーがまったく泡立たず、使い物になりませんでした。結局、備え付けを使いました。しかし、コンディショナーはないので、コンディショナーは持ってきた方がいいと思いました。最後にいらなかったものはパソコンです。授業などで使うかもしれないと持っていきましたが、全く使うことがなかったので、期間中に他に使うことがない限り必要ありませんでした。
たった二週間という短い期間でしたが、日本語がほぼ通じず、中国語、もしくは英語を使わなければいけない環境は非常に新鮮で、それらを学ぶのに非常にいい環境でした。初めはレストランで満足に注文できませんでしたが、過ごしていくうちに分かることが増えていきました。最後まで完璧に注文することはできませんでしたが、明らかに翻訳するものが減ってきたのを感じ、嬉しかったです。また台湾に行く際には、より長い期間滞在したいと思いました。日本とは異なる文化や習慣を体験し、非常に充実した二週間でした。今回の経験を活かし、今後も積極的に海外へ出て、新しいことに触れ、挑戦していきたいです。

2024年9月から2月までの6か月間、カナダ・バンクーバーのランガラ・カレッジに留学してきました。ここでは、大学での生活と私生活についてお話ししたいと思います。最初にカナダに降り立った時に感じたことは空気が綺麗だと感じました。夏に行ったのですが、日本と違い蒸し暑くなくとても過ごしやすかったです。カナダは移民が多い組で、様々な言語を耳にすることが出来ました。更に、この6か月間で一度もアジア人差別を受けることがなかったので、海外生活に対する不安がある方には、日本と似た環境のカナダは非常におすすめです。
私のホストファミリーはイギリス人のお母さん、お父さん、息子、フリーダ(犬)の四人家族でした。クルージングしたり、島に遊びに行ったり、Thanksgiving Dayなどの家族で過ごす行事にも毎回参加させてもらい、とても貴重な経験をすることが出来ました。中でも一番の思い出は、先ほども紹介したThanksgiving Dayです。この日は家族全員集まって祝う、日本で言うお正月のようなイベントです。ホストファミリーはこの日を迎えるためにVictoriaに住むおばあちゃんに会いにイギリスやバンクーバーから3家族が集まり、約4日間滞在しました。違う場所で多くの会話が繰り広げられており、自分のスピーキング力の不足を実感したり、お酒を飲んで楽しくなったり、とても充実した4日間でした。
次にランガラ・カレッジについてです。ランガラ・カレッジでは、留学前のリーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能に基づいてクラス分けが行われます。私は8つあるレベルの中の4から始まり、その後、6までの3セッションを受講しました。1セッションは7週間で構成されており、各週『Marketing』や『Archeology』などの異なるテーマを学習するプログラムです。私のクラスは8:30~12:30までの授業だったので、午後は課題を終わらせ、その足でダウンタウンに遊びに行ったりしていました。課題自体も難しくなく、2~3時間程度で終わらせるものでした。最初は、授業中に質問するのが少し恥ずかしかったですが、他の生徒も積極的に質問していたので、クラス内はとても質問しやすい雰囲気でした。
休日には、海や美術館、島に出かけるなど様々なアクティビティを楽しみました。また、1セッションが終わると約2~3週間の休暇があり、その間に、ロサンゼルスやサンフランシスコ、シアトルなどに行きました。友達がアメリカからカナダに来てくれて、初めてシアトルで年越しを過ごしましたが、日本でも一緒にいた友達と一緒に海外で過ごすという経験はすこし不思議な感覚がありましたが、唯一無二の思い出になりました。日本から行くよりも格段に安く、約2時間程度のフライトで行くことが出来るので、おすすめです。
この留学で私は多くの貴重な体験をすることが出来ました。初めての一人海外やホームステイで不安しかなかったですが、支えてくださった先生方やランガラ・カレッジの先生方、ホストファミリー、そして友達には感謝の気持ちでいっぱいです。留学は誰しもが経験できるわけではありませんが、一人でも多くの方に挑戦してほしいと思います。今後はこの留学で得た経験を基に、将来設計に役立てて行きたいと思います。

私はカナダのプリンスエドワード島で9月の初旬から2月の中旬まで留学をしました。約半年の留学を通して感じたことを書きたいと思います。
プリンスエドワード島は小さな島ということもありとても静かで生活しやすい場所でした。9月に到着したため日差しが強く思っていたよりも暖かく過ごしやすい天候でした。私にとって初めての留学だったため、初めの頃はとても緊張しました。初日はホストマザーと挨拶をし、軽くホームステイルールの説明を受け就寝しました。私がお世話になったホームステイ先には犬が2匹、ホストマザー、モンゴル人、ブルネイ人、日本人が3人いました。ホストマザーがフィリピン人だったこともあり、英語に少し癖があり最初は質問の理解をするのに時間がかかりました。時間が経つにつれ理解できるようになりました。ルームメイトたちはとても親切で優しい単語で質問をたくさんしてくれました。彼らのおかげで、すぐに緊張が解けホームステイ先での生活を楽しく過ごすことができました。
プリンスエドワード島に到着し数日後に大学が始まりました。初めにクラス分けのためのテストがありました。そのため、自分のレベルに合ったクラスで授業を受けることができました。大学での授業は少人数制で中国、モロッコ、ベトナム、サウジアラビアなど多国籍なクラスメイトと共に英語を学びました。私のクラスではあまりグループワークは無く、自分で考え発表することが多かったです。私の先生は特に発音と文法に厳しかったので初めは、細く発音などの注意をされたのですが、回数をこなしていくうちに正しい発音で発表することができました。個人的に一番楽しかったのは、リスニング・スピーキングの授業です。この授業では2分間スピーチというお題に沿って自分の意見を、クラスメイトの前で発表することがありました。私は、あまり人前で発表することが好きではなかったのですが、英語で自分の意見を発表しクラスメイトと意見を交換するのが楽しくなっていきました。
授業が無い日は大学にあるジムに行ったり、ルームメイトとサッカーやプールなどで体を動かして過ごしていました。モンゴル人のルームメイトが大学のサッカー部に入っていたので、他のルームメイトとサッカーの応援をしに行ったりもしました。また、私の家がダウンタウンに近かったのでイベントがある時には、ダウンタウンに行き買い物などをして楽しみました。
10月の中旬にリーディングウィークという10日間ほどの休みがあったので、友人とラスベガスに旅行に行きました。プリンスエドワード島とは違いとても気温が高く驚きました。私たちはNBA観戦とグランドキャニオンに行きました。人生で一度はアメリカでバスケの試合を観戦したいと思っていたので、良い経験をすることができました。また、グランドキャニオンでは約1時間ほど迷子になり人生で1番焦りましたが、友人と協力し、なんとかホテルに戻ることができました。私は滞在2日目に体調を崩してしまい薬も持参していなかったこともありとても大変な思いをしました。旅行でも薬の準備をすることはとても大事なことだと気が付きました。
カナダに戻るとダウンタウンの周辺ではハロウィンの準備が始まり、日本と比べてとても準備が始まるのが早いなと感じました。ハロウィン当日はルームメイトとホストマザーと共に仮装をし、家を訪問し大量のお菓子を貰いました。ハロウィンの夜に大学のパーティーにクラスメイトとルームメイトと行きました。そこで会った中国人と仲良くなり一緒にジムに行くようにもなりました。大学のイベントに行くと色々な国籍の人と会話し仲を深めることができるので、イベントには積極的に参加していました。
12月に入りルームメイトが帰国しました。約3ヶ月間共に過ごしたのでとても悲しかったのですが、またいつか日本で会う約束をしたのでとても楽しみにしています。ダウンタウンとその周辺ではクリスマスの準備が本格的に始まりました。私のホームステイ先では、家の中にクリスマスツリー、とても大きなサンタクロースの置物、雪だるまの置物が飾られとても良い雰囲気でクリスマスを迎えました。クリスマス当日はたくさんの種類の食事が用意されルームメイトとホストマザーと楽しい時間を過ごしました。クリスマスが過ぎると新たにコロンビア人と日本人が私のホームステイ先に来ました。夕食の際によく会話をしたので他国の文化を学ぶ良い機会になりました。
1月に入ると大学の授業が再開しました。前のセメスターよりも1つ上のレベルの授業を受けることになり、より良い学びになりました。前のクラスに比べ英単語の難易度が上がり授業の内容を理解するのが少し難しくなりました。そのため、家で単語の意味を調べ授業の復習と予習を多くするようになりました。また、質問に対し自分の意見を素早く正確に述べることができるようになり、自身の英語力が留学当初に比べ向上したなと実感し自信に繋がりました。意見を述べることに自信を持つことができたため、疑問に思ったことを質問しより深く理解することができました。
プリンスエドワード島では2月に入りとても雪が降り大学が休みになることも多くあり、家から出られない日もありました。天候が良い日にルームメイトと友人とスノーボードに行き質の良いカナダの雪を存分に楽しむことができました。私が帰国する数日前にも友人とビリヤードなどをし、帰国までの時間を悔いなく過ごすことができました。私が帰国する前日からスノーストームがプリンスエドワード島を直撃してしまい、帰国が3日ほど遅れてしまいましたが臨機応変に行動することができ無事に日本に帰国することができました。
今回の留学を通して何事にも1回は挑戦してみることは大事なことだと感じました。何かを始めることはとても勇気のいることですが、実際にやってみると意外に通用することも多くあるので少しでも悩んだら挑戦するべきだと学びました。今回の貴重な経験を経て自身の英語力だけでなくメンタル面でも向上することができました。留学のプログラムに携わってくださった全ての方に感謝を忘れず、学んだことを行動に移していきたいです。

1. はじめに
私は2024年の9月から2025年の2月までの5ヶ月間、イギリスのリーズ大学でGeneral Englishコースを受講しながら、留学生活を送りました。日本とは異なる環境の中で、教育、生活習慣、文化の違いを実感することができました。特に、ホームステイをしながらの生活を通じて、イギリスの家庭文化や価値観に直接触れる機会がありました。本レポートでは、留学生活の中で感じたイギリスと日本の違いについて詳しく述べます。
2. 教育環境の違い
リーズ大学のGeneral Englishコースでは、4技能全てをさまざまな課題を通して勉強しますが、特にスピーキングやリスニングを中心とした授業が多く、ディスカッションやグループワークが頻繁に行われます。日本の授業では、教師が一方的に講義をする形式が一般的ですが、イギリスでは学生の自主性が重視され、授業中に発言する機会が非常に多いです。また、授業以外でも学習サポートが充実しており、リーズ大学内にあるLanguage Zoneという施設では、英語学習のサポートや交流の場が提供されています。日本では、授業外の学習支援は限られていますが、リーズ大学では積極的に活用することで、より実践的な英語力を伸ばすことができます。特に、自習スペースが充実しており、現地の学生や他の留学生と一緒に学ぶ機会が多いため、英語を使う機会が自然と増えます。また、イギリスの大学では、課題の量が多く、さまざまな課題が頻繁に課されるため、自主的に学習する習慣が身につきます。日本の大学では、試験前に集中して勉強する傾向がありますが、イギリスでは日常的に学ぶ姿勢が求められる点が大きな違いだと実感しました。
3. ホームステイと生活習慣
私の留学中はホームステイをしており、現地の家庭の中でイギリスの生活を体験しました。イギリスの住宅では、セントラルヒーティングが完備されているため、冬でも室内は暖かく保つことができます。日本の住宅では、エアコンやこたつを使って暖を取ることが多いですが、イギリスではそのような設備は一般的ではなく留学中に見ることは一度もありませんでした。また、食事はイギリスの伝統的な料理が中心で、朝食はシリアルやトースト、夕食は肉や豆を使った料理、パスタなどが多かったです。日本の食事と比べると、野菜の種類が少なく、調理方法もシンプルである点が印象的でした。また、家族とのコミュニケーションも文化の違いを感じる要素でした。イギリスの家庭では、夕食時に家族全員が集まり、一日の出来事について会話をする習慣があります。日本では、家族で食事をすることが一般的ではあるものの、個々のスケジュールによっては別々に食事をとることもあります。ホームステイ先の家族との会話を通じて、日常的に英語を使う機会が増え、異文化を直接学ぶ貴重な体験となりました。
4. 文化的違い
イギリスではパブが酒場や社交の場として大きな役割を持っています。リーズでも多くの学生が授業後にパブに集まっていました。日本の居酒屋文化と似ているがイギリスのパブの方がよりカジュアルで昼間から利用する人もいました。また、買い物の場でも違いがありました。イギリスのスーパーでは、大容量のパックで売られることが一般的であり、日本のように個包装で売られている商品は少なかった。また、キャッシュレス化が日本より進んでおり、ほとんどの支払いがカード決済で行われる。日本ではまだ現金払いが根強く残っているが、イギリスでは現金を使う機会がほとんどありませんでした。また、イギリスではチップを渡す習慣が根付いており、レストランやカフェ、タクシーなどのサービス業を利用した時に通常10%〜15%ほどのチップを払うことを求められました。しかし、日本ではチップ文化が存在せずサービス料は基本的に料金に含まれているためチップを払うべき場面や適切な金額を選択することが難しく感じました。
5. 交通と移動手段
イギリスの公共交通機関は、日本と比べて時間に対して緩く、電車やバスの遅延が毎日のように発生します。日本では、電車が分単位で正確に運行されることが一般的ですが、イギリスではバスの時刻表があまり厳密でないことがあり、予定通りに移動できないこともあります。そのため、移動の際には時間に余裕を持つことが重要です。また、イギリスでは徒歩や自転車を利用する人が多く、リーズの街中でも多くの人が歩いているのを見かけます。日本では、都市部では電車やバスの利用が主流ですが、イギリスでは日常的に歩く習慣が根付いていると体感しました。
6. 価値観と人間関係
イギリスでは、個人の意見や権利が尊重される文化が強く、授業や日常生活の中でも「自分の考えを持つこと」が求められます。日本では、周囲との調和を重視する傾向があり、相手の意見に合わせることが多いですが、イギリスでは「自分はどう思うか」をはっきり伝えることが重要視されます。実際に授業中に先生から意見を求められることが多くて驚きました。また、日常的な会話の中でも「Please」や「Thank you」を頻繁に使う習慣があり、これらの言葉を使うことで円滑なコミュニケーションが生まれると感じました。ホームステイ先でも、これらの言葉をイギリスではよく使うと教えられました。些細なことでも感謝の言葉を伝えることが自然な文化として根付いていると感じました。さらに、友人関係においても、日本よりもカジュアルな雰囲気があり、初対面でも気軽に会話を始めることが多かったです。
7. まとめ
イギリスでの留学生活を通じて、日本とは異なる教育環境、家庭文化、交通事情、価値観を体験しました。特にホームステイをしながら現地の生活に溶け込むことで、言語だけでなく文化的な理解も深まりました。この経験を通じて、異文化に対する柔軟な姿勢を持ち、多様な価値観を受け入れる重要性を学ぶことができました。例えば、日本では授業中に発言する機会が少なく、先生の話を静かに聞くことが一般的ですが、イギリスでは自分の意見を求められる場面が多くありました。最初は戸惑いましたが、授業に積極的に参加することで、相手に自分の考えを伝える力が身についたと感じます。また、ホームステイでは、食事のときに家族と一緒にその日の出来事を話し合う習慣があり、最初はうまく会話に入れませんでしたが、次第に自分の意見を伝えたり、質問したりすることで、自然にコミュニケーションが取れるようになりました。このような経験を通じて、自分の考えをしっかり持ち、それを伝えることの大切さを実感しました。留学は単なる語学学習ではなく、新しい環境での適応力や異文化理解を深める貴重な機会であると理解しました。また、日本に帰国した後も、この経験を活かして国際的な視点を持ち続けたいと思います。異文化の中での生活は簡単ではありませんが、それを乗り越えることで自分自身の成長につながると強く感じました。

私は2024年9月から2025年2月までの約半年間カナダにあるプリンスエドワード島大学(UPEI)へ留学をしていました。私は元々、商業高校出身で高校まではひたすら野球漬けの日々を送っていました。野球部を引退した後、何か新しいスキルを獲得したいと考え、そのとき思いついたのが英語でした。そして大学で留学をすることを決意しました。この決断が私の人生の大きな1ピースができるきっかけとなりました。
プリンスエドワード島での生活は刺激的な毎日の始まりでした。まず通りすがりの人に挨拶をされることが日常的にあり、驚きました。それだけでなく私が歩道を歩いているときに、同年代ほどの若者が車の中からhey broと声を掛けてくれたこともありました。日本では経験したことがなかったため、とても印象に残っています。学校が始まるとお昼に食べるサンドウィッチを毎朝作り、持っていくため朝は忙しかったです。
クラスは様々な国からきた学生で構成されていました。中国やモロッコから来た学生は独特な発音で英語が違う言語のように感じ、初めは聞き取るのに苦労しました。先生はカナダ人であったため発音に癖がなく話が聞き取りやすかったです。授業は日本の中学校で習うような基礎的な文法の復習がメインでしたが、先生からよく単語の意味や文脈について質問されるため、英語で瞬発的に発言する力や説明する力が鍛えられました。また学生の授業に対しての姿勢が日本の学生とは違うという点に気づきました。多くのクラスメイトから授業を真剣に取り組んでいるだけでなく、自ら挙手をして発言するなどの授業に自ら入り込んでいくような積極性を感じました。日本では高校、大学と上がるにつれて授業中に自ら挙手をして発言するような光景が減っていると思います。私はそれに刺激を受け、他国から来た学生に負けないよう積極的に発言することを心がけていました。そのため英語を話す機会も増え意見や気持ちをうまく言葉にできるようになっていき、英語力が向上していることを実感しました。
ホストファミリーとは、ハロウィンの仮装やパーティー、クリスマスには家にオーナメントなどの装飾を施しみんなでごちそうを囲むなど初めての経験ばかりでした。夕飯時には毎日ルームメイトと会話をしながら食事をとっていました。ジョークを言い合う日もあれば深いテーマについて話し合う日もあり、夕飯の時間は特に思い出深かったです。ある日ホストマザーが言葉の重要性についての話をしてくれました。私が「親や家族に対して愛情や感謝の気持ちがあったとしても言葉で伝えることがあまりない」と言うとホストマザーからなぜ伝えないのか質問されました。家族に対して愛していると言うことが照れくさいと思う人は少なくないと思います。しかしホストマザーに「親が愛情を持って接してくれるのに対して、愛情で返すことが子供の役目だ。親に直接その気持ちを伝えることができなくなってから後悔するのでは遅い」と言われました。この言葉は特に印象に残っており、今でも鮮明に覚えています。ホストマザーとはカジュアルな内容の話から、人としての在り方についても話をしました。
年が明け新学期になるとクラスのレベルが上がり、クラスメイトも変わりました。授業はライティング、リーディング、会話の3つの授業がありました。ライティングではエッセイの構成や書き方を細かく分析し、何度も書く練習をしました。先生が直接間違いを訂正してくれるため適切な表現を学ぶことができました。リーディングの授業は読み物の内容が前期よりも専門的な内容になり、使われている単語のレベルも上がったため分からない単語やイディオムも増えました。それらを覚えるため、メモに書き留めて日常会話で使うことを意識すると知識の定着が早いと感じました。英語学習にはインプットとアウトプットを並行して行うことが大切だと思いました。
休日にはホストマザーと地域のボランティアに参加する機会もありました。老人ホームでボランティアを行った際はシャンプーやボディーソープなどの日用雑貨や本や雑誌などを寄付しました。5箱ほどのダンボールがいっぱいになる程の量を持っていきました。車からそれらの荷物を全て運んだため疲れましたが、老人ホームの職員の方々が喜んでくださいましたのでとてもやりがいがありました。留学が終わりに近づくと友達とパーティーやスノーボードを一緒に行くこともありました。楽しかった思い出ができただけでなく、遊びを通して英語を話すことに自信がついていきました。スノーボードをした帰りにはモロッコ人の友達が、アルバイトをしている日本食レストランへ招待してくれました。その日本食レストランは想像以上に繁盛しており日本食は世界的に人気で愛されていることを改めて感じました。食文化以外にもマンガが特に人気で日本に住んでいたときよりも好きなマンガについて話すことが多かったと思います。また、本屋の文房具コーナーに置かれている文房具はほとんどが日本の製品でした。私はこの留学で日本のブランド力の高さにも気づくことができました。
プリンスエドワード島での生活で私は英語力の向上はもちろん、人との関わり方や関係性の大切さについても学ぶことができました。この半年間で得た学びや思い出は生涯忘れることのない宝物です。最後にこのようなすばらしい経験ができたのはホストファミリーや現地でできた友達だけでなく、家族や国際センターの方々など、この留学に関わった全ての人たちのおかげで成り立っています。全ての出会いに感謝しその気持ちをこれからも忘れずに日々成長していきたいです。またこの留学を起点として更に英語力を向上し、次のステップへ踏み出したいと思います。

<春セメスター>
オランダでの授業が始まるのは2月19日からで、私たちは2月15日にオランダに到着しました。まずは鍵を受け取り自分達の家に行き、ブランケットや布団が無いので買いに行きました。初めの一週間くらいは緊張や慣れない環境、時差ボケなどで相当疲れていて、夕方の4時に眠ってしまって、夜中の2時、3時に起きるという生活をしていました。また、初めの一週間は私の部屋はキッチンの電気が一切使えなく、料理もできませんでした。しかし、業者が来てコンロをIHに変えてくれたので使いやすくてよかったです。
イントロダクションデイでは、キャンパスツアーやオランダについてのクイズを楽しみました。また、バスでどこかの施設へ行き、アスレチックやシューティングゲーム、斧を投げたりして楽しみました。今思うとこの時は全然まともに英語を話せてなかったと思います。
私が春に取った授業は、Beginners English, Culture, Marketing for beginners, Dutch for beginners, Business English の5つです。
Beginners Englishは週3回あり、ほか4つは週1回の授業でした。大体、朝に授業に行って、昼頃には家に帰るという日が多かったと思います。Beginners Englishでは、発音やa,an,theの違いなど英語の基礎的なことはもちろん、Job interview やメールの書き方、履歴書の書き方、プレゼンテーションのやり方についても学びました。テストはJob interviewとオランダでの留学生活についてのプレゼンテーションをしました。私は特にJob interviewが苦手であまりうまくいきませんでした。
Cultureの授業はヨーロッパやオランダの文化、食べ物について先生が紹介してくれたり、カルチャーショックやホフステードの六次元モデルなどの事も学んだりしました。テストはなく、毎週、どんなことをして何を学んだのか、どんな感情かなどの日記を書いておいて最後に提出するという物でした。また、オランダでカルチャーショックを受けた物の写真を10枚撮る、文化について話しているテッドトークを見つけてそれを要約するというのもありました。大変でした。
Dutch for beginnersでは、基本的なオランダ語について学びました。英語すら分からない私にはとても難しくて何度も諦めようかと思いました。毎授業、頭にハテナマークが50個くらいという感じでした。テストは筆記テストと、スピーキングテストでした。一緒に授業を取っている友人と集まって勉強し、無事に合格することが出来ましたし、いい成績を取れて飛んで喜びました。ちなみに筆記テストはチャンスが2回あり、1回目で合格できなかったらもう1度テストを受けることが出来ます。私の友人の1人が1回目で合格できなかったので、一緒に勉強した友人みんなで2回目を受けたのはいい思い出です。
Business Englishは、会議やプレゼンテーションについて学びました。テストもその内容です。個人的に会議についての授業が楽しかったです。先生がお題を出してくれて、店長やマーケティング部門、会計部門などそれぞれ役を決めて企業の問題をどう解決するか会議で決めるという物でした。プレゼンテーションはBeginners Englishでも学んでいたので簡単に感じました。
私は、2月にはドイツに1ヶ月研修していた友人とパリに行き、夜行バスの中にスマホを置いてきました。観光どころではなかったです。運が良いことにそのバスは私たちを下ろした後に倉庫に行っていたようで、誰にも盗まれず、無事に見つけ出すことが出来ました。運転手の方に英語が通じず、バスの中を確認したいと主張しても「ダメ」と言われ続け、15分くらい格闘していたと思います。最終的に確認させてくれ、スマホを見つけてバスから出てきた時には友人、私、バス運転手の3人でハグをしました。本当に見つかってよかったです。
4月下旬から5月上旬まで、春休みがあった為、私、台湾人2人、フィンランド人の4人で10日間の旅行に行きました。ドイツ、スイス、イタリアの3カ国を巡りました。英語しか話せない環境で不安も疲れも感じましたが、本当にみんなが優しくて、楽しい以外の何でもなかったです。週末にはオランダ国内を観光したりもしました。チューリップを見に行ったり、ミッフィーで有名なユトレヒトに行ったり。1人一品持ち寄って家でパーティーしたりバドミントンしたりもしました。
6月中旬には私たちはもう夏休みに入っていました。夏休みには、ホロコーストの歴史について興味のある私と友人で、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、スロバキア、チェコ、ドイツを14日間で旅行しました。ポーランドにはアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所があり、オーストリアのザルツブルクはヒトラーが好きだった場所、ドイツのミュンヘンにはダッハウ強制収容所があるため行きました。旅行に行く前には2人でよくそれらの歴史についてのドキュメンタリーや映画を観ました。映画などでは画面が全体的に暗いものが多く、悲しみや残酷さを表現していると思うのですが、現実は怖いくらいに明るく、晴天で、そこに恐怖のようなものを感じたのをよく覚えています。1ヶ月先のバスを予約していたり、ホテルにパスポートを忘れたり、ホテルのカードキーを落として探し回ったりしましたが、めんどくさがりでテキトーな2人でやり切ったことが何よりも嬉しかったです。フィンランドとパリにも行きました。
<秋セメスター>
私たちは、8月下旬にあったイントロダクションデイに再び参加しました。友達を作るために。内容は春セメスターとほとんど同じだったと思います。
9月初旬にはもう授業が始まり、私はCambridge English, International Customer Insight, International Event Management, Current Affairs という授業を取りました。
Cambridge Englishは、週3回あり、ビジネスについて英語で学んだり、意見を交換、プレゼンテーションしたりしました。英語の文法や使えるフレーズなども多く学びました。テストはなく、先生が出している課題を毎週解くというPortfolioでした。Reading, Writing, Practice、そしてオンラインの課題もありました。最終的にはみんな70〜100ページほどのPortfolioになっていたと思います。大変でした。
ICIは週に1回でしたが、1回の授業時間が長かったです。2時間半ほどあった気がします。ここでは、マーケティング戦略について毎週学びました。私もこのような戦略にまんまと引っ掛かっているのかと、授業内容はとても面白かったです。この授業でもLogbookを作成する必要があり、自分が選んだ企業と毎週学ぶマーケティング戦略を結びつけて文章を書きます。9つほどトピックがあり、1トピックごと400 words以上書く必要がありました。また、グループプレゼンテーションもあり、自分達が選んだ企業について、マーケティングでの問題点を見つけ、どんな戦略を使えば解決できるかという事をプレゼンしました。プレゼンを作るためにするグループミーティングが何よりも辛かったです。
IEMも週に1回でしたが授業時間が長かったです。グループで協力してイベントを作ってマネジメントするという授業でした。私たちは地元の中学校で自分達の文化をクイズなどのゲームを交えて紹介するというイベントをしました。子どもたちが本当に良い子たちで積極的で救われました。最終課題は、そのイベントについての25分間のビデオを作るというもので、予算や目的、イベントの映像などを組み合わせて製作しました。また、授業での態度や積極性は先生が評価するのではなく、グループのメンバーがそれぞれのメンバーを評価するという形式で、面白いなと思いました。
10月中旬から11月初旬まであった秋休みには、トルコに行きました。クリスマス前には再びハンガリーに行き、クリスマスシーズンにはドイツ、フランス、ルクセンブルクのクリスマスマーケットを回りました。ちなみに冬休みは12月中旬ごろから始まりました。年末年始は友達と家で過ごしました。オランダの年始はすごくて、一般市民が花火を打ち上げまくっていました。毎年死者も出るくらい危険なので行く際には気をつけてください。1月にはスペイン、ポルトガルにも行きました。友達と今までの留学生活について話し、もうこの生活が終わるという事を信じたくなくて泣きそうでした。
旅行の思い出ももちろん大切ですが、みんなでご飯食べてパーティーしたり、散歩したり、ただの 日常ですらも本当に尊くて愛おしい時間でした。オランダに着いて最初の頃は英語を話すのが怖くて、レストランで注文するのすら怖かったけど、今では英語を話す恐怖心は無くなったと思います。英語力が上がったということもあると思いますが、度胸がついたのかなともこの留学の経験を通して思います。春セメスターはとても日本が恋しくて、毎日のように「帰りたい」と言っていたと思いますが、英語を喋らなくてはいけない、よく分からない世界に自分を放り込んでよかった、辛くても諦めなくてよかったと本当に思います。秋セメスターは日本に帰りたいという思いはあまりありませんでしたが、トラブルや辛いことは多かったと思います。どうにかならなかった、解決しなかった問題もありました。
良いことも悪いことも、こんなに素晴らしい思い出たちを、時間が経つことで思い出せなくなっていくことが悲しいです。日本に帰った時も、友達に会ったり、一歩歩いたりする度に自分はもうオランダにいないし、家族のように過ごした友人にも簡単には会えなくなるのだと再認識してとても辛かったです。日本の友人や家族には、「また日本とか友達の国に行けば会えるじゃん」とよく言われますが、そういう話ではないのです。こんなに濃くて、こんなに心が動いて色々な事を感じた1年は初めてで、この先それを超える1年があるかはわかりません。とにかくこの1年は私にとって宝物です。ありがとうございました。

















