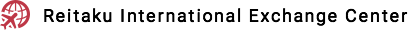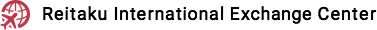愚者は教えたがり、賢者は知りたがり
- ドイツ語・ドイツ文化専攻2年 赤羽 虹咲
- 2018/02/07
留学して四か月が経ち、いつもと違うと思っていた景色が当たり前のように感じてくるような感覚で日々を過ごしている。けれども一歩外を出て、いろんな人たちと会話をするといつも新しい発見や考え方に驚かされたり、自身の新たな一面や再発見をしている。今回の留学体験記はその会話の中で見つけた小さい発見、それに関しての私自身が感じたことを書いていく。
■コンプレックス
自分が苦手とすること、自分と他者を比べてたときに時に不快になったりマイナスな気持ちを感じたりするものが私はコンプレックスと考えている。ここドイツではどんな人がどんなコンプレックスを抱えて生きているのか、を聞いてみた。日本ではよく 「学歴コンプ」 と言われるものがあるが、ロストックにいる人はあまり感じないらしい。理由はここロストックにいる人は学生が多く、というよりはロストック大学を中心にして、様々な教科を勉強しにきた学生が多い。私と同じくらいの年代でここロストックにいるということ=学問を勉強しにきた人、もしくは音楽を勉強しにきた人、と認識されるために学歴はあまり関係がない。ドイツの他の街から来たという人にも同じような質問をしたら、あまり感じたことがないし、そういう考えをしたことがないと話していた。なんでもそれはドイツの教育システムが関係しているそうで、「大学で勉強するか、専門で早々と手に職をつけるか」がドイツに住む人の将来の指針の基準だそうだ。それを決めるのが日本よりも速いため、日本と似ているようで似ていないなと感じた。
それよりも人種や身長といった外見やその人が話す言語で差別をしたり、されたりがやはり多いのでコンプレックスと聞くとそこに考えをめぐらせる人が多くいた。イラクからきた学生からの勧めで彼らのグループで話をしたところ、様々な話が聞けた。中東からドイツに来る学生はアルバイトで生活費を稼ぎながら学業をする、というのが多い。彼らの上司とは言語の壁からきちんとしたコミュニケーションをとれず、それによるストレスが互いに溜まりやすく、互いの悪口を言い合っている状態であるし、私も何度かそれを目にしたことがある。日本のイジメは陰湿で世界的にみて、それは異常だ、というが似たようなことはどこでも起きていて、絶対になくなったりしない不変のものだと考えた。
■スキンヘッド?禿げ?ハゲ?
日本で秘書に「このハゲーーー」と罵倒した等で問題になったことはまだ記憶に新しいところだが、見ためで差別を強列にするならば、髪はどういう風に見ているのかと疑問がでる。日本では髪が薄い、というとあまり良い印象を持たない。海外ではスキンヘッドと認識され、映画ではスキンヘッドのマッチョがアクションをしているカッコいいイメージがあるが実際にそうなのかと思い、聞いてみたところ、実はそうでもないらしい。というのも髪が薄くなり始める時期が早い人では二十歳ころから始まっていたりする。気にしていないように他人には振る舞ってはいるものの、心の中では恥ずかしいし、触れられたくないと考えている人がほとんどであった。私はそうとも知らずに「今日寝坊しちゃって癖っ毛直さずに外出ちゃったよ~」と言い続けていたのである日「癖っ毛つくぐらいの髪があってうらやましい」と本気で相手に深刻な顔つきで言われてしまった。先ほどの人種の違いから起きてしまう喧嘩などでも相手の髪に関する悪口を言わないのは、お互いにとってのダメージが大きいからだそうだ。自分では軽い話と思っていても相手にとっては違うということを学ぶ機会になった
■弱点と課題
以前まで私はここロストックに来て以来、苦しい思いしかしていないと感じていた。最近になり、なぜそう思うのかが理解できた。ロストックで私は様々な人といろんな話をすればするほど、自分の中で感じること、意見や考え方の再発見をしている。とはいうものの自分の中で確たる芯のようなものが出来ていないので、様々な人の様々な意見にくっついたり離れたりしているような状態である。そんな状態であるにも関わらず、私は慢心したり、天狗のように鼻高々としていた。しかし、会話を重ねるごとにある違和感があり、また簡単なテストでさえも時に上手くいかない時があった。自分では出来る、と思っても実際にはそうでもないということに気付いた。
友達や知らない人と会話をする時に感じる違和感とは、相手の話していることは理解できるが内容が全く理解できないのだ。例えば、インド人と話をしている時になぜ牛を食べないのか、という話をしたのだが、私は全く理解できなかった。食べない理由の一つとして宗教であったが、宗教の話がベースにあるのでそれを踏まえての説明であったため理解が出来なかった。私は言語が理解出来れば、あらゆる会話をすることができると思っていたがそうではなく、話の全体(システム)が理解できないと会話が成り立たないということに気付いた。ならば、今迄自分はどうやって新しいことを理解してきたのだろうか。全く知らない未知のことをどうやって学んできたのだろうか。それは他者がいたからである。私はこれまで、知らず知らずのうちに人の助けを借りて会話をしていたのだ。これはすごく恥ずかしかった。虎の威を借る狐とはまさにこのことだった。他人の考え、意見、知識をあたかも自分がそう考えたかのように、またそう知っているかのように振る舞っていただけであった。それが私の弱点であり、これからの課題でもあるのだ。ひたすらに語学を上げれば良いということではない。つまり、言語が出来なければ、話が理解できないし、かといっても話の基礎となる様々な事柄に関する知識がなければ内容も理解出来なのだ。自分が学んできた学問の基礎が違う中で、知識をつけて、自分の意見を発していく、あまりにも単純であり、当たり前のことに今ようやく気がついたのだ。自分がどれほど世間しらずであったかを学んだのだ。
外国人ではなく一人の人として接する、その時になにを話して、どう自分の意見を発していくのかが大切である中で、自分の芯がいかに重要であるかをここ数日で学んだ。


現地レポート 一覧へ