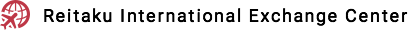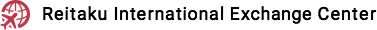約1年間のドイツ生活を終えて
- 外国語学部 ドイツ語専攻 池田 夏望
- 2025/10/22
2024年10月からドイツ・チューリンゲン州イェーナにて語学留学を開始し、前期・後期を通して約1年間にわたり現地で生活してきました。慣れない環境の中で数々の困難に直面しながらも、少しずつ生活に順応し、自分なりのペースで学びと成長を重ねた日々だったと思います。
食生活では現地の食材に工夫しながら、少しずつ自分らしいスタイルを確立しました。特に印象に残っているのは、ドイツで購入した炊飯器を活用して、日本風の料理に挑戦したことです。ミルヒライス用のお米を水で炊き、昆布だしやはちみつ、油を加えることで日本の味に近づけたり、ケチャップライスや炒飯も炊飯器で再現したりするなど、限られた環境でも試行錯誤しながら楽しむことができました。ただし、ドイツでは水質が日本と異なり硬水が主流のため、炊き上がりの風味や食感が思うようにいかないこともありました。そのため、私はブリタの浄水器を使って軟水に近づけた水を使用するようにし、日本の米に近い食感を再現する工夫をしました。
また、野菜を冷凍ストックしてすぐに調理できるようにするなど、効率面でも工夫を重ねました。さらに、日本の調味料を持参したことも食生活の充実につながりました。私の場合は、胡麻油と香味ペーストが特に重宝しました。胡麻油は炒め物に風味を加えるのに便利で、香味ペーストは肉料理やスープのベースとして活用できました。ほかにも、日本のマヨネーズは現地のものと風味がかなり異なり、好みに合わず苦労することもあるため、持参して正解だったと感じました。こうした調味料があることで、限られた食材でも「自分の味」でほっとできる瞬間が増えました。
授業への集中に関しては、特に片頭痛に悩まされることが多くありました。気候や生活リズムの変化に体がうまく適応できず、痛みに耐えながら授業に出席する日も少なくありませんでした。そのような状況でも、ドイツ国内外への旅行を楽しみに計画することで前向きな気持ちを保ち、薬を用いながらなんとか乗り切ることができました。
また、春休みに現地企業でのインターンシップに参加する機会にも恵まれました。限られた語学力での実務経験は決して容易ではありませんでしたが、職場でのコミュニケーションを通して語彙力や表現力が鍛えられたほか、ドイツならではの働き方や職場文化を肌で感じる貴重な経験となりました。
住居はWG(シェアルーム型の寮)で、最初は4人で共同生活を送っていましたが、前期終了後に1人が退寮し、後期は3人での生活となりました。人数が減ったことで共有スペースの使用状況も変化し、より静かで落ち着いた雰囲気の中で過ごすことができました。それぞれの生活リズムを尊重し合える距離感が心地よく、無理なく自然な関係を築けたことは大きな安心感につながりました。
交通面では、車両ごとに行き先が異なる電車に乗り間違え、知らない場所へ向かってしまったことがありました。この経験以降は行き先の表示を習慣的に確認するようになりました。しかし、慣れてきた後もつい忘れてしまうことがあり、日本とは異なるシステムを実感しました。
留学前は、海外で一人旅をすることに対して大きな不安を抱いていました。見知らぬ土地で自分の身を守れるかどうか、自信が持てず危険な目に遭うのではないかという恐れが常にありました。しかし現地での生活を重ねる中で、徐々に自分自身で行動する力や判断力が身についていきました。今では、治安の悪い地域を事前に調べて避ける、夜間の外出を控えるなど、自分なりに安全対策を講じながら、積極的に一人旅を楽しめるようになりました。どうしても治安が気になる場所へ行く際は、友人と一緒に行動するなど柔軟に対応しています。こうした経験を通して、「一人でいること」への恐れが、「自分で選び取る行動」へと変化したのだと感じています。
また、ドイツで過ごす中で人々の親切さにも大きな驚きと感動がありました。駅や街中で重いスーツケースを持って乗り物に乗れずに困っている人がいると、すぐに手を差し伸べてくれる姿を何度も目にしました。日本ではあまり見かけない自然な助け合いの文化に触れることで、言葉を越えた人とのつながりの温かさを実感しました。
振り返れば、語学力の向上だけでなく、異文化の中での適応力や課題への向き合い方、人間関係の築き方など、多くの「生きる力」を育むことができた1年間でした。この経験は今後の人生においても、深い意味を持ち続ける大切な糧となると感じています。
現地レポート 一覧へ