
簿記というと「なんだか難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし実は、簿記には社会のしくみやお金の流れを理解するためのヒントがたくさん詰まっています。 経営学部の倍 和博先生は、学生一人ひとりが「簿記って面白い」「社会とつながっている」と実感できるように、身近な題材や実務の視点を取り入れながら授業を行っています。前編では、1年次生向けの「簿記原理」の授業に参加し、その魅力やおもしろさをレポートしていきます!

学生目線に寄り添う授業の空気
経営学部で開講されている「簿記原理」には、簿記を初めて学ぶ1年次生が多く集まります。
教室を訪れてまず印象的だったのは、倍先生の語り口です。難しい専門用語をできるだけ避け、身近な例え話や図を使いながら、一人ひとりの理解を丁寧に支えていました。
学生に問いかけ、対話しながら進む授業は、教室全体に温かく心地よい空気を生み出しています。簿記が「一部の人の専門知識」ではなく、社会のしくみやお金の流れを理解するための入り口であることを自然に感じられる時間です。
"払いすぎ・もらいすぎ"を整える会計の工夫

-
この日のテーマは「費用・収益の繰延(くりのべ)と見越(みこし)」。一見難しそうな内容ですが、倍先生は、「簡単に言えば、"払いすぎ"や"もらいすぎ"の話なんです」と切り出しました。
たとえば、10月に1年分の保険料を前払いしたとします。実際には来年分も含まれているのに、それをすべて「今年の出費」として記録してしまうと、正しい利益が見えません。そこで簿記では期間ごとに分けて記録する必要があります。
黒板にカレンダーの図を描き、さらに資料をPCで共有しながら「今年の分」と「来年の分」を色分けして、視覚的にわかりやすく説明していきます。
「実際にお金が返ってくるわけではありませんが、帳簿上では"取り消す"という操作を行います。これは、帳簿という仮想の世界で利益を正確に捉えるための"フィクション"なんです」こうして丁寧に説明されると、複雑に思える会計の仕組みも自然と理解できるようです。学生たちは真剣に耳を傾け、熱心にメモを取っていました。
中華料理店から学ぶ、簿記のリアルな風景
-
簿記の仕訳には常に「背景」と「理由」があります。倍先生はそれを伝えるために、できるだけ身近な題材を取り入れていました。
たとえば、「お客さんから"先にもらった"お金は、まだサービスを提供していないから"収益"にはならず、『前受収益』という負債になる」「まだ払っていないけれど今期に関係する出費は、『未払費用』として扱う」といった事例が紹介されました。

さらに中華料理店を例に、「店主がポケットマネーで支払った場合は"個人のお金"なので、店の経費とは分ける必要がある」と説明します。
専門的な内容も、生活の中の風景とつながることで、ぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。
反転学習で広がる発見! "問い"から始まる理解
この授業では「反転学習」のスタイルが取り入れられています。学生はオンデマンド授業で予習し、教室では演習や応用的な解説に取り組みます。

-
「動画だけでは理解が難しい内容も多いので、対面での解説や実例を交えることで理解度が上がるんです」と倍先生は語ります。テーマが一区切りすると、「さあ、この問題を解いてみましょう」と声をかけ、学生は問題集に取りかかります。
わからないことがあれば、すぐに手を挙げて質問できる雰囲気があり、先生やTA(ティーチング・アシスタント)、SA(スチューデント・アシスタント)が教室内を巡回して個別にサポート。学生同士で教え合う姿も見られ、学び合いの文化が根づいていることが伝わってきました。
授業の最後には、簿記試験や進路についての話もあり、「どんどんチャレンジしてほしい。落ちても構いません。受けてみること自体に意味があるんです」と、やさしく背中を押していました。
数字の向こうに人が見えてくる
-
取材を通して感じたのは、この授業が単なるスキル習得にとどまらないということです。
倍先生が何より大切にしているのは、「学生が自分の意思で学び、自らの未来を切り拓いていくこと」。
「わからないことをそのままにしない」文化づくり、補講による学び直しの機会、個別に寄り添うフォロー体制、そして学生同士が自然に助け合う"小さなコミュニティ"。こうした仕組みが、学生の自発的な学びを支えています。

また、簿記原理は大学院の税理士プログラムへの第一歩としても位置づけられており、会計の学びが将来の進路やキャリアにもつながるように設計されています。
「会計の勉強を通じて、自分の強みが見えてくる。それがやがて"人の役に立つ"実感にもつながるはずです」倍先生の言葉には、教育者としての真摯な想いが込められていました。







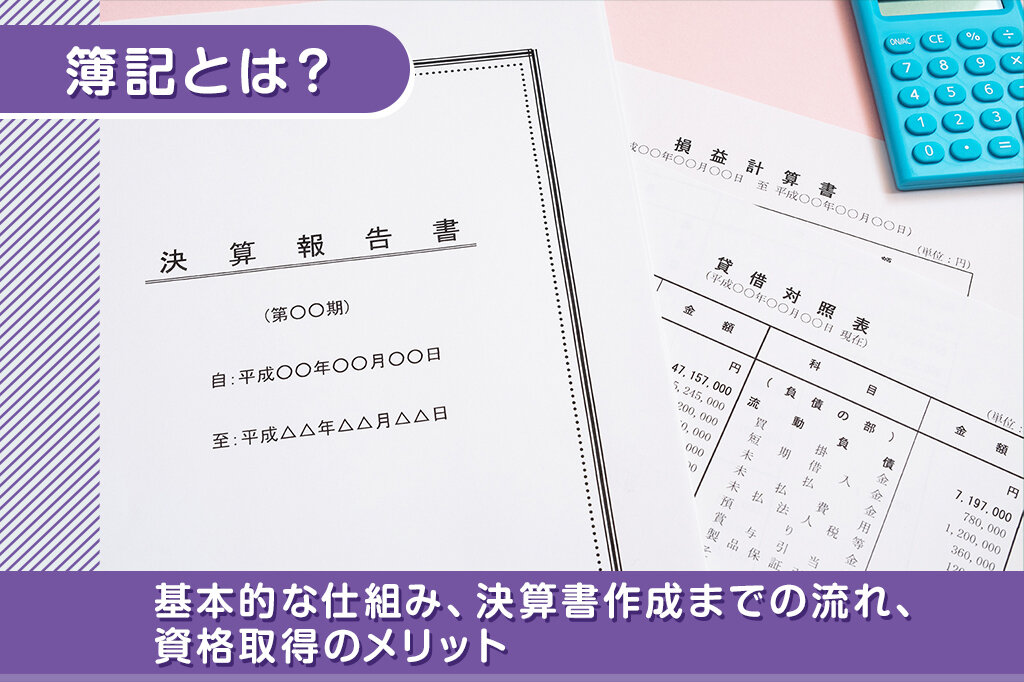



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

