
簿記というと「なんだか難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし実は、簿記には社会のしくみやお金の流れを理解するためのヒントがたくさん詰まっています。 経営学部の倍 和博先生は、学生一人ひとりが「簿記って面白い」「社会とつながっている」と実感できるように、身近な題材や実務の視点を取り入れながら授業を行っています。後編では、倍先生へのインタビューを通じて教育への想いや授業づくりの考え方を深掘りします。

会計の授業は「社会の見方」を学ぶ時間
「簿記原理」という授業を通して、学生たちに伝えたいのは"社会の見方"です。

-
簿記は定型的な仕訳から始まりますが、どの取引をどう認識し帳簿に記録するかは、背景の理解が不可欠です。企業やお店の動きを客観的にとらえる「共通言語」とも言えます。
特に初めて簿記や会計に触れる学生が大半であるこの授業では、専門用語を避け、背景を丁寧に説明することを心がけています。たとえば「費用・収益の繰延と見越」といったテーマも、「払いすぎ」「もらいすぎ」と言い換えることで、感覚的に理解しやすくしています。
また、実務の感覚を重視しているのも麗澤大学の特長です。経営学部には実務経験を持つ教員が多く、それぞれが現場の視点を授業に反映しています。私自身も、会計事務所での勤務経験を踏まえ、同じ取引でも目的や状況によって処理が異なることを伝えています。だからこそ、学生には"型"を覚えるだけでなく、"なぜその処理を選ぶのか"を考える力を養ってほしいのです。
「できる」ではなく「わかる」を大切に
-
授業では、保険料や売上、家賃といった身近な題材を取り上げながら、抽象的な概念を具体的に伝えています。生活に結びつけて考えることで、簿記を"自分事"として捉えやすくなるからです。
また、この授業は反転学習の形式を採用しており、まずはオンデマンド動画で予習したうえで、教室では30分の解説と10分の演習を組み合わせるなど、理解を深めるための工夫をしています。動画だけでは補えない部分は、対面で補足説明や図解を交えてフォロー。単なる「わかったつもり」で終わらせず、確かな理解へと導いています。


-
さらに、授業中のコミュニケーションも重視しています。私は、学生からの問いに対してすぐに答えを提示するのではなく、語りかけるようにヒントを投げかけ、自ら考える時間を大切にしています。こうしたやり取りを通じてこそ、深い理解や記憶の定着が生まれると感じているからです。
また、TAやSAに自由に声をかけられることはもちろん、学生同士が気軽に相談し合えるような空気づくりにも力を入れています。わからないことをそのままにしない文化が、教室の中で自然と育まれています。
私自身も、学生の表情や反応をこまめに観察しながら、その場で授業の進行を柔軟に調整しています。「わかった!」という小さな気づきを見逃さず、教室全体に学びの輪が広がっていく過程を何より大切にしています。
「会計」はどんな人生にもつながっている
「簿記原理」は、会計教育の入り口です。1年次のうちに日商簿記2級の取得を目指し、2年次以降は専門的な会計学や財務諸表論へとステップアップできるよう構成しています。その先には、大学院で税理士試験の受験科目に挑戦する道も開かれています。
-
しかし、簿記を学ぶ価値は資格取得に限りません。企業で働くうえでお金の流れを読む力は不可欠ですし、個人の生活でも家計管理や資産形成に役立ちます。数字を正しく読む力があれば、見える景色が変わるのです。
さらに授業では、IFRS(国際会計基準)やUS-GAAP(米国会計基準)と日本の会計基準(J-GAAP)の違いについても触れることがあります。基準の比較を通じて、日本独自の会計思想や社会構造への理解も深まります。

会計は単なる数字の知識ではなく、社会を理解するためのツールであり、その奥深さを学生に感じてほしいと考えています。
小さな関心からでも、学びは始まる
私は、学生が自分の意志で学ぶことを何より大切にしています。誰かに言われたからではなく、自分の中から湧いた関心に従って、行動してほしいのです。
簿記や会計に少しでも興味があるなら、ぜひ大学で学んでみてください。わからなければ何度でも聞けばいい。質問して、考えて、また挑戦する――その繰り返しが学びを形づくります。

-
私たち教員は、いつでも学生の背中を押す準備をしています。教室外での質問対応や、夕方から夜遅くまでの個別相談もあります。小さな悩みから将来の進路まで、対話の積み重ねが学生の力になるのです。
簿記は覚えることも多く、時に難しく感じるかもしれません。しかし、その先には「わかる喜び」があり、自分の強みにも気づき、やがて誰かの役に立つ実感へとつながっていきます。
この授業が、数字の向こうにある社会や、自分自身の未来に目を向けるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
私たち教員は、いつでも学生の背中を押す準備をしています。教室外での質問対応や、夕方から夜遅くまでの個別相談もあります。小さな悩みから将来の進路まで、対話の積み重ねが学生の力になるのです。
簿記は覚えることも多く、時に難しく感じるかもしれません。しかし、その先には「わかる喜び」があり、自分の強みにも気づき、やがて誰かの役に立つ実感へとつながっていきます。
この授業が、数字の向こうにある社会や、自分自身の未来に目を向けるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。







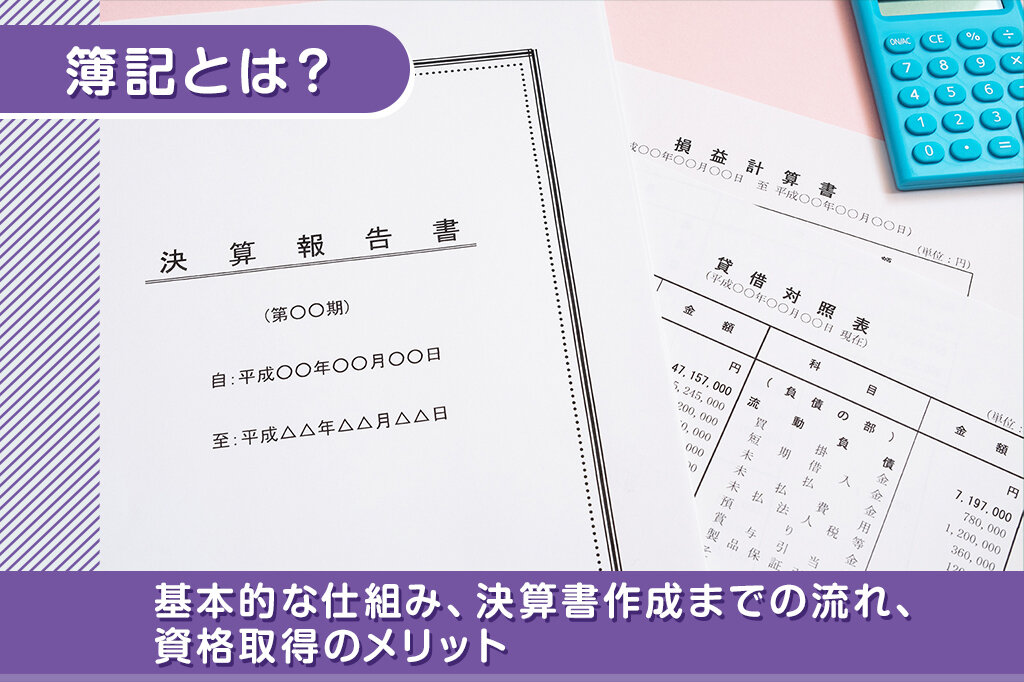



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

