
【麗澤大学監修】 近年はビジネスだけでなく、社会全体で「イノベーション」が求められています。それは社会のデジタル化、産業構造の変化、温暖化による環境の変化などが起こり、これまでの仕組みが通用しなくなっていることが理由に挙げられます。 そこで、イノベーションとは何か、専門家が提唱する理論や注目される背景、日本の事例や必要な学びについて、麗澤大学経済学部の大野正英先生に解説してもらいました。
イノベーションって何?
2007年に閣議決定された長期戦略指針「イノベーション25」によると、「イノベーションとは、技術の革新にとどまらず、これまでとはまったく違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすことである」とされています。
参考「第3 『イノベーション政策』について」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000440165.pdf
ヨーゼフ・シュンペーターが提唱したイノベーション
イノベーションの概念を生み出したとされる経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、著書『経済発展の理論』の中で新結合という言葉を用いてイノベーションの概念を提示し、世の中に大きな影響を与えました。
ヨーゼフ・シュンペーターは「新結合」を5つのタイプに分類しており、このような新結合、すなわちイノベーションが資本主義発展の原動力になると論じています。
1.新しい財貨の生産
2.新しい生産方法の導入
3.新しい販路の開拓
4.原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得
5.新しい組織の実現
大野先生は、新結合の意味を「多くの人がイメージする無から有を創り出す革新というより、すでに世の中に存在しているものを新しい形で組み合わせることによって、まったく新しい価値を創り出すこと」と補足しました。また、イノベーションの実現について次のように説明します。
「イノベーションの実現には『新たな価値を生み出したいと考える企業家精神を持った企業家(アントレプレナー)』と『資金提供などで応援したい支援者(投資家)』の組み合わせが重要です。新しい価値が生まれ、世の中に適応して受け入れられるには、時間と資金を必要とするため、イノベーターには投資家ら支援者が必要不可欠になります」
参考「シュンペーターの経済発展の理論」(新潟産業大学附属研究所)
https://nsu.repo.nii.ac.jp/records/93
参考「第2節 イノベーションの進展と日本の競争力」(内閣府)
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je18/h03-02.html
イノベーションが注目される背景
近年、さまざまな分野でイノベーションが注目されるようになっています。その背景として、3つの要因があるといわれています。
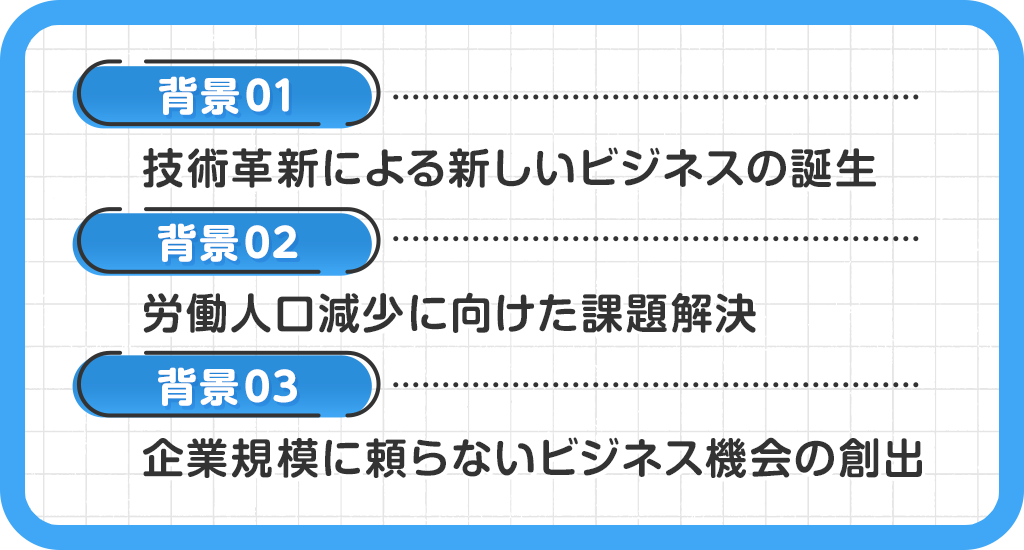
技術革新による新しいビジネスの誕生
IoTやAI(人工知能)など、近年は技術革新が急速に進んでいます。例えば、AIを取り入れた製品やサービスが開発され、新しいビジネスが生まれています。カスタマーサービスやオンライン学習サービス、マーケティング調査などさまざまな分野で、AIを活用した新たな市場が開拓されています。
労働人口減少に向けた課題解決
少子高齢化による労働者不足は、人材不足という問題も引き起こしています。日本では、2030年に高齢化(65歳以上の比率)が人口の33%以上を占めるようになるといわれ、大きな課題になっています。その解決策の1つとしてテクノロジーが注目されており、人材不足、労働力不足の改善のためにイノベーションが求められています。
参考「2030年、高齢化率33%社会 における労働と社会保障」(内閣府)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/281020/shiryou2_1.pdf
企業規模に頼らないビジネス機会の創出
現代社会ではテクノロジーの進化に伴い、新たなビジネスを創出して成功することが可能な時代になっています。さまざまな分野のスタートアップ企業が資金調達を行い、これまでにない新たな製品やサービスを開発し、新たな市場を切り開いています。経済産業省もスタートアップを支援しています。
参考「新規事業・スタートアップ」(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html
現代の課題を解決するための3つのイノベーション
イノベーションを語る上で、重視すべき方向性として3つのテーマがあります。ここでは、次の3つのテーマについて説明します。
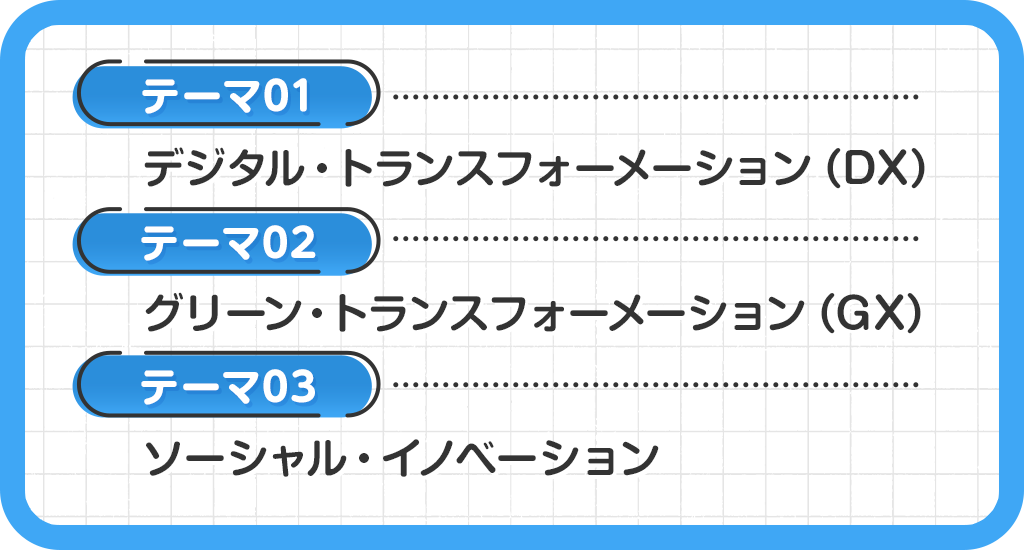
デジタル・トランスフォーメーション(DX)
3つのテーマでもっとも活況なのが、デジタル技術によるイノベーションです。行政手続きのオンライン化や企業における社内業務のデジタル化は、もちろん日常生活にも広がっています。身近なところではデジタル決済もデジタル・イノベーションの一部です。
数年前まで、買い物の支払方法は現金とクレジットカードの2択でした。しかし、PayPayなどのQRコード決済が急速に普及し、私たちの生活はより便利になっています。デジタル・イノベーションはビジネスにおいても、私生活においても多くの効率化をもたらしています。
グリーン・トランスフォーメーション(GX)
2つ目は、地球温暖化を解決するために取り組まれているイノベーションです。グリーン・トランスフォーメーションとは「化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のこと」をいいます。
地球温暖化については数十年後に起こり得るリスクという認識が持たれていましたが、近年世界中で頻発する異常気象などの気候変動を目の当たりにし、温暖化対策への取り組みが急務になりました。日本では、2023年4月から「GXリーグ」を立ち上げる準備が始まっています。
近年では、太陽光発電や風力発電など環境課題への取り組みがビジネスとしてもマーケットになるとわかり、さまざまな企業が参入しています。EV(電気自動車)化に取り組む自動車産業も1つの典型的な例です。今では環境課題に対する取り組みの遅れは、ビジネスにおける競争でも後手に回ることにつながります。
参考「知っておきたい経済の基礎知識~GXって何?」(経済産業省)
https://journal.meti.go.jp/p/25136/
参考「脱炭素時代の国際ルールを日本から-『GXリーグ』立ち上げのための議論を開始」(経済産業省)
https://journal.meti.go.jp/p/20259/
ソーシャル・イノベーション
3つ目は、社会課題の解決を行うためのイノベーションです。貧困対策や差別撲滅、福祉などが大きなテーマです。これまで社会課題を解決する活動は、主に政府やNPOが行っていました。ただ資金不足によって規模が小さく、実行速度が遅いという課題がありました。
そこで、企業が関わることによって資金や人的な資源、さらにビジネススキルを活用して社会課題の解決に大きく貢献することができます。これは社会課題解決とビジネスの両立が可能であるという考え方がベースになっています。ビジネスの発想を持ちながらも「どのようにして社会課題を解決するか」を実現することが求められるため、企業者の精神性が大事になります。
日本のイノベーション事例
日本でもイノベーションにより新たな価値を創造している企業があります。大野先生が2つの企業を事例として取り上げてくれました。
1.富士フイルム
「富士フイルム」は事業の中心であった写真フイルムの市場がデジタル化によって縮小するのに対応し、フイルムや光学技術を用いて新たな事業展開に成功しました。会社が持つ技術とノウハウを活用し、結果としてファインケミストリー(医薬品・化粧品などの化学製品に関連した化学)からエレクトロニクス(電子の働きを活用した通信・計測などに関連した電子工学)まで新しいビジネスの創出を行いました。
具体的には、フイルムで培った技術を応用して医薬品の分野や再生医療の分野に参入しています。今では写真・映像を扱ったイメージング事業をはじめとして、ヘルスケアやビジネスイノベーションなどを事業の中心として社会課題の解決に取り組んでいます。
参考「富士フイルムの歴史」(富士フイルム)
https://careers.fujifilm.com/graduates/about/history.html
2.認定NPO法人フローレンス
ソーシャル・ベンチャー(社会貢献や社会課題の解決とビジネス)として2004年に創業した「認定NPO法人 フローレンス」(以下、フローレンス)は、官民の保育体制の狭間に置かれた病児保育の分野で新しいビジネスモデルを展開しました。
現在、子育てと仕事の両立の壁になっている病児保育問題、待機児童問題、障害児保育問題といった社会課題に対し、ビジネスを通して多くの家族が抱えている問題の解決に取り組んでいます。
フローレンスが起こしたイノベーションの1つは、病気の子どもの世話をお願いしたいという家族のニーズと、子育て中でフルタイム勤務ができない保育経験者の就業ニーズをマッチングさせたことです。
2005年より自宅訪問型の病児保育を開始し、2010年には都心の空き物件を活用した0-2歳児を対象とした定員19人以下の保育園「おうち保育園」をスタートするなど、子育て世代が抱えるさまざまな課題と向き合い続けています。
参考「フローレンスとは」(認定NPO法人 フローレンス)
https://florence.or.jp/about/
麗澤大学が考えるイノベーションに必要な学び
イノベーションは、これからの社会において必要不可欠な考え方です。麗澤大学では、イノベーションを起こせる人材を育成するため、どのような教えを重視しているのでしょうか。経済学部では、4つの観点から取り組んでいます。
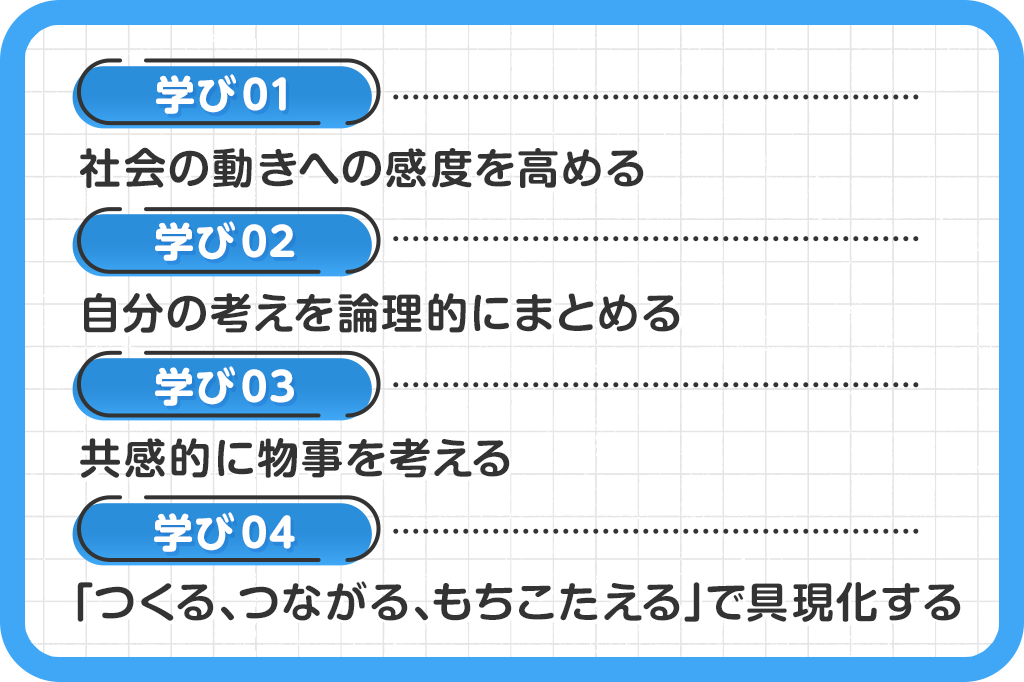
社会の動きへの感度を高める
まず大切なのは、社会の動きに対する感度を高めることです。「今、何が社会で求められているのか」を察知することが重要です。表面的な話題に惑わされることなく本質に目を向け、意味をしっかり理解しながら社会とのつながりを認識できるようになることが大事です。
自分の考えを論理的にまとめる
自身のアンテナで得た情報、調べた事実、そして自ら考えた意見を、他者に伝わるように論理的にまとめる力が必要です。「◯◯がこう言っていた」「◯◯にこう書いてあった」という伝聞では、説得力がありません。
情報感度を高めることはもちろん、他者の意見を受けて「どう考えたか」「現実と照らし合わせてどうなのか」など、自分なりの答えにたどり着くために考える力が必要です。大学生活ではさまざまな角度から物事を見つめ、考える力を身につけてほしいと思っています。
共感的に物事を考える
共感性も、これからのイノベーションに必要なテーマです。例えば、高齢者向けのサービスを考える際に「高齢者がどのような視点で物事を見ているか」を感じ取れるようになれば、それに合ったサービスを創出できます。
「つくる、つながる、もちこたえる」で具現化する
イノベーションには創造性が何より必要ですが、同時にまわりの人を上手に巻き込む力が求められます。なぜなら1人で実行できる領域は限られるからです。自分の考えを形に起こしてその思いを伝え、相手の考えを理解しながら多くの仲間とつながる力は不可欠です。
そして、うまくいかないことがあっても、めげずに前進する粘り強さが必要です。社会に対して新しい価値をもたらすには、物事がうまく進まなくて当たり前です。失敗しても投げ出さず、物事に取り組む粘り強さが問われます。アイデアを形にするには「つくる、つながる、もちこたえる」の3点が重要です。
経済学部が目指すイノベーション精神を持った人材像
イノベーション精神を持つ人材とは、社会にある課題を見極める力を持ち、自分なりの方向性を示した上で具体的なアクションを起こせる人です。アクションを起こす際には、自分だけでなく多くの人と行動をともにできる社会性も必要です。
麗澤大学には「経済・経営+道徳=道経一体」という考えがあり、私たちは「社会で何が必要とされているのか」を主体的に考え、「自分なりの答えをしっかり出せる」ことを大学で教え、社会に役立つ人材を育成していきたいと日々尽力しています。
これからは文理融合の視点がより重要になる

経済学部では、自分で考える際にデータに基づいて考察することを重視しています。データから導き出したアイデアを論理的にまとめ、相手に説得力を持って伝える力は、文系や理系に関係なく必要不可欠なスキルです。そのため、麗澤大学は全学部共通の柱としてデータサイエンス教育に力を入れ、経済学部も裏づけに基づいた考え方を重視しています。
麗澤大学サイト「経済学部」
https://www.reitaku-u.ac.jp/faculty/economics/
あわせて読みたい記事
「経済学とは?経済学について簡単に分かりやすく!学ぶメリットや就職先についても解説」(Reitaku Journal)
https://www.reitaku-u.ac.jp/journal/1776270/
【麗澤大学 経済学部・大野正英先生】

職名:教授
学部/学科:経済学部経済学科
専門分野:経済倫理
研究テーマ:経済学における利他性、コミュニティの役割
■学歴
1986年 東京大学経済学部経済学科/卒業
1988年 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程/修了
1994年 早稲田大学大学院経済学研究科博士課程/単位取得満期退学
■経歴
1988年 (財)モラロジー研究所/道徳科学研究センター研究員
1996年 麗澤大学経済学部/非常勤講師
2008年 麗澤大学経済学部/准教授
2013年 (財)モラロジー研究所/道徳科学研究センター長
2016年 麗澤大学経済学部/教授
プロフィール参考
https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/economic/467/























 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

