
海外の大学とオンラインでつながり、双方の学生が共同でプロジェクトに取り組む。そのような国際協働学習を「COIL(Collaborative Online International Learning:コイル)」(以下COIL)といい、麗澤大学は2019年から実施しています。 2020年秋に行われたCOILプロジェクトの実際の取り組みの様子を、COILを実践する山下先生、そして授業に参加したルバさん、スーセンさんに伺いました。

インド在住のインド人の先生からオンラインレッスンを受けている。

※取材時、3年次生

麗澤大学校舎「あすなろ」2階にあるInternational Floor「iFloor」にSS(Student Support)として勤務。
新しい学びの形、オンラインでの国際交流学習を体現する授業:COIL
2020年10月7日、山下先生の「Intercultural Communication」の授業。麗澤大学の学生8名とポートランド州立大学(以下PSU(Portland State University))のクリスティーヌ・クレス(Christine Cress)教授の担当するアメリカ人大学院生4名、双方の教員2名がテレビ会議システムZoomでつながり、日米共同プロジェクトのキックオフミーティングを行いました。
また台湾出身のスーセンさんは、台湾茶と世代を超えた家族とのつながりを紹介。PSUのエリンさん(アメリカ出身)は、テントウムシのマスコットを見せながら、それにまつわる家族の思い出を話しました。他にも「月餅」や「ズニ族のブレスレット」など、様々な文化的なオブジェクトと共に素敵なエピソードが語られ、オンラインとは思えないほど交流は和やかに進みました。
多種多様なエピソードのおかげで、お互いの距離がグッと縮まったところで、初回ミーティングが終了しました。
「自分の当たり前が他人の当たり前ではないことに気がつく」
そんな学びがCOILにはある
麗澤大学とPSUのコラボレーションは、今回が2回目です。1回目は、経済学部の1年次生とPSUの大学院生が「観光客を災害から守る」をテーマに共同プロジェクトに取り組みました。2回目となる今回のプロジェクトテーマは「ユニバーサルデザイン」。
-
多様化が進む中、国・文化、年齢や障がいの有無に関わりなく、あらゆる人に役立つデザインを、多様な文化背景を持つメンバーで考えようというものです。「ユニバーサルなものは、独りよがりな考えでは生み出すことができません。相手の立場に立ち、相手が何に困っていて、何を求めているかを理解する"エンパシー(empathy:共感)"を働かせる必要があります。そして、エンパシーは異文化コミュニケーションにおいても重要なスキルです。文化背景の異なるメンバーでチームを組み、ユニバーサルデザインを考えることで、エンパシースキルを高め、新しい視点を見出すこと。それが、今回のプロジェクトの狙いです」(山下先生)

リアルタイムの日米共同オンラインミーティングは全3回。それ以外は、Slackというツールやメールなどを活用し、プロジェクトを進めます。メンバーは、アメリカ人大学院生のリーダーのもと、4つのチームに分かれて活動。スーセンさんのチームは「公衆トイレ」のデザイン(マーク)に取り組みました。

-
「私は日本の公衆トイレをリサーチするため、柏市内の公園に行きました。実際に見てみると、点字ブロックがトイレの手前3mくらいのところで途切れてしまっていたり、トイレの個室にある様々なボタンの使い方の説明が、日本語表記しかなかったり。視覚障がい者や日本語がわからない外国人にとって、非常に使いにくいことがわかりました。私は、課題と感じる箇所を写真に撮ってチームと共有し、みんなでどうすべきか、特にデザインについて考えていきました」(スーセンさん)
-
「私のチームは"トランスレーション(翻訳)"に取り組みました。たとえば日本では、音声案内や案内表示の言語が英語・中国語・韓国語などに限られ、私の出身国パキスタンのウルドゥ語や、隣国インドのヒンドゥー語などには対応していません。これらの国は貧富の差が大きく、英語の教育を受けていない人がたくさんいます。そこで私たちは、日本語も英語もわからない人たちに対応するためのアイデアを考えました」(ルバさん)


-
「ユニバーサルデザインに取り組む過程で、事前に山下先生の授業でこんなことを学んでいました。シンパシー(sympathy:同情)は自分のレンズから見る世界、エンパシー(empathy:感情移入)は相手のレンズで見る世界。相手のレンズで物事を見ることができれば、相手が何を必要としているかがわかると。その時は何となくしか理解していなかったと思います。しかし、今回、障がい者や外国人の立場で公衆トイレを観察してみると、彼らに全くフレンドリーではないと気がつき、これがシンパシーではなく、エンパシーなんだ! と実感し、本当の意味で理解することができました」(スーセンさん)
各チームはリサーチ、デザインの考案、プレゼンテーションの準備を着々と進め、11月末、3回目の日米共同のオンラインミーティングで成果を発表し、プロジェクトは終了しました。
実際にアメリカに行けなくても、アメリカの大学院生と学べたことは一生の思い出
「私のチームはアメリカ、パキスタン、日本の混合チームでした。それぞれに文化が違うので、色々な意見が出ましたが、お互いに理解しようと努力し、一緒にプロジェクトを成し遂げることができました。私は、アメリカ人とのプロジェクトは今回が初めて。英語ネイティブでもないので、最初は緊張しましたが、回を重ねるうちに慣れて、最後は緊張せずに話せるようになりました。実際にアメリカに行くことはできませんでしたが、アメリカの大学院生と一緒に学べたことは貴重な経験であり、一生の思い出です」(ルバさん)












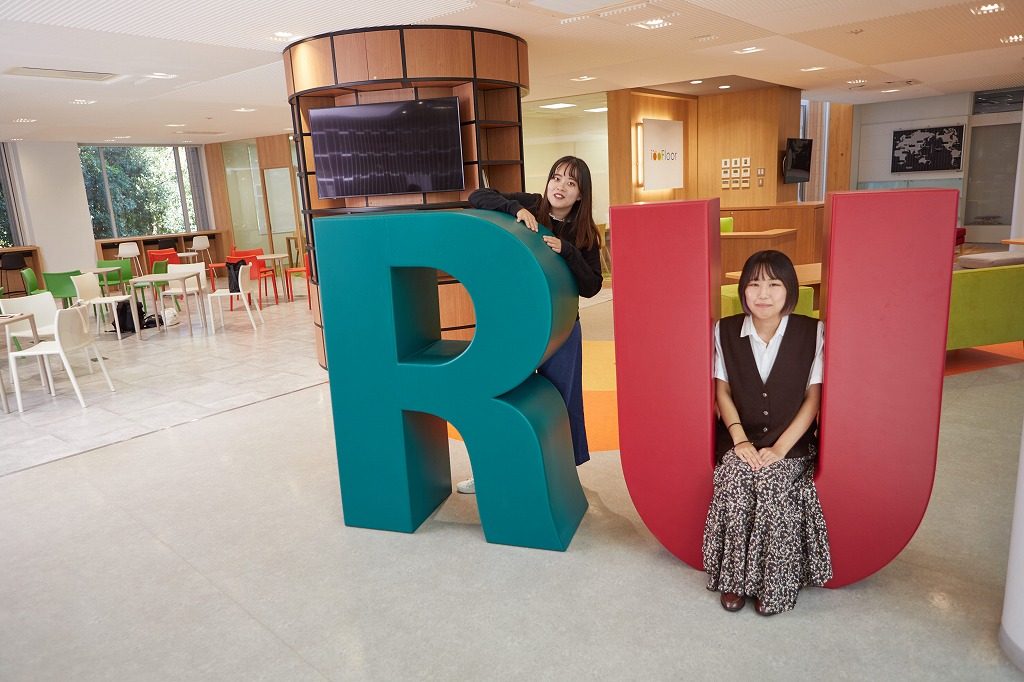

















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

