
10歳のときにルーマニア革命を経験し、後に難民として生き延びた恩師と出会ったことで、「人間の安全保障」という問いに強い関心を抱くようになったヨネスク先生。授業では、少数民族や自然との共生を切り口に、学生一人ひとりが社会や自分自身の価値観を見つめ直していきます。前編では、ヨネスク先生がなぜ「人間の安全保障」という考え方に至ったのか、その背景となったご自身の生い立ちや、授業で大切にしている価値観について掘り下げていきます。

10歳のときに直面した「社会の崩壊」
私の原点は、幼少期に体験した社会の崩壊にあります。ルーマニアの首都ブカレストで生まれ育ち、共産主義体制のもとで生活していました。そして、10歳のときにルーマニア革命が起こり、それまでの制度や価値観が一夜にして覆る瞬間に立ち会いました。それはテレビの向こう側の出来事ではなく、私の目の前で「日常」が「非日常」に変わる衝撃的な体験でした。

-
昨日まで"善"とされていたことが突然"悪"とされ、敵は国家の外にいると教えられていたのに、ある日を境に敵はご近所の誰かに変わっていました。私はまだ幼く、その状況をうまく言葉にできないまま「なぜ同じ国民同士が争うのか」という疑問を抱えていました。この体験が、私の価値観の礎を築いたといっても過言ではありません。社会とは何か。国家とは何か。そして「人間の命や尊厳は、なぜこれほどまでに脆く、簡単に踏みにじられてしまうのか」──そういった問いが、私の中に静かに芽生えました。それは一時の好奇心ではなく、人生をかけて探求していくべき「根源的な問い」でした。
その後、国が開かれ海外の文化や情報に触れられるようになると、外の世界への憧れとともに、社会の仕組みや権力構造に対する批判的な視点も芽生えてきました。目の前で起きたことをどのように理解すればいいのか考え続ける中で、「人間とは何か」「社会はどうあるべきか」への関心が深まっていきました。
日本語との出会い、そして人生を変えた恩師
日本語と出会ったのは高校生の頃でした。東アジアの文化や歴史に興味があり、日本を描いた映画をきっかけに、日本という国そのものに惹かれました。日本語の発音はルーマニア語に近く、耳に馴染んだこともあり、自然と受け入れることができました。高校卒業後、ブカレスト大学の日本語学科に進学したものの、在学中から「日本語だけでは将来の道が見えない」という現実に直面しました。当時のルーマニアには日本との経済的・人的交流がまだ少なく、せっかく言語を学んでも職業につながらない。しかし、言葉を学ぶだけでなく、その文化と社会の中に身を置きたいという強い思いから日本への留学を決意しました。
-
留学先での恩師との出会いが、人生の転機となりました。彼はカンボジア出身で、ポル・ポト政権の迫害から逃れて難民としてカナダに渡った方でした。難民キャンプでの生活を経て、独学で英語を学び、大学院博士課程にまで進んだ方です。彼は、カンボジアの復興を目指して、法律、政治、経済、教育といった幅広い視点から「人間の安全保障」という概念にもとづいた研究を進めていました。この出会いこそが、私が「人間の安全保障」という学問分野を初めて意識した瞬間でした。

彼の問いかけは、「人間の尊厳とは何か」「国家の安定の陰で見過ごされている声なき声をどうすくい上げるか」といったもので、私自身が抱えてきた問いとも重なりました。この出会いをきっかけに、大学院では制度設計や法制度、経済理論といった知識に加えて、「生きるとは何か」「守るべきものは何か」といった哲学的な問いにも取り組むようになりました。
少数民族の視点から、世界の「当たり前」を問い直す
私の授業では、ロマ族やアイヌ民族などの少数民族の視点から教育や国家観を問い直すことを行っています。少数民族に焦点をあてるのは、社会がどのような視点で語られてきたか、そしてその語りからこぼれ落ちてきたものは何かを考えるためです。多くの社会制度や教育、国家観は、主流派の視点から語られてきました。そこには「普通とは何か」「正しさとは何か」といった価値の偏りが潜んでいます。

-
私は自身の研究の中で、ロマ族に長年関わってきました。ロマ族の人々は、何世紀にもわたって差別や排除を受けながらも、自らの言語や文化、価値観を守り抜いてきた人々です。彼らの歴史を学ぶことは、単に"かわいそうな人々"の物語を知ることではありません。それはむしろ、私たちが無意識に信じている「文明」や「発展」「教育」「国家」「秩序」といった概念が、どれほど一面的で、時に暴力的なものとして作用してきたかを見直す作業なのです。
私たちの多くは、主流の教育、メディア、制度などの中で生きています。そこでは「普通」とされる価値観が当然のように繰り返され、それ以外のものは"異質"として排除されがちです。けれども、ロマ族のようにその"外側"に置かれてきた人々の視点から世界を見つめ直すと、これまで見えていなかった構造や価値の前提に気づくことができます。こうした構造的な"見えなさ"に対して、私はあえて学生たちに問いを投げかけます。「あなたの価値観は、誰の視点から育まれてきたのか?」「見ようとしなかった、あるいは見せられてこなかったものは何か?」と。授業では、ロマ族の事例を通して"問いの立て方"を学び、後半では学生がグループを組み、調査・討議を重ねて、最終的にプレゼンテーションを行っています。
2026年度から始まる「総合安全保障教育プログラム」に含まれる「人間の安全保障」の授業でも、多様な視点に触れながら、自らの思考を深めることを重視していきます。
【総合安全保障教育プログラムとは?】
全学教育基盤「麗澤スタンダード」の新科目であり、私たちの暮らしや社会を脅かす様々な課題―戦争、災害、気候変動、サイバー攻撃など―について学ぶ新しい学びの場です。文系・理系の枠を越えて、多角的に問題をとらえ、より安全で持続可能な未来を考え、行動できる力を養います。
―後半では、ヨネスク先生が担当する「人間の安全保障」の授業の中身や、それを麗澤大学で学ぶ意味についてお届けします。








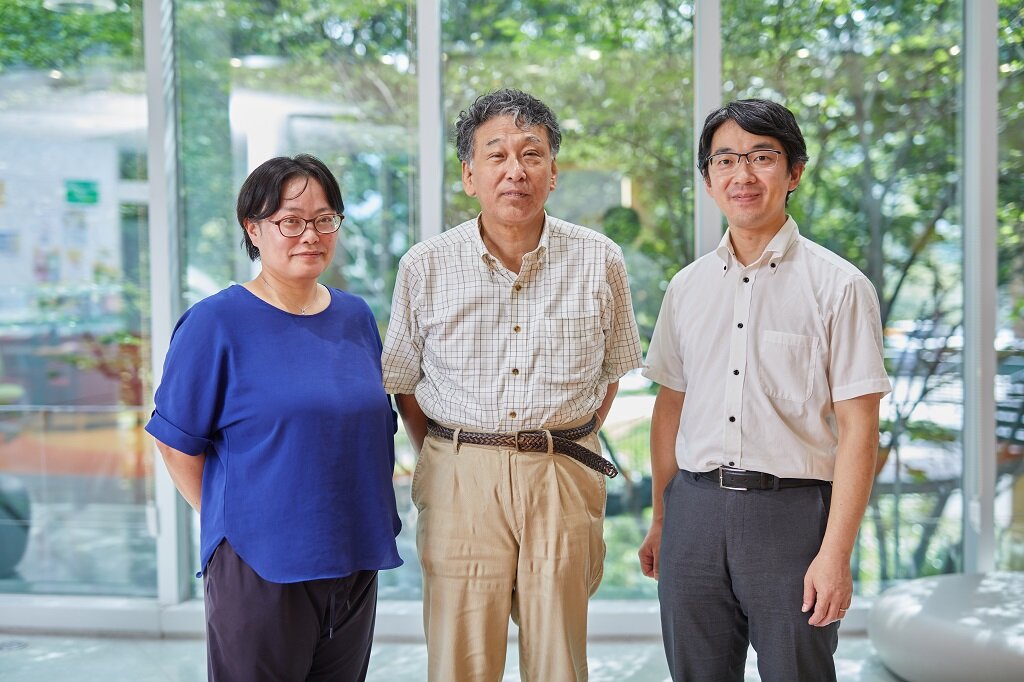


















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

