
麗澤大学の自主活動サークル「すまいる」は、2023年に学生が主体となって立ち上げました。外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語学習支援を目的に、松戸市立相模台小学校をはじめ、様々な場所で子どもたちに日本文化や日本語に触れる機会を提供しています。前編では、サークル発足の経緯、具体的な活動内容とメンバーの学び、やりがいなどについて、メンバーの学生から詳しくお話を伺います。




外国人児童に笑顔を届ける日本語支援サークル
―「すまいる」の具体的な活動内容や目指していることについて教えてください。
-
三浦さん:「すまいる」は、日本語支援が必要な子どもたちや、外国にルーツを持つ子どもたちに対して日本語学習の支援を行う自主活動サークルです。子どもたちが楽しく日本語を学びながら、日本文化に親しむ機会を通じて成長できるよう、現在9名で様々な活動を行っています。主な活動としては、松戸市立相模台小学校の「にほんごルーム」で月に1回ボランティアをしています。
家族の事情で日本に来た子どもたちが多いからこそ、まずは日本に親しみを持ってもらうことが大切です。七夕や餅つきなどの行事を一緒に楽しむイベントを企画し、実際の体験を通して日本語を学べるよう支援しています。 
その他にも、外国人児童が安心して日本語を学べる環境を提供する「1人100時間プロジェクト」への参加や、柏市国際交流協会が開催したスピーチコンテストでの活動紹介など、地域やオンラインでの交流を通じて活動を展開しています。
―今のお話に出てきた「1人100時間プロジェクト」とは、どのような活動なのでしょうか。

-
三浦さん:「1人100時間プロジェクト」は、「一般社団法人 外国人の子供たちの就学を支援する会」が主催する活動であり、外国にルーツを持つ子どもたちが日本語を習得し、学校生活に適応できるよう、1人の子どもに対して100時間の日本語支援を行うというものです。私たち「すまいる」は2024年8月からこのプロジェクトに参加しています。週3回程度、メンバーが交代で子どもたちをサポートしており、講師1名と子ども3名の少人数制で、ひらがなの読み書きや日常会話を学ぶオンライン授業を行っています。子どもたちが自信を持って日本語を使えるようになるまで、長期的に寄り添っていける点をやりがいに感じています。ただ教科書通りに進めるだけでは興味を持ってもらえないので、授業中にはできるだけ体を使った遊びやゲーム、歌などを取り入れるようにしています。
由さん:このプロジェクトに参加するきっかけとなったのは、「外国人の子供たちの就学を支援する会」の代表理事の方が麗澤大学で講義をしてくださったことでした。外国にルーツを持つ子どもたちは日本語が話せず学校生活に苦労することが多く、学習の遅れも生じやすいと聞き、「私たちもこのプロジェクトに参加したい」と思いました。金先生に相談したところ、先方に掛け合ってくださり、私たちの参加が認められたのです。私たちの活動はまだスタートしたばかりですが、子どもたちが少しずつ自信を持って日本語を使えるようになる姿を見て、この活動が子どもたちにとって非常に大きな意味を持つと実感しています。
異文化への関心から生まれた、日本語教育への熱意
―「すまいる」を立ち上げるに至った経緯や、当時の想いを教えてください。
-
堀越さん:「すまいる」は2023年に5名の学生でスタートしました。きっかけは、先ほどお話があった、相模台小学校での日本語支援の依頼を受けたことでした。私は大学院で日本語教育を専攻していたので、最初は自身の研究に役立てたいという想いで参加しました。しかし活動を進める中で、支援が必要な子どもたちが多い現状を知り、ほかの学生たちと協力して団体として活動していくことを決めました。「すまいる」という名前には、私たちが笑顔で楽しく活動することはもちろん、子どもたちにも笑顔を届けたいという想いを込めています。

―由さんと三浦さんが「すまいる」に参加することを決めたきっかけを教えてください。
由さん:私は留学生として日本に来たのですが、日本語の文法を学ぶだけでなく、文化を深く理解することが日本語力の向上に不可欠だと感じていました。そんな時、小学校での日本語支援の話を聞き、私も力になりたいと思って「すまいる」に参加しました。
三浦さん:私は高校時代に外国人のクラスメイトと接する中で、異なる文化や考え方に触れることのおもしろさを実感しました。多様な文化や価値観をもっと理解したいという想いから、日本語教育について学ぶため麗澤大学に入学したので、「すまいる」の活動を知ってぜひ参加したいと思いました。異文化交流や日本語教育を通じて、子どもたちの学びをサポートできることにやりがいを感じています。
子どもたちとのふれあいから広がる、学びと喜び
―活動を通して得た学びや成長、やりがいを教えてください。

-
由さん:オンライン授業中、まだ慣れていない子が泣いてしまったことがありました。私も突然のことで戸惑ってしまったのですが、飽きないように工夫しながら進めていくうち、次第に笑顔になっていき、とても安心しました。子どもの感情は変わりやすいということを学んだと同時に、笑顔で楽しんでくれている様子を見られることに大きなやりがいを感じました。こうして何か困ったことや上手くいかないことがあった時、また嬉しいことがあった時などには、ほかのメンバーにグループチャットで相談しています。「こんな風に進めるといいよ」とアドバイスをもらえたり、子どもたちの成長を一緒に喜んでくれたりするので、日本語支援をしていく上での支えになっています。
堀越さん:この活動を通して、本当に多くの学びや気づきを得ました。まず、子どもたちの素直な反応に触れながら、それにどう応じるかを考えて活動を進めてきました。たとえば、子どもたちは楽しいとすぐに笑顔を見せてくれるし、つまらない気持ちも顔に出るので、その反応を見ながら次にどう改善するかを考えるようになりました。こうした子どもたちとのやり取りが、私にとって大きな学びとなっています。
また、「すまいる」は自分自身の成長を実感できる場にもなっています。異文化理解や日本語教育の知識を深めるだけでなく、ほかのメンバーと協力しながら役割を分担し、主体的に学びを進めることができる環境にいることに感謝しています。単に知識を得るだけではなく、実際にその知識を現場でどう活かすかを学べるのは、とても貴重な経験です。







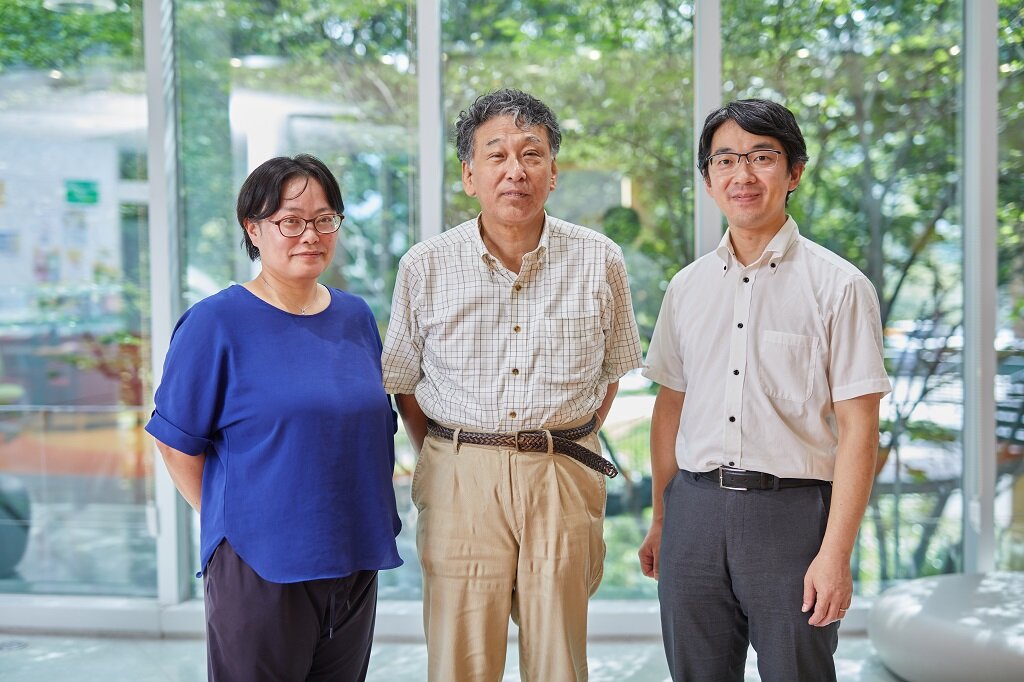



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

