
10歳のときにルーマニア革命を経験し、後に難民として生き延びた恩師と出会ったことで、「人間の安全保障」という問いに強い関心を抱くようになったヨネスク先生。授業では、少数民族や自然との共生を切り口に、学生一人ひとりが社会や自分自身の価値観を見つめ直していきます。後編では、ヨネスク先生が担当する「人間の安全保障」の授業の中身や、それを麗澤大学で学ぶ意味についてお届けします。

「人間の安全保障」は人間だけのためでは不十分

-
「人間の安全保障」とは、国家の安全が確保されていれば人々も守られるという前提を問い直し、一人ひとりの命や尊厳を起点に社会をとらえる考え方です。国家が機能していても、貧困や差別、暴力、環境破壊などで苦しむ人がいる限り、それは「安全」とは言えません。
私がこの概念に注目するのは、国家や制度といった枠組みではとらえきれない現実を、個人の立場から見つめ直す必要があると感じているからです。特に現在では、人間中心の視点だけでは不十分であり、自然や動物、環境など人間以外の存在との関係にも目を向ける必要があると考えています。
人が安心して生きるためには、周囲の生命環境も共に守られていなければなりません。こうした視点は「More-than-Human Security(人間以上の安全保障)」とも呼ばれ、私はこの考え方を授業に取り入れています。
社会の中で、自分の軸を見つける
私の授業は、答えを教えるものではありません。むしろ、学生一人ひとりが「自分の中にある問い」に気づき、それを掘り下げていくことを出発点としています。問いとは誰かが与えるものではなく、日々の違和感やふとした感情、あるいは「なぜだろう」という素朴な気づきの中に、すでに芽生えています。私はまず、その芽を大切にしたいのです。
-
自分の感情、価値観、関心はどこから来ているのか。それは本当に「自分のもの」なのか。親や先生、社会の中で刷り込まれた考え方ではないか──そうした問いを重ねながら、学生たちは少しずつ自分という存在の輪郭を描き始めます。そうして輪郭が浮かび上がると、視野は自然と外に開かれ、社会や世界とのつながりに目が向いていきます。
私が大切にしているのは、「世界の問題」と「自分の問い」を結びつけることです。人権、貧困、環境破壊、差別といったテーマを、どこか遠い出来事としてではなく、「私の暮らしとどう関係しているのか?」という視点で見つめていく。その過程で、学生たちは自分が無意識に信じていた"当たり前"が、実は偏りのあるものだったと気づきます。

そうしたタイミングで、私はあえて「More-than-Human Security(人間以上の安全保障)」という視点を提示します。国家に頼る安全保障から、互いに支え合う「人間の安全保障」へ、そしてさらに「人間以外の存在」との共生へと視点を広げていく。この時、学生たちの内なる世界観がそっと揺らぎ始めます。しかし、崩すことが目的ではありません。壊れた先に、自分の手で組み直していく経験こそが、学びの核です。変化する社会の中で自分の軸を持ち、他者や自然ともつながっていく。その力は、どんな分野に進んでも、どんな人生の場面においても、きっと自分を支えてくれるはずです。
麗澤大学だからこそできる学び
私が大切にしているのは、学生が自分自身の内側にある問いに気づき、それを出発点として外の世界とつながっていくような学びです。内省と思考、感情と論理を往復させながら、「私は何者か」「何に共鳴し、何に違和感を覚えるのか」「この社会をどうとらえるのか」といった問いを、学生自身の手で耕していく。そのプロセスこそが、私の授業の核になっています。しかし、こうした学びは大講義形式ではなかなか成立しません。自分の内面に向き合うことも、他者と丁寧に意見を交わすことも、安心と信頼に支えられた環境があってこそ可能になるからです。

-
だからこそ、私は少人数制で授業を行う麗澤大学という場に、特別な意味を感じています。学生一人ひとりの言葉や沈黙にじっくりと耳を傾けることができ、教員と学生の距離も近く、互いに信頼関係を築きながら、学びのコミュニティとしてともに時間を過ごすことができる。この密度の高い時間こそが、学生の変容を後押ししてくれるのです。私の授業では、学生同士が意見を交わすグループワークや、少数民族についての発表などを多く取り入れています。お互いに自分の価値観をぶつけ合い、ときには考えを揺さぶられながら、考えを深めていく。そのような知的で感情的な「対話の場」は、やはり少人数だからこそ成立するものだと、日々実感しています。
麗澤大学には、そうした「学びの土壌」がしっかりと整っています。小規模であることは単なる特徴ではなく、一人ひとりの変化を見届け、寄り添い、支えられる教育の在り方を可能にする"強み"だと私は思います。だからこそ私はこの大学で、学生たちと共に、"問いから始まる学び"を丁寧に育てていきたいと願っています。








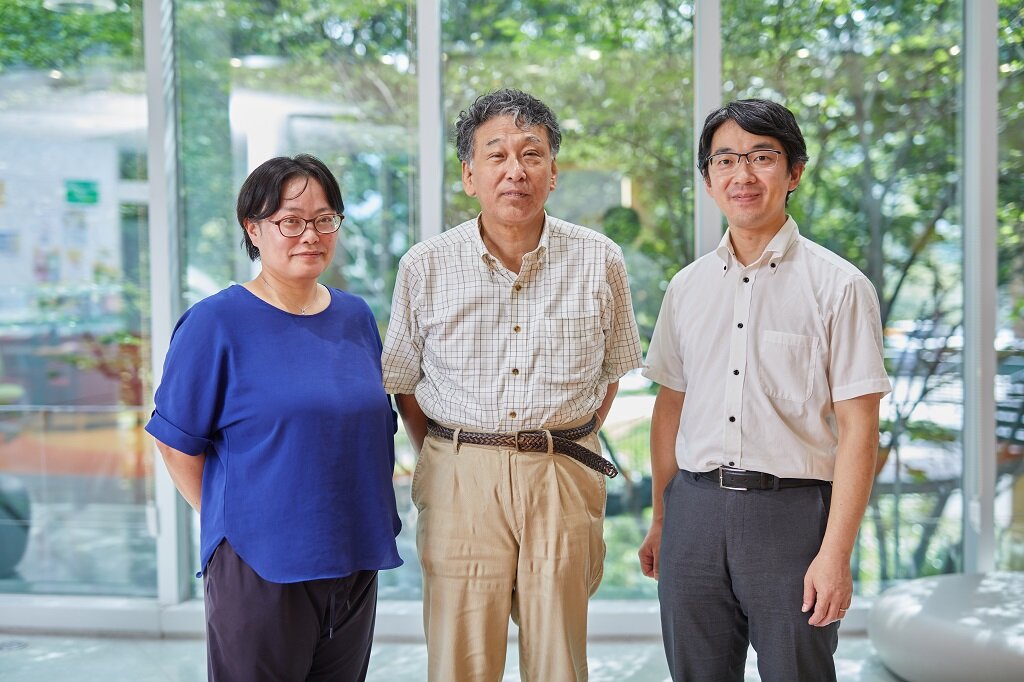


















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

