
ホスピタリティ業界を目指す学生を対象とした授業「ホスピタリティ科目」では、実践の場として、パーク ハイアット 東京のインターンシップ・プログラムを実施。多くの応募者から選抜された長谷川さん、牛嶋さん、市橋さんの3名が参加し、フロントサービスやハウスキーピング、スパ&フィットネス部門など様々な業務を体験しました。体験談の後編は、将来に向けたお話と、ホスピタリティ科目のコーディネーターを務める佐藤先生にもお話を伺います。

華やかさの裏にあるプロ意識――漠然とした興味や憧れが具体的な目標に
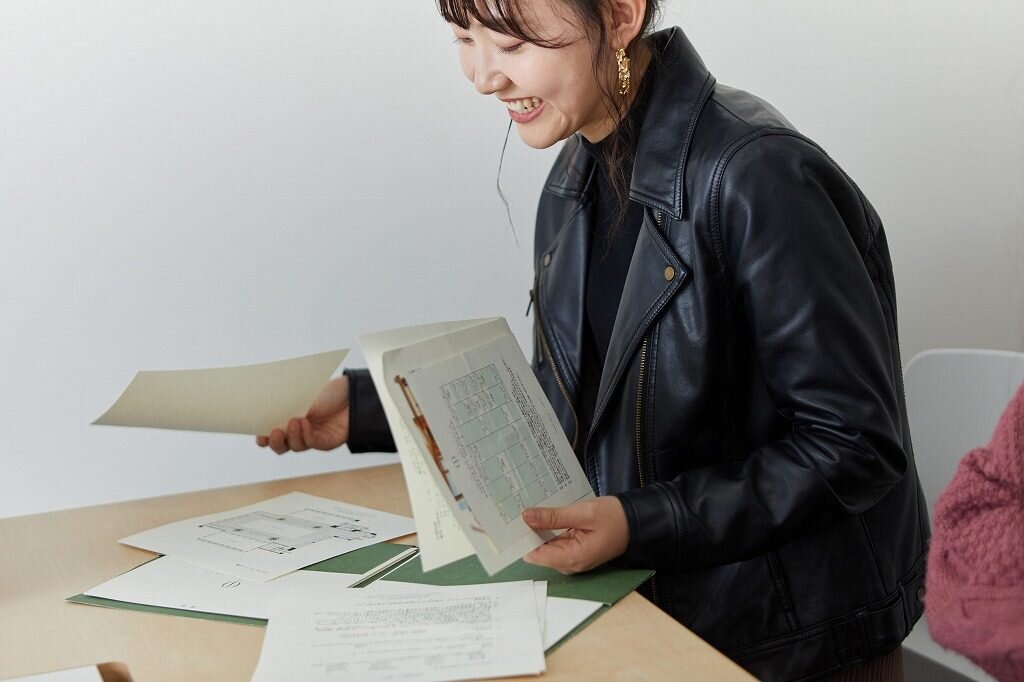
――多くのことを学んだインターンシップ・プログラム。終えての感想はいかがですか?
長谷川:これまでホスピタリティ業界に漠然とした興味はあっても、具体的に絞り込めていなかったのですが、今回の体験を通して、ホテル業界、それも世界中からお客様が集まる、都内の外資系ホテルへの興味関心がぐんと高まりました。私はもうすぐ就職活動も視野に入ってくるので、企業研究に活かしていきたいです。
牛嶋:ホテル業界への憧れが強かっただけに、行く前は「現実を知ったら、夢が壊れちゃうかもしれない」と心配しましたが、
憧れがいっそう強くなりました。これを機に、他にもいろいろなホテルのインターンシップに参加し、さらに視野や知見を広げたいと思うようになりました。
市橋:私も、ホテルスタッフの華やかな仕事の裏にある大変さやプロ意識を知ることで、これまで以上に興味が沸いてきました。そしてホテル業界でも何でも、より高いレベルを目指そうと思うようになりました。英語力をもっと高めて、スタッフの皆さんがお客様に積極的により良いサービスを提供していたように、私も何事に対してももっと積極的になろうと思いました。たとえば授業では、積極的に発言することを継続すれば英語力向上にもつながるし、アルバイト先など日常生活でも、自分から行動していくことでたくさんのものが得られると思います。
努力すれば後で必ず実を結ぶ。色んなことにチャレンジしていきましょう!

――将来の夢を教えてください
長谷川:大好きな英語と日本人であることを活かして、海外のお客様に、日本ならではのおもてなしができるようになりたいです。そして、どんなお客様に対しても、思いやりの心でお客様の気持ちに寄り添い、望まれていることを事前に察して叶えてさしあげられるようになることが目標。そのための学びの一環として、障がい者の方への対応方法を学ぶ検定「ユニバーサルマナー検定」にも挑戦し、3級を取得しました。さらに2級を取得し、1歩ずつ夢に近づいていきたいです。
市橋:私の夢はやっぱり、ホテルスタッフです。少し先輩である私から高校生の皆さんには「勉強は継続が大事!」というメッセージを伝えたいです。私の高校時代の勉強方法はテストのための一夜漬けで、テストが終わったら全部忘れてしまう。そんなことを繰り返していたため、受験勉強は最初からやり直すはめに...。毎日コツコツと継続して勉強していれば良かったのに、大変な思いをすることになりました。そうならないためにも、できるだけ早い段階から勉強する習慣がついていれば、受験勉強も苦にはならず、やりきったという自信もついて、また次の新たな目標にも向かえると思います。

牛嶋:私は日本が大好き。将来は海外にあるホテルではなく、あえて日本にあるホテルで、日本にいらした外国の方に、接客を通して日本の魅力を伝える仕事をしたいです。高校生の皆さんには、高校でも大学でも、後悔のないように色んなことに積極的に取り組んでほしいなと思います。新しいことにチャレンジするには、不安だったり勇気が必要だったりするけれど、努力をすれば、あとで必ず実を結びます。私も今回、インターンシップに参加して本当に良かったと思っています。次のチャレンジは留学です。いろんなことをたくさん経験して、パワーアップしていきましょう!
「気がつくだけ」から「気がついて行動する」へ変わること

――最後に、佐藤先生からお願いします
佐藤:3人とも、このインターンシップを通して期待を上回る学びを得てきてくれました。きちんと学生生活に活かせる学びに変換して考えてくれたことが嬉しいですね。ホテル業界に憧れる学生は多いものの、憧れだけで仕事に就くとギャップに苦しむこともあります。見えないところではどんなことをしているのか、どんな想いで働かれているのかを知ることができるので、ホスピタリティ科目の授業やインターンシップは、そこを知った上で自分の適性を見極める良い機会にもなります。
インターンシップには一部の希望者しか参加できません。審査は、応募書類に誤字脱字がひとつでもあればNGというように非常に厳しいですが、それだけに応募書類を書いたり面接を受けたりするだけでも良い経験になり、学びにつながると思います。ホスピタリティ科目の授業で学んでほしいのは、気づいて行動すること。「この人、困っているな」と気がつくことができる人は意外にも多いもの。でもその後「この人は何を求めているのだろう」と考え、実際に行動に移せる人は少ないのです。ホスピタリティ科目の授業では様々なシチュエーションを想定し、対応を学びます。
それを参考にしながら、学生生活の場でも実践してほしいですね。たとえば、本学には車いすや杖を使う障がい者の学生もいるので、必要な時には手を差し伸べてあげる。障がい者に限らず、困っている学生がいたら「何か手伝えることはある?」と声をかけるというように、日々の実践を通して授業の学びを自分のものにし、あらゆる場で通用するホスピタリティ精神を身につけていってほしいです。
【この記事を読んだ方にオススメの記事】
麗澤大学では、学生たちがキャンパスを飛び出し、社会や世界と直に触れ合う機会を豊富に用意しています。
パークハイアット東京でのインターンシップや、商業施設との連携企画など、相手の立場を尊重した丁寧な気遣いや、英語力を活かした外国人への対応、地域活性化の課題解決に取り組むなど、様々な企業と協力し、学生たちは実際に社会に出た際に役立つ実践力を培います。 全学部で展開しているPBL(課題発見解決型学習)が気になる方にオススメな記事をご紹介します。

-
<実社会から学ぶ PBL(課題発見解決型学習)>
【前編】企業と学生がコラボ!学生のアイデアが商業施設の可能性をひらく?!
【後編】企業と学生がコラボ!学生のアイデアが商業施設の可能性をひらく?!

-
<実社会から学ぶ PBL(課題発見解決型学習)>
麗澤大学生と一緒に商品を開発し販売したい
麗澤大学の先生と"NUIZA縫EMON"のスタッフに親交があったことをきっかけに、2016年5月から麗澤大学の経済学部に所属する学生達と"NUIZA縫EMON"のマーケティング、集客、商品開発などの戦略を一緒に練っています。経済学部として実際に学んでいる事を実店舗で活かしてもらっています。

-
<卒業生の活躍>
ホテルのサービスに正解はないだからこそ、感じて、考えて、行動する
麗澤大学には留学生も多く、日々異文化交流ができるような恵まれた環境ですよね。そのチャンスを活かし、限られた時間の中でできるだけ多くのものに触れ、感性を磨いてください。



























 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

