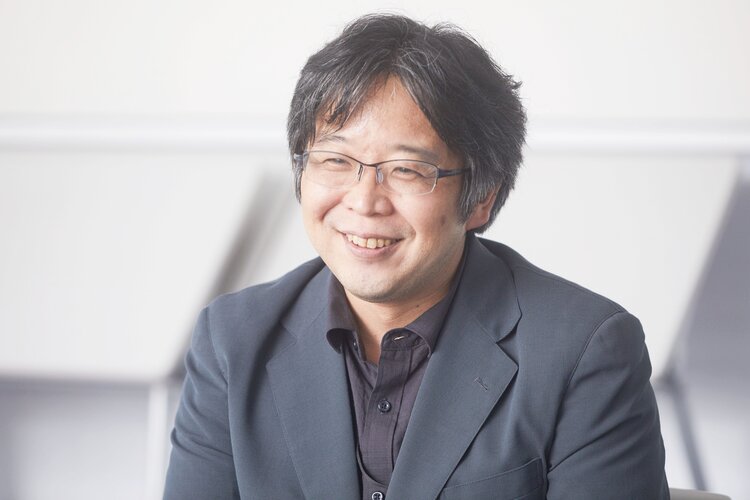
麗澤大学と関わりの深い田中俊弘先生へのインタビュー。後編では、コロナ禍における授業の取り組み、これからの時代、外国語学部の学生に必要な学びについてお話を伺います。
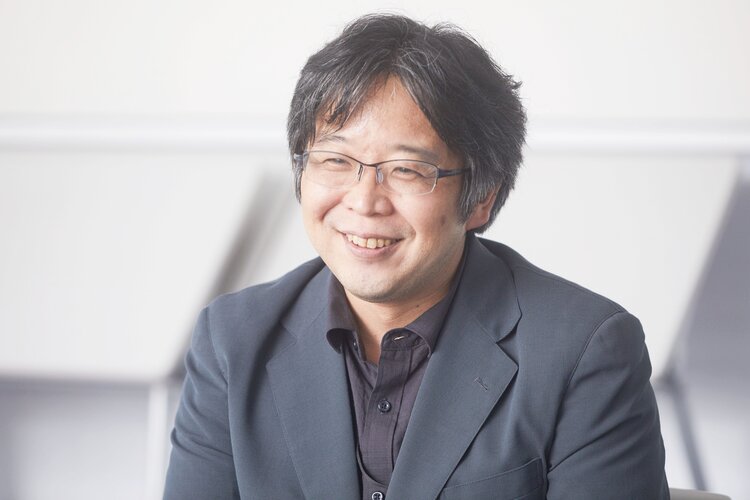
オンラインでも、対面授業に遜色ない授業は可能です
課題は、その次の回の講義内容につながるテーマで、30分以内にレポートを書いて提出するというもの。かなりハードですが、学生の食いつきは予想以上。学生は制限時間内に、自分の頭をフルに使って書き上げ、それに対し私は、一人ひとり隅々まで丁寧に添削し、コメントをつけて返しています。これを毎週実践していると、学生は回数を重ねるごとに、確実にレベルアップしています。オンライン授業でも、チャット機能を活用するなどして、学生の質問にきちんと答える、課題提出物を丁寧に見てフィードバックするというように、方法は変われど、今まで同様に十分なサポートさえすれば、対面授業に遜色ない授業をすることが可能です。むしろオンラインのほうが、学生と1対1で向き合いやすく、学生一人ひとりの様子がよくわかるといったメリットもあります。対面授業の再開後も、オンラインを活用し、さらにグレードアップした授業をしていけたらと考えています。
翻訳ソフトがあれば外国語を学ぶ必要はなくなる?
私は、大学で外国語を専門とするからには「学問」として学ぶべきだと思います。学問として学ぶとは、ただ、単語や例文を暗記するのではなく「なぜ、この表現になるんだろう?」「この文法は本当に正しいのだろうか?」と、すでにあるものを疑い、探求するということ。そこまで外国語を追究すれば、立派な知識人になることができます。そして日常会話はもちろん、ビジネス文書や論文などフォーマルな場にも通用する正確な英語を、自信を持って使えるようになるでしょう。高度な語学スキル、ITスキル、対人スキルを併せ持ち、これからの時代で活躍できる人材を目指してください。
一人で決めない、悩まない。周りの人を信じて、相談してみよう

-
私には大学3年生と高校1年生の息子がいることもあり、学生もわが子のように思っています。麗澤大学の先生方は皆、同じような感覚ではないかと思いますよ。時には厳しいことを言うかもしれないけれど、学生を親身にサポートしていこうとする教職員が、麗澤大学にはたくさんいるからこそのこと。高校生の皆さんの周りにも、皆さんのことを大切に思う人がいるはず。周りの人を信じて、進路のことでも何でも、相談してみてください。一人で悩んだり、自分だけで何でも決めたりしないこと。言われたことに全て従えという意味ではありませんが、自分よりも長く生きて、世の中や人生のことを知っている人たちの意見を聞くことは、それだけで価値があるし、その人たちはきっと、皆さんの支えとなってくれますから。







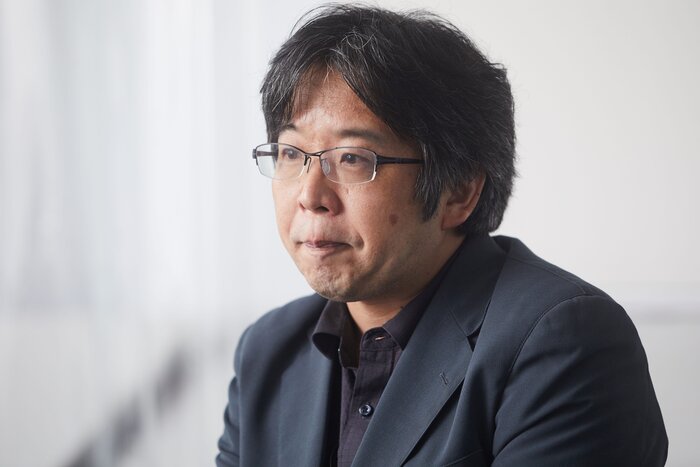





















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

