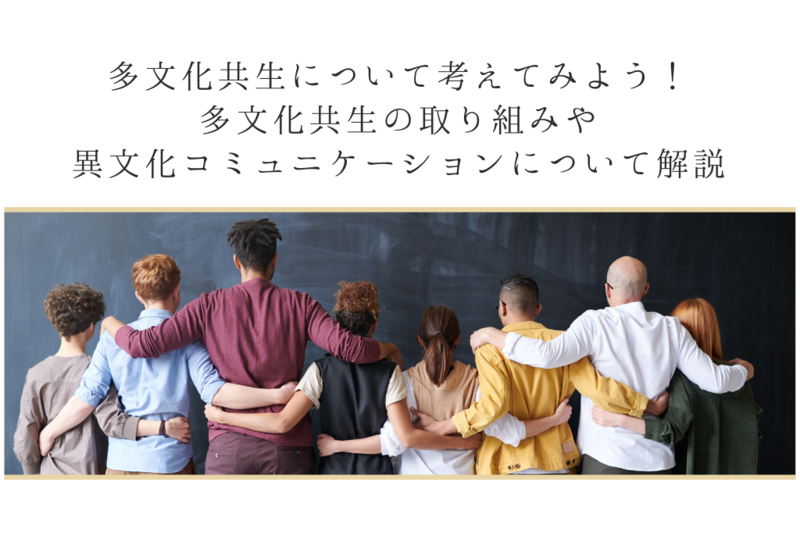
【麗澤大学国際学部国際学科 金孝卿教授監修】多文化共生って具体的にどういったもの? グローバル化が進み、近年では留学や働きに日本へ来る外国人も増え街や学校、職場などで外国人とコミュニケーションをとる機会も増えてきました。 今回は日本の多文化共生に必要なこと、また異文化コミュニケーションについて国際学部国際学科の金教授にお話をうかがい、多文化共生先進国の取り組みについてもまとめて紹介します。
日本には日本の人口の約2%ほどの外国人が住んでいると言われています。
また、2020年からのコロナ禍の影響でこの2年ほどは激減しましたが、それでも昔に比べ日本に旅行に来る観光客の数は上昇傾向にあります。
多文化共生はこれからの未来に必要不可欠になっていく取り組みで、私たちはこれに対してしっかりと考えていく必要があるのです。
まずは多文化共生とは何か学ぼう

皆さんは「多文化共生」という言葉を知っていますか?
総務省によると、多文化共生とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義されています。
つまり、日本人であっても外国人であっても異文化を理解しようと努め、一人ひとりの違いを認め合い、互いに協力し合って豊かな地域社会にして生きていこうとする考え方のことをいいます。
海外からの日本移住者・留学生や観光客に向けてどんな取り組みをしているのか

地域社会が多文化共生を実現させるための取り組みには、通訳や外国人向け多言語相談窓口などの「コミュニケーション支援」や、日本語指導が必要な子供たちのための日本語教室、外国人の安定した職場環境づくりなどの「生活支援」をはじめとするいくつかの大きな柱があります。(※)
日本では海外からの移住者や留学生、観光客に対して実際にどのような取り組みがなされているか、ここから具体的に紹介していきます。
(※)参考:総務省多文化共生の推進より
実際に行われている日本国内の取り組みについて
【福島県 新型コロナウイルスに関するSNS通話での相談】
福島県では、在住外国人向けに新型コロナウイルス感染症についての不安や、生活の困りごとなどを相談するホットラインを24時間体制、20言語対応での相談対応を行っています。
元々は電話回線のみでの対応だった相談ですが、スマートフォンしか持っていない留学生や技能実習生のために、LINEを利用して相談できるように改善されました。
【石川県小松市 市からの通知の二次元コードによる多言語対応】
市から住民に送付される重要な通知について、封筒の見えやすいところに二次元コードを印刷し、英語とポルトガル語で翻訳されたホームページにアクセスできるようにしました。
「二次元コードがあったため給付金があることを知ることができた」という声もあり、重要度が高いものから順次多言語化を進めています。
【株式会社菅原工業 技能実習生の受入れ・支援の整備】
株式会社菅原工業では、ムスリムが多いインドネシアからの技能実習生のために、礼拝スペースを設置したムスリムフレンドリーのインドネシア料理店「WARUNG MAHAL(ワルンマハール)」を開設しています。
日本とインドネシアの食文化を学
び合うワークショップもこの料理店で開催されており、地元の日本人住民に対する多文化共生に関する意識啓発を目指しています。
【福岡県北九州市 北九州市外国人就業サポートセンター】
サポートセンターでは市内の企業と留学生のマッチングから、面接、雇用手続きまで市が行い、留学生の就職支援を行っています。
令和 2 年度には実際に企業から69件の専門相談を受け、206人のうち13人が市内企業への内定に繋がりました。
日本語能力や給与水準面でのミスマッチも生じているため、企業セミナーや、留学生へ就職ガイダンスの開催を行うなどミスマッチ解消のための取り組みを強化しています。
【愛知県西尾市 乳幼児を持つ外国人住民向け防災支援事業】
愛知県西尾市では、外国人が災害時弱者にならないために8言語に対応した防災リーフレットを作成し、配布しています。
4ヵ月児健康診査時に合わせて防災リーフレットを配布し、市職員が保護者にその内容の説明を、さらには外国人の保護者に日頃の困りごとの聞き取り調査を実施しています。
また、いつでもどこでも見られるようにインターネット上でも公開しています。
【東京都 外国人人権啓発動画等のコンテンツの配信】
動画配信サイトを利用して、外国人観光客や外国人住民に関するヘイトスピーチなどの課題を紹介したり、東京都の取り組みなどを配信しています。
動画以外のコンテンツでは幅広い層への啓発効果を期待し、ホームページやSNSを通じて、外国人の人権コミックエッセイを制作・公開しており、これらのコンテンツは外国人の人権や多文化共生の啓発に貢献しています。
参考:総務省多文化共生事例集(令和3年度版)より
多文化共生が進んでいる国の取り組みは?
多文化共生が進んでいる国の取り組みをみてみましょう。
例えば多文化主義のオーストラリアでは多国籍エリアが点在しており、スーパーマーケットにも、世界各国の食材や菓子が並んでいたり、積極的にイベントを通して異文化交流が行われています。
また、オーストラリアのクイーンズランド州の取り組みでは、1998年以来、難民、留学生、庇護を求める人々、移民など、新たにクイーンズランド州にやってきた5,000人以上の人々を毎年支援しています。(※)
世界中から子どもたちが集まるスイスでは、ヨーロッパ諸国を中心に20〜30ヵ国の学生が一緒に学べる環境にある学校もあります。
言語もドイツ語、フランス語、イタリア語、レート・ロマンシュ語と4つの公用語があり、さらには英語教育もあります。これらの教育は段階を踏んで幼稚園、小学生の頃からスタートし、子どもの頃からさまざまな国の文化にふれます。文化の違いや考え方の違いに戸惑いながらも、自然と仲良くするためのコミュニケーションを積極的に取れるようになっていくのです。
ベトナムでは、ベトナム人の日本への関心が高まっており多くのベトナム人留学生や技能実習生が日本へ入国しているのは皆さんもご存知かと思いますが、ベトナム国内でもベトナムに住む日本人とベトナム人が協力して積極的に日本の文化をベトナム国内へ伝えており、ジャパンフェスティバルや日本の文化を伝えるイベントは各地で行われており、異文化交流は積極的に行われています。
日本も、これらの国から学べることも多くあるはずです。
(※)参考:Multicultural Australiaより
麗澤大学国際学科の日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻で学ぶこと

麗澤大学の国際学部 国際学科 日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻では、留学生とともに学ぶクラス編成で日常的に多文化共生を体験することができ、専門的に日本語や日本文化を学び、さらに英語と第二外国語(ドイツ語、中国語、韓国語)を使って「発信力」を鍛えることができます。
グローバル社会で活躍するためには言語や文化的背景の異なる他者を理解することが不可欠です。そのためにはまず自分自身を知る必要があるため、私たちが住む国「日本」を多角的な視点で学び、世界の視点から改めて日本の文化・言語・社会などを学びます。
英語と日本語の高度な運用技術を身につけて、世界に「日本」を発信したい人、グローバル社会で通用するコミュニケーション能力を身につけたい人、そんな人におすすめの専攻です!
日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻在学留学生の声を聞こう

■(左)グェン ゴック タン タオ:ベトナム ニャチャン出身
■(中)羅 程允(ナ ジョンユン):韓国 礼山郡出身
■(右)カク センイ:マレーシア クアラルンプール出身
日本人学生と外国人留学生が "日常的異文化空間"で、共に多文化共生と日本について学ぶ、国際学部の日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻(以下、JIC専攻)
。どんな環境で、どのように学んでいるのか、2020年に入学した3人の留学生にインタビューを行いました。
【麗澤大学、JIC専攻で実際に学んでみていかがですか?】
カク:JIC専攻では、日本のことだけでなく、国際的な事柄も含め学べることが楽しいです。様々な国籍の学生が在籍しているので、それぞれの国ならではの価値観や意見を交わし合うことができます。たとえば、「社会学概説」という授業では、社会で問題視されている時事問題について学びを深めています。先日の授業では、「ジェンダー平等」をテーマに討論しました。中国の家庭では、「夫よりも妻の地位が高い」ことや、日本人の中には「夫は外で働き、妻は家庭を守るのが当たり前」と考える人もいたことに驚きました。母国マレーシアは、男女平等社会なので性別で役割を決めることはしません。しかし、マレーシアはマレー人を経済的に優遇する国策「ブミプトラ政策」があるため、逆に民族間での平等はありません。その国々で、こんなにも考え方が異なるんだと痛感しました。
グェン:私も「社会学概説」は好きな授業のひとつです。印象深いのは、賄賂問題について議論した時のこと。大多数の学生が、親が子どものために賄賂を贈ることについて反対派でしたが、私は子どもに良い教育を受けさせるためなら、必ずしも悪いこととはいえないと意見を述べました。しかし、同じベトナム出身の学生の意見は「私は賄賂を贈ることについて反対です。私は贈りません」と。同じ国の人であっても意見や考え方まで同じとは限らないなと思いました。
羅:日本と世界の歴史やつながりについて学ぶ「国際交流史」もおもしろいですよ。この授業では、最後に講義の感想を全員で共有しています。先日、日清戦争について学んだ際に、日本人学生の発言から自分とは違う目線の意見を聞くことができ、考えさせられました。JIC専攻では、ひとつのテーマを様々な観点から考える機会が多く、世界について深く学ぶことができるようになりました。
【高校生の皆さんへメッセージをお願いします!】
羅:麗澤大学は本当に素晴らしい大学です。将来、グローバルな舞台で活躍することを目指すのであれば、選択肢のひとつとしてぜひ、麗澤大学を検討してみると良いと思いますよ。
グェン:JIC専攻は、国際社会のミニチュアのような環境です。多文化に触れながら学んでみたい、国際性を身につけたい人にぴったりだと思います。
カク:大学生になれば、自分の学びたいことを学ぶことができますし、サークルなどの課外活動にも挑戦できます。また様々な国の友達と出会い、国際的な感覚を養うこともできます。4年間の充実した大学生活を楽しみに、高校での勉強を頑張ってください!
引用:留学生から見た麗澤大学 ~国際学部の日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻では留学生とともに学ぶ~
共に生きていくために! 近い未来に必ず訪れる多文化共生社会を見据えて

国際化がどんどん進んでいく中で、日本に来る外国人観光客や、留学・就労のために移住してくる人は今後も増えていくでしょう。
異文化への理解を深めるためには、日本語や日本文化の理解は欠かせません。
「常識」という考え方を捨て、お互いの文化を客観的に捉え、尊重し、誰もが安心して過ごせるような多文化共生社会の実現を目指しましょう!























 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

