
日本語教師を目指し、日本語・国際コミュニケーション(JIC)専攻(現在の日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻)(以下、JIC専攻)で勉強している田端穂香さんへのインタビュー。前編では、日本語教師になるための日本語・日本語教育の学びについてお話を伺いました。後編ではJIC専攻の学びについて、そしてJIC専攻と麗澤大学の印象、将来の夢についてお話を伺いました。

(現在の国際学部 国際学科 日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻)2019年入学
※取材時、3年次生
「意見交換の場をつくる」授業づくりを学生が実践
JIC専攻は、異文化理解や多文化共生について学ぶ機会が多く、中でも印象に残っているのが金孝卿先生の授業「多文化共生メソドロジー上級演習※」です。多文化共生にまつわる課題に対して、他者との意見交換の場をつくり上げる実践形式の授業です。具体的には、グループに分かれて、その回の「話題提供および場づくり」担当者になった学生が自由なテーマで自ら授業を展開し、場づくりの実践を行います。たとえば中国人と韓国人留学生のグループは自国の料理を話題に取り上げたり、国際問題を取り上げるグループもあったりと、本当にさまざまなテーマで授業が行われました。参加者側もその話題について調べた上で授業に参加し意見交換をするので、一緒に学ぶ仲間を通して多様な世界に触れることができました。
クラスメイトは皆、とても楽しそうに、しかも真剣にディスカッションしてくれて、私一人では思いつかないような意見や実際に教育の現場で役立ちそうな意見がたくさん出てきました。皆で考えたほうが良いアイデアが生まれることを実感できましたし、多文化共生社会におけるコミュニケーションの重要性も感じました。
※2016~2019年度入学者カリキュラム科目。
皆違うのが当たり前。だからおもしろい。異文化理解は身近なことだった
JIC専攻の授業はディスカッションとグループワークがとにかく多く、学生同士、良い意味で遠慮なく、自分の思っていることを言い合える環境があります。おかげで、JIC専攻の学生は皆仲が良いです。コロナ禍前は、皆でキャンパス内の芝生でお弁当を食べるのが楽しみでした。

-
私は、皆とディスカッションする時間が大好きです。いろんな人の意見を聞いて、自分の考えも伝える。すると、一緒に学んでいる仲間同士でも考え方やカルチャーの違いに気づき、驚くことが多いです。「異文化理解」と聞くと、何だか自分からは遠い世界の話のように感じていましたが、実は身近なことでもあるのだと思いました。皆違うのが当たり前で、違うからこそおもしろい。麗澤大学で過ごしたからこそ、気づけたことだと思います。
私が学びの場をつくってあげたい! 外国人児童の課題と向き合う
麗澤大学の先生方は、とても親身で相談しやすいと思います。勉強のこと、進路のこと、先生にいつも相談しています。それだけでなく、先生方は、日本語学校のアシスタントや外国人の子どもたちとのワークショップなどの機会があると「今度こういうのがあるから、やってみない?」と声をかけてくださいます。先生方のサポートのおかげで、学外でもいろいろな経験を積むことができましたし、そこで出会った人と新しい活動を始めたり、紹介していただいた日本語学校の先生とご縁ができたりと、世界がどんどん広がっています。
-
大学卒業後は、麗澤大学大学院に進学する予定です。修士課程を修了すれば大学教員になることも可能となり、キャリアの幅が広がります。私は学費を節減するため、通常2年間要するところを1年で修了する「日本語教育プロフェッショナル・コース」を選択する予定です。このコースは麗澤大学のJIC専攻、あるいは日本語教員養成課程を修了見込み※である学生が、大学4年次に大学院修士課程の科目を履修することで、1年で修士課程を修了することができるというものです。大変だよ、と先生から念を押されていますが、覚悟してチャレンジします!

大学院を卒業したら、まずは日本語学校などでキャリアをしっかりと積み、将来は外国人の「不就学児童」をサポートする活動をしたいと考えています。そう思うようになったきっかけは、授業で「日本にはきちんと学校に通えていない可能性がある外国人児童が約2万人もいる」という現実を知ったことです。日本語で行われる授業についていけず学校に行かなくなる子ども、外国人の子どもは義務教育の対象ではないため、学費を払うことができずに通えなくなる子ども、経済面の理由で高校へ進学できない子どもなどがいます。外国人の子どもたちに対する支援が足りないのならば、自分も支援したい。その子たちの学びの場がないのなら、私がつくる! これが、将来私が本当にやりたいことです。
※このほか卒業研究、修得済み単位等諸条件があります。









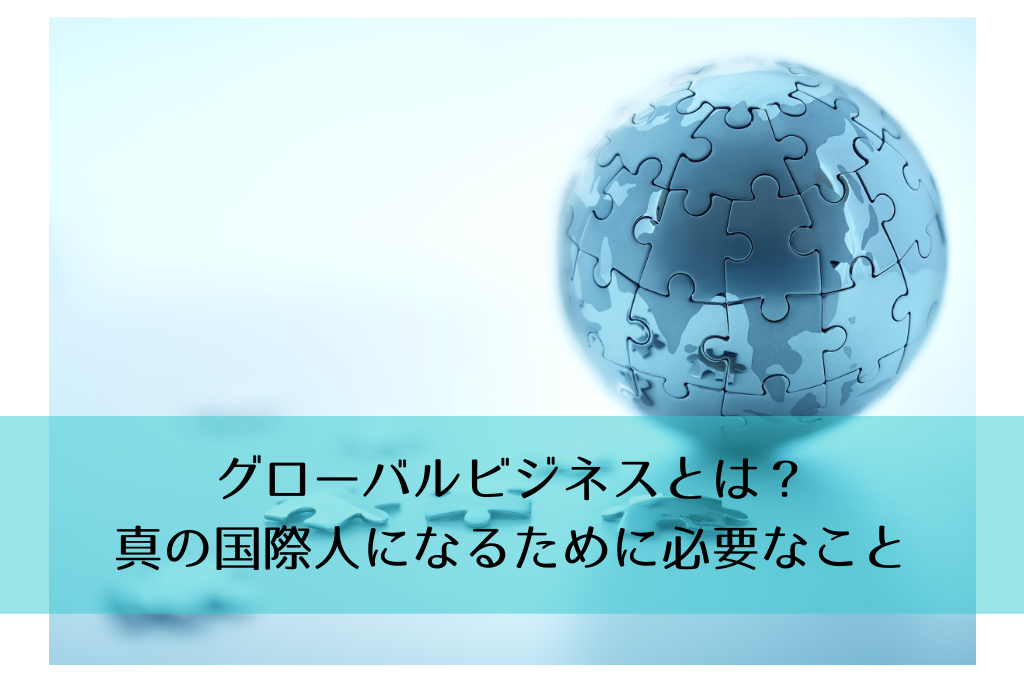



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

