
「お金を通して人に貢献できる仕事がしたい」と金融業界を志し、麗澤大学で経済学を学んでいる鎌塚さん。3年次には日本銀行が主催する経済・金融分野のプレゼンテーションコンテスト「第17回 日銀グランプリ〜キャンパスからの提言〜」に麗澤大学チームのメンバーとして参加し、全国122チームから上位5チームに選抜され、決勝大会進出を果たしました。鎌塚さんが日銀グランプリへの挑戦から得たもの、そして大学4年間で学んだこととは?

大好きな野球が教えてくれた、お金の意義
中学校に入学し野球部に入りたいと思った時、学校から配られた部費一覧を見て、「野球ってこんなにお金がかかるんだ!」とびっくりしました。私は小学校1年生から野球をしていて、野球をしている時間が本当に楽しくて幸せだったのですが、そんな大好きな野球ができていたのは、お金のサポートがあったからだと、その時初めて気がつきました。この体験から、お金とは選択肢を広げてくれるもの、やりたいことをやる自由を与えてくれるものなのだと考えるようになり、高校生の頃には、お金を通して人に貢献できる金融の仕事に就きたい、そのために大学では経済学を学ぼうと決意しました。
-
大学選びの条件は、少人数制であることでした。というのも、高校生の時に所属していた野球部が他の学校よりも小規模な環境で、その分監督が部員一人ひとりをよく見て指導してくださり、そのおかげで技術が向上した経験があったからです。大学も大人数で授業を受ける学校よりも、先生との距離が近い環境で学べる少人数制の学校のほうが、私は成績が伸びるだろうと思いました。

いくつかの大学を受験しましたが、第一志望の大学には受からず、合格した中から麗澤大学を選んで進学することにしました。実を言うと、麗澤大学は受験した中でも志望度が低い大学だったので、入学した時は「この大学で本当に良いのかな」とすごく不安でした。途中でほかの大学に編入学することも考えましたが、「今いる場所でやるしかない。ここで頑張れなかったら、どこへ行っても同じだ」と次第に思うようになりました。それからは「大学受験で第一志望の大学に進学できなかった悔しさは、就職活動でリベンジしよう。そのために4年間、今いる場所で一生懸命に頑張ろう」と心に決めました。
「日銀グランプリ」に挑戦し、チームで協働することの大切さを学ぶ
ゼミナールを選ぶときは、敢えて先輩方から「厳しい」「大変だよ」と聞いていた中島真志先生のゼミナールを選びました。就職活動に向けて自分を鍛えたかったからです。中島ゼミは毎年、日本銀行主催のプレゼンコンテスト「日銀グランプリ」に参加するのが恒例で、私たちも3年次の時挑戦しました。私たちのチームが提案したのは、グループ型投資の「Quintet投資」でした。日本は少子高齢化によって将来の公的年金給付額の減額が見込まれており、貯蓄や投資による資産形成が重要になっていますが、投資をする人は欧米諸国に比べて圧倒的に少ないのが現状です。初めての人が少しでも投資をしやすくするにはどうすれば良いかと考え、「グループ投資」という、複数のメンバーで共同口座をつくり一緒に株式投資をする形を考案しました。私がたまたま、映画「スタンド・バイ・ミー」を観ていて、映画の中で仲間が協力し合って困難を乗り越えていくように、投資も仲間がいればトライしやすいのではないか、と思ったことをヒントにしました。

-
予選は小論文による書類審査でした。アイデアを出した私が小論文を書くのが早いだろうと、チームのメンバーとよく話し合わずに一人で小論文を書いたのですが、これが大失敗。中島先生に提出したら「全然ダメだよ」と返されてしまいました。説得力やわかりやすさに欠ける、ひとりよがりな小論文だったからです。
行き詰まってしまい、メンバーに「どうすればいいかな?」と相談してみると、みんな快く「僕はこう思っているよ」「こうしたらいいんじゃないかな」と、いろいろな意見を出してくれました。自分だけでやっているつもりになっていたけれど、そうではありませんでした。実は皆もたくさん考えていたし、良いアイデアを持っていたことに気がつきました。
チームで議論しながら書き上げた小論文は、最初のものから格段に良くなり、全国122チームから上位5チームだけが選抜される予選を突破することができました。この時、人に頼ったり、協働したりすることの大切さを学びました。
伝統ある日本銀行本店でプレゼンテーションに挑戦
決勝に出るからには優勝したいと、そのためにできることはすべてやるつもりで臨みました。提案に抜けはないか何度も見直し、前年、決勝に進出した先輩方からもご指導を頂きながら、プレゼンテーションや質疑応答の練習を繰り返し行いました。
そして、いよいよ本番。決勝大会の会場となった日本銀行本店の前に立った時は、「テレビや教科書で見ていた建物だ!」と気持ちが高ぶりました。本番はものすごく緊張し、手や声が震えるほどでしたが、審査員からの鋭い質問にもどうにか回答し、すべてを出しきることができました。










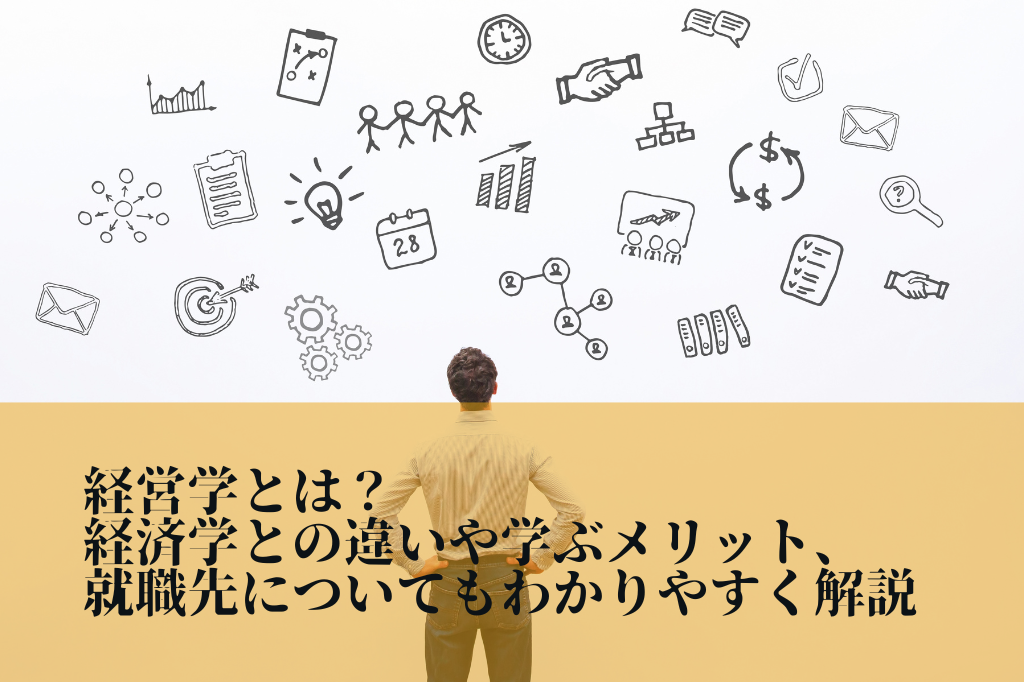

















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

