
ベネッセコーポレーションに在職中、通信教材のデジタル化に貢献した小田先生。麗澤大学では、最新テクノロジーを駆使して効果的な学習方法を設計する先進的な取り組みをしています。前編では、小田先生の学生時代とこれまでの職歴、そして麗澤大学との出会いについてお話を伺います。

アジアを中心に10ヵ国以上訪れた学生時代
学生時代、私は多様な文化に触れることに夢中でした。幼い頃から本を読むことが好きで、特に海外の文化や風習にとても関心がありました。海外の本の中には、その頃の私には見たことも聞いたこともない名詞が多く出てきました。たとえば『小公女』の中に描かれていた「屋根裏部屋とはどういうものなのだろう」などと、よく想像していました。

-
そのような海外の文化や風習への関心から、大学時代にはバックパッカーとしてアジア各国を10ヵ国以上旅しました。春休みや夏休みの長期休暇を利用し、毎回1ヵ月程度滞在しました。初めて訪れた海外の地は中国の天津でした。自分がこれまで見たことのない、現地の人の様子や雰囲気に、日本との文化の違いを感じたことを鮮明に覚えています。自分とは異なる考え方に触れたことで、どのような文化的背景からそのような考え方に至るのか興味が湧き、もっと色々な国を見たいと思うようになりました。その後、シンガポール、マレーシア、カンボジア、タイ、ベトナム、ネパール、インドなどアジアの国々を訪れました。
コミュニケーションには英語を使用しました。どの国も英語は第一言語ではなかったため、お互いシンプルな英語で会話することができ、意思疎通にはそれほど困りませんでした。しかしながら、お互いを深く理解するためには英語力が足りず、自分の英語力をさらに伸ばさなければというモチベーションにもなりました。
「教育」と「テクノロジー」の融合に挑戦
大学院卒業後、大学生の頃に自分の旅行体験を発信するホームページを作成したことから、インターネットによる情報発信に関心を持ち、旅行情報サイトを運営するベンチャー企業に就職しました。当時は、従業員数20~30名くらいの会社規模だったと思います。ここでは、世界各地の旅行情報を旅行者が共有するサービスを立ち上げ、個人による旅行情報の発信という新しい価値創出に挑戦しました。初めて社会人として働く中で、自分の価値観の中で大切な部分がはっきりし、もっと仕事の中で社会に貢献したいという思いが強くなりました。具体的には父母がともに教師であるという家庭環境の影響もあったかもしれませんが、人の成長に関わる仕事をしたいと感じるようになりました。そのため、3年間その企業で働いた後、教育事業を展開しているベネッセコーポレーションに転職しました。
-
当時ベネッセでは、紙で提供していた通信教材をデジタル化するプロジェクトが立ち上がりました。私はそれまでも携帯電話を用いた学習教材の設計や進路情報サイトの運営に携わっていましたが、そのプロジェクトはそれまで紙で提供していた教材をデジタル化するといった、サービスの基幹に関わる大きなプロジェクトでした。これまで紙の教材を使用している時は、受講している児童生徒がどのように学習しているのかを知る機会は限られていました。しかし、教材をデジタル化したことで、学習ログが取れるようになり、いつ学習しているか、どこでつまずいたのかなど、受講生の学習情報が手に取るようにわかるようになりました。このプロジェクトを通して、デジタルを用いた学習環境の可能性にとても感動しました。

一方で、その時に自分が担当していたデジタル教材の設計は、本当にデジタルの可能性を発揮しきれていたのか、自問自答しました。そのため、海外のデジタル教材などを調査したところ、たとえば学習理論に基づき効果的に学習できるような設計を行っているなど、既存の教材設計の延長ではないデジタルならではの設計方法があるのではないかと感じました。その頃の私には、この分野の知識や経験が不足していると感じ、2年間ニューヨーク大学の大学院に留学し、理論や原則をもとにテクノロジーを活用して、効果的な学習活動を設計する専門家の育成を目指したプログラムで学びました。
麗澤大学とは偶然ではなく運命の出会いだった
麗澤大学との出会いは、私の人生において意味深い転機となりました。留学後は、政府機関や国際機関で経験を積み、並行して教育とテクノロジーの分野で自己を高めるため、博士課程に進学して学びを継続しました。修了後に大学教員の道を模索していたところ、同じ博士課程の研究室の友人が偶然にも麗澤大学の教員募集情報を見つけ、私のスキルと関心が、麗澤大学の求める人材像に合致すると感じ、その情報を私に伝えてくれたのです。テクノロジーの教育への活用が私の専門分野ですので、その時の麗澤大学外国語学部の外国語教育とテクノロジーに関する人材募集は運命的な巡り合わせだったと思っております。
友人が見つけて共有してくれなければ、私は麗澤大学と出会うことはなかったでしょう。この運命的な出会いは、私のキャリアにおいて新たな方向性を定めるきっかけとなりました。







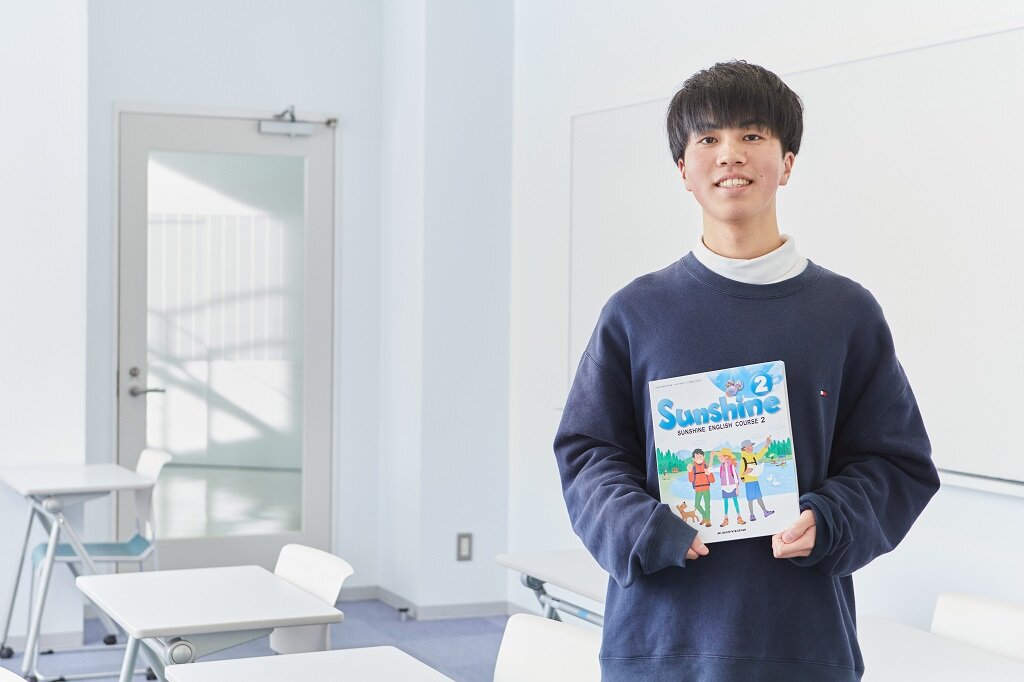



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

