
大学1年次の時、国際協力の現場で働くという夢を叶えるために、国際連合(以下、国連)の職員を目指すと決めた卒業生の宮野さん。その第一歩としてオックスフォード大学大学院に進学するべく1日10~15時間の猛勉強を続け、見事合格を勝ち取りました。前編では、宮野さんが国際協力に興味を持ったきっかけと、オックスフォード大学大学院に合格するまでの努力の軌跡を伺います。
※取材は2023年に実施。

ハンドボール三昧で、スポーツに熱中していた高校までの私
私は、高校では部活のハンドボールに全力で打ち込んでいました。強豪校ではなかったけれど、仲間と日々の練習に熱中していて、高校時代は正直まともに勉強したという記憶がありません。将来の夢については、普通の社会人になるんだ、と漠然と考えていた程度で、具体的なビジョンもありませんでした。勉強は苦手でしたが、高校3年生になった頃から少しずつ英語に興味を持ち始め、麗澤大学を知りました。自宅から通学可能なロケーションで、語学を勉強する環境が「手厚い」という評判を聞き、関心を持ちました。

-
無事に大学から合格をいただき、大学入学直前の春休みに英語を少しでも勉強しておこうと思い、初めて英語で書かれた原書を手にとりました。それは『Unbowed: A Memoir』(ワンガリ・マータイ)でした。たまたま選んだこの本の内容がアフリカに関することでしたが、紛争や貧困などの問題に触れて、大きな衝撃を受けたのを覚えています。それまで私はぼんやりと日々の生活を送っていましたが、この本によって「誰かの役に立ちたい」と強く心を動かされ、国際協力や開発学に興味を持ち始める大きなきっかけとなりました。
大学入学と同時に、私には国連で働きたいという夢ができました。国連への就職をゴールにして、逆算して調べていくと、最低でも修士の学位が必要だということがわかりました。それならば、英語圏の大学院で修士号を取ろうという考えにいきつき、イギリスの大学院への進学を検討し始めました。英語圏の国の中でも、イギリスに絞ったのには2つの理由があります。1つは、アフリカ研究と開発学に興味があり、イギリスの大学院が特にこれらの研究に強いということ。もう1つは学費がアメリカより安かったことです。大学院進学を心に決めた日から、私の勉強漬けの毎日が始まりました。
夢に向かって徹底的に語学力を伸ばすために猛勉強した大学時代
イギリスの大学院はIELTSという英語の試験を使っていますので、IELTSの傾向と対策を念頭に置き、まず1年次はとにかく英語の勉強に集中しました。嬉しいことに少しずつ英語力が伸びてくるのがわかり、授業以外でも洋書や専門書、他の論文などを読むようになりました。
-
大学での最も大きなご縁は、ヨネスク先生との出会いでした。入学してすぐ、ヨネスク先生に「イギリスの大学院に留学したいこと」「将来は国連に就職したいこと」を話しに行きました。すると先生は、「すごく難しくて大変だろうけど、翔太郎が頑張るなら、私もサポートするよ」と私の志を真摯に受け止めてくださったのです。大学の4年間はヨネスク先生に本当に頼りっぱなしでしたね。開発学やアフリカ研究の専門分野においてものすごくサポートをしていただきましたし、授業外でも先生の研究室でご指導くださるなど、必死に私を鍛え上げてくださいました。


-
大学2年次に約9ヵ月間ウガンダに留学した経験は、特に有益でした。アフリカの大学との留学提携がない中で、留学先を探すのはなかなか大変でした。しかし、梅田先生が現地の知人を介して私を紹介してくださり、幸運にもウガンダの大学への個人留学を叶えることができました。いざ現地を訪れると、ストライキや暴動が日常的に起こっており、生活面で不安な場面もありましたが、徐々に現地の生活にも慣れていくことができました。一番思い出に残っていることは、難民キャンプに行ったことです。親がいない難民の子どもたちから生活状況を聴き取り、何が必要かということを自分たちで知ろうというものでした。実際に調査することで新しい気づきが多々あり、「もっと勉強しよう」とモチベーションの向上につながる経験となりました。
帰国後はさらに勉強の意欲に火が付き、イギリスの大学院の中でも、オックスフォード大学への進学が徐々に視野に入ってきました。オックスフォード大学大学院の試験では「経験」が重視されるので、ウガンダへの留学経験があり、さらに大学3年次にはアフリカの若者開発に関する論文を出版する経験も積んでいた私は、手ごたえを感じていました。先生方にはたくさんお世話になったので合格しなければというプレッシャーもあったので、無事に合格通知が届いた時は本当に嬉しかったです。

-
彼からオックスフォード大学大学院への進学の意思を告げられた時は、特に驚きませんでした。「ギリギリで受かるのではなく、オックスフォードの教室の一番前に座って、教授に堂々と質問し議論ができるくらいの力をつけて、入学しよう」と言いました。実際に出願して、受験が終わるまで、私は特にドキドキもしませんでした。ひたむきに努力した彼が受かるのは当然だし、もし彼を選ばないとしたら、オックスフォードは優秀な学生を見る目がない、とまで真剣に思っていました。もし不合格で、少々大学で周り道をしたとしても、彼が本当にやりたいことにたどり着く道は揺るぎないと確信していました。













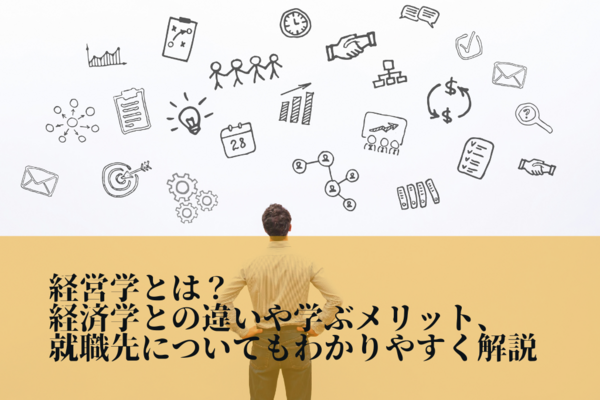
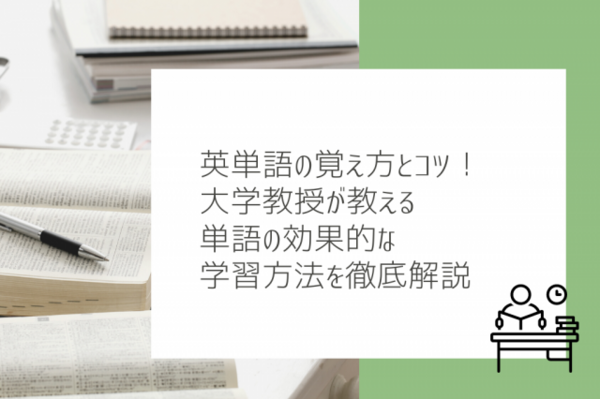
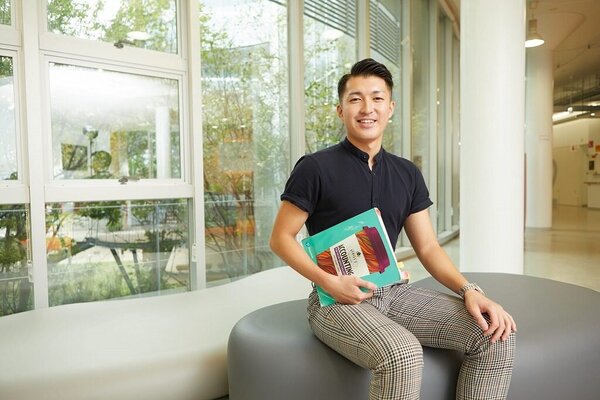











 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

