【前編】興味を抱いたらすぐに挑戦!文理融合のキャンパスで拓く、新しい学びの可能性
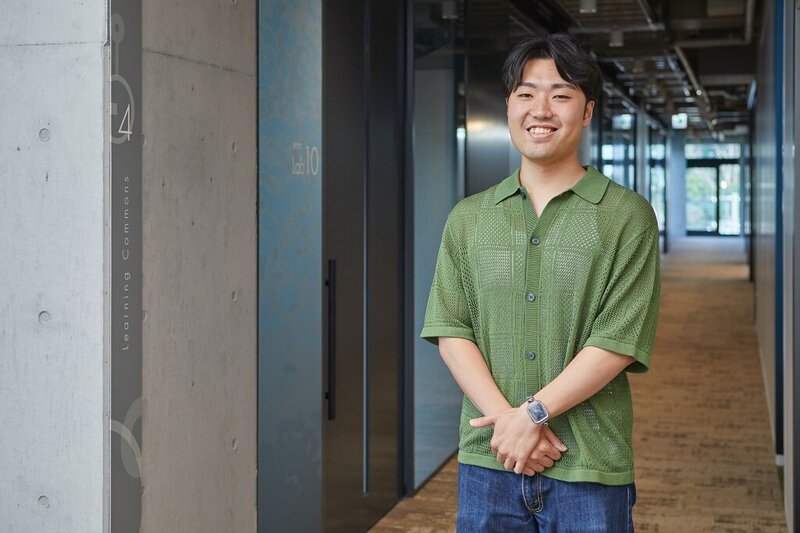
経済学部で「行動経済学」を学び、アフリカの貧困問題を改善すべくプロジェクトを立ち上げた笹谷直生さん。自主企画ゼミナールでは、福島の声を届けるドキュメンタリー映画の制作にも挑戦しています。前編では、経済学部を専攻した理由や麗澤大学の魅力、アフリカの貧困問題をテーマにしたプロジェクトについて伺います。

生活を豊かにする「経済学」のおもしろさを学んだ高校時代
私が大学で経済学を専攻しようと思ったきっかけは、高校時代の社会科の先生の影響でした。先生は経済学部出身とのことで、ご自身の経験をもとにした経済の授業をしてくれました。親の勧めで元々経済学部は気になっていたのですが、その授業を通じて、ますます興味を持つようになりました。経済学は単なる理論ではなく、私たちの生活を豊かにする学問であることを実感し、「これこそ自分が学びたい学問だ」と強く感じるようになったことを覚えています。また、高校では国際教養コースを選択していたこともあり、ただ経済学を学ぶのではなく、培った語学力も活かして多角的に学びたいと思い始めました。
国際色豊かな環境で経済学を学ぶ。麗澤大学の魅力

-
数多くの大学の中から麗澤大学を選んだのは、国際的な教育環境が整っており、経済学を多角的に学べる点に強く魅力を感じたからです。高校3年生の時に訪れたオープンキャンパスで、麗澤大学にはiFloor(International Floor)という英語コミュニケーション能力を磨くことができる施設があることを知り、国際系の教育に力を入れている大学だという印象を強く抱きました。帰宅後、麗澤大学のことをより詳しく知りたいと思い、入学案内書を読み進めていくと、経済学部の教授である大越利之先生が経済学の応用について語る記事が目に留まりました。身近な問題を経済学の考え方を用いて解決する点に惹かれ、大越先生のもとで絶対に学びたいと思い、麗澤大学への進学を決意しました。
入学後、私は大越先生の授業を中心に履修しました。3年次生になると履修するゼミナールも大越ゼミを選択しました。大越ゼミでの学びの中で、「行動経済学」が特に印象に残っています。行動経済学とは、心理学と経済学を融合させた新しい学問です。経済学と心理学が組み合わさることで、社会課題をより深く理解でき、社会で必要となるスキル・知識を学ぶことができます。また、ゼミナールでは、プレゼンテーションをする機会が多いのですが、先生の口癖である「中学生にもわかるように説明しよう」という教えのおかげで、自分の考えを見直し、わかりやすく物事を説明できるようになったと感じています。
学びを活かして、アフリカの農家の貧困問題に立ち向かう
-
現在、私はアフリカの貧困問題に関するプロジェクトに取り組んでいます。きっかけは、アフリカの方の生活に迫るテレビ番組を見たことでした。自分の幼い頃の記憶とテレビで映し出されていたアフリカの様子を比べ、驚いたことを今でも覚えています。あれから10年ほど経過した今でもほとんど貧困問題が改善されていないことを疑問に思い、調べてみました。現状、政府は様々な施策を導入しているものの、貧しい生活から抜け出せない人もいることがわかりました。お金で解決するのではなく、人間の行動を変える行動経済学を用いて調査することで、課題解決できるのではないかと思い至り、大越先生にすぐに相談しました。その後、大越先生の後押しもあり、アフリカの農家の貧困問題を行動経済学で変えていくプロジェクトを立ち上げました。

プロジェクト発足にあたり、最初の難関となったのが資金調達です。行き詰まり、学生課に相談したところ、麗澤大学麗澤会の補助金制度を紹介してもらいました。このプロジェクトにかける想いをつづり、企画書を提出すると、審査を通過して麗澤会から30万円を補助してもらえることになりました。まさか支援してもらえるとは思っていなかったので、自分でも非常に驚きました。
行動経済学を通して、現地民の意識と行動を変えていく

-
プロジェクトの一環として、ケニアに住む貧困層の農家を対象に、行動経済学のナッジ理論を用いて、どのようなアプローチが彼らの行動を変えるのに効果的かを仲間とともに研究しています。まず、現地に住む日本人コーディネーターを通じて、ケニア人の金銭感覚や国民性、地域の特徴を調べていきました。その一例が、地形による貧困度合いです。ケニアの国土面積は日本の1.5倍ほどあり、エリアによって文化や生活様式が異なります。北部の山岳地帯では、農業が盛んで生活に困る人はほとんどいません。一方、南の沿岸地域は漁業で生計を立てている方が多く、都市部に比べ収入が低いのが現状です。こういった事実を踏まえ、調査対象者向けにチラシを作成・配布し、行動変容を促していきます。あと2ヵ月調査・研究し、結果をもとに卒業論文を書く予定です。
このプロジェクトで、大越先生には全面的にサポートしていただきました。「調査は進んでいる?」とお父さんが我が子を思うように気にかけてくれる一方で、研究の話になるとリアリストな一面を見せます。「実行可能性はあるの?」「予算は十分?」と、現実的にプロジェクトが実行できるか否かをチェックしてくれました。このメリハリのある指導のおかげで、リラックスしながら伸び伸びと準備や調査に向き合えました。多くの方が関わっており責任も大きいですが、学生時代に国境を越えた調査に携わることができ、自分の中で誇れる経験となっています。プロジェクトが無事に終えられるよう、最後まで走り続けたいです。



























 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

