【後編】企業と連携し、社会で活躍するために必要なスキルやマインドセットを育む"基礎ゼミナールB"

AIをはじめとして次々と新しいテクノロジーが登場する変化の激しい時代の中で、必要とされる人材であり続けるためには、「アクション・シンキング・チームワーク」の3つから構成される「社会人基礎力」が欠かせません。基礎ゼミナールBでは実際に存在する企業と連携を取り、企業から与えられたミッション達成のために学生たちが主体性と応用力を持ってPBL(課題解決型学習)を行います。後編では、実際に「基礎ゼミナールB 」に参加して、授業の様子をレポートしていきます!


グループワークで磨かれる力、学生たちの成長の瞬間
本授業は4社と連携しており、学生は理念に共感した企業を選び、各企業が提示する独自のミッションに挑戦します。今回はHarito by NUIZAEMON様と協働する学生たちに密着しました。
授業の冒頭で先生が説明したのは、アンケート設計の重要性でした。たとえば「どのようなデータを収集するべきか」「設問の表現で回答率がどう変わるか」といった視点が成功の鍵になるそうです。これを受け、学生たちは自分たちが解決したい課題に沿ったアンケートを作成するべく議論を開始します。
-
4~6名ずつのグループに分かれた学生たちは、それぞれノートPCやスマートフォンを活用しながら設問の内容を詰めていきます。「この設問でデータが集まるかな」と誰かが問いかければ、仲間たちが「もっとターゲットを具体化したほうがいいかも」と答えるなど、活発なやり取りが続きます。1年次生ながらも真剣な姿勢で課題に向き合う様子が見受けられます。また、「誰にアンケートを取るのか」「回収目標はどれくらいが妥当か」といった現実的な課題に対しても、学生たちは協力して解決策を模索します。「この質問でデータが集まるだろうか」と頭を抱える学生もいれば、「もっと簡潔な設問にすれば回答率が上がるのでは」と提案する姿も見られます。実社会で必要な問題解決力や協調性を育んでいることが感じられます。

壁にぶつかっても、先生がサポートします!
先生方は各チームを巡回し、学生たちの進捗を確認しています。その指導スタイルには、それぞれの個性と工夫が光ります。
遠藤先生は、学生のアイデアを決して否定せず、「その考えもいいね、でも他の方法も考えてみるとおもしろいかも」と前向きなアドバイスを送り続けます。学生が、アンケートの回収人数を「100人」と提案した際には、「それではすぐに集まるかもしれないけど、データの有効性を考えるともっと多いほうがいいかもね」と、現実的な視点を優しく示します。このような具体的かつポジティブな指摘は、学生たちが議論を深めるきっかけとなっていました。

-
一方、冬月先生のアプローチは、発想を広げることを重視しています。「最初にアイデアを思い切り広げてみるといい。その中で現実的なものを選べばいいんだよ」という助言は、学生たちが固定観念にとらわれず柔軟な考え方を持つ手助けとなります。また、先生自身が「ここまでやってもいい」という安全域を示すことで、学生たちが安心して挑戦できる環境を提供していました。この手本となる姿勢は、学生たちにとって大きな支えとなっているようです。
このように、先生方は学生たちの自主性を尊重しながらも、必要に応じて的確な方向性を示します。学生たちが壁にぶつかった時でも、解決策を見つけるためのヒントを提供しつつ、成長を見守る姿勢が印象的でした。
成長への架け橋、実学がもたらす未来
-
この授業を通じて、学生たちは実社会に近い環境で課題解決に挑むことで、確かな自信と実践力を身につけています。
授業の終盤、学生から「まだ不安な部分もあるけれど、アイデアの実現に近づけることができた」という声もあがり、挑戦の成果が実感されている様子でした。


-
さらに、本授業で培ったスキルは、社会人として活躍する上で欠かせない力となります。知識を応用する力、多様な視点を持つ力、そして困難な状況にも立ち向かうチャレンジ精神など、この授業で得たものは未来を切り拓く実践的な力となっているのです。
麗澤大学の建学精神にもとづき、地域や企業と連携しながら、学生たちは「社会人基礎力」を鍛え、自分自身の可能性を広げています。先生方のサポートと実学の力を活かしたこの取り組みは、学生一人ひとりにとって大きな成長の場となり、社会での活躍を後押しする架け橋として機能しています。基礎ゼミナールBは、学生の未来を形づくる重要なステップであることを改めて実感しました。













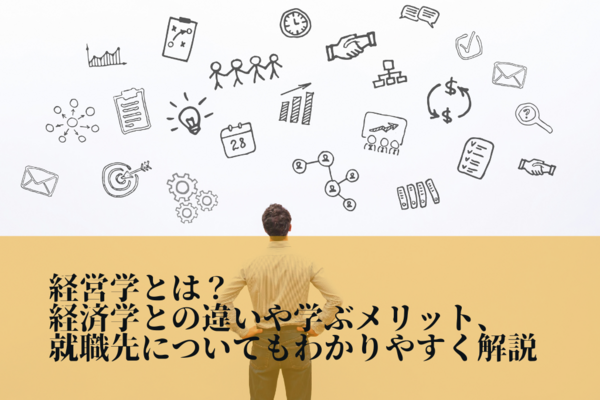
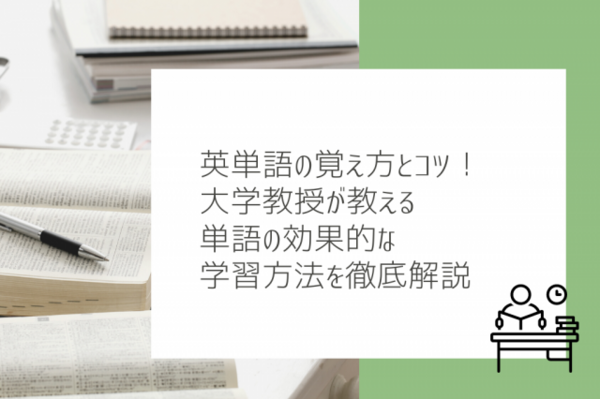
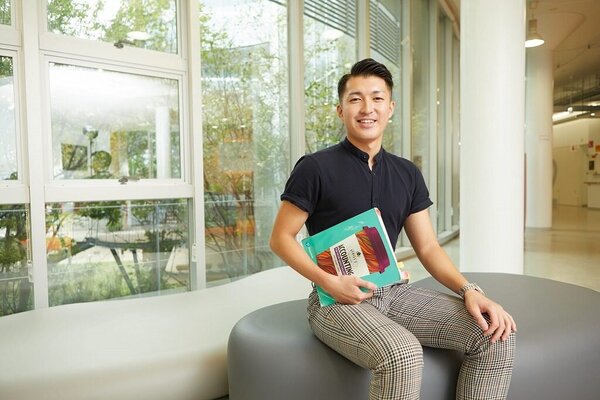











 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

