
外国語学部 外国語学科 英語・リベラルアーツ専攻では、英語を通じて文化や社会、国際的な問題を深く学べます。中でも、田中先生のゼミナールや田中先生が主導する外国人観光客サポートボランティア「ホスピタリTeeプロジェクト」では、語学力やコミュニケーション力以外にも幅広い教養を身につけ、価値観を広げることができます。前編では英語・リベラルアーツ専攻の学びと、田中ゼミについて伺いました。


※取材時、3年次生。
英語・リベラルアーツ専攻では何を学ぶのか?
―まずは外国語学部について教えてください。
田中先生:麗澤大学の外国語学部では、言語学習に加え、世界の文化や社会などについても学びます。現在は「英語コミュニケーション専攻」、「英語・リベラルアーツ専攻」、「ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻」、「中国語・アジアグローバル専攻」の4専攻があります。
―その中で、英語・リベラルアーツ専攻にはどのような特色がありますか?
-
田中先生:本専攻は、英語をツールとして活用しながら、異文化理解や社会問題の探究を行います。英語である理由は、私たちが高校までで学習してきたということに加えて、歴史的にイギリスやアメリカといった英語圏の国々が世界の中心的な役割を担ってきたことにあります。英語圏を理解することは、世界全体の動きを理解する上で重要であり、日本の社会や文化を深く理解する手助けにもなるでしょう。

この専攻の学びは、海外を「憧れ」で終わらせず、その背景にある現実や課題に目を向けることから始まります。国境を越えた幅広い教養と世界観を学ぶことで、英語力を磨くだけでなく、将来に向けてどのような知識や価値観を持つべきかを問い、幅広い教養を身につけることができます。そして、広い視野を持って自分の未来を描けるようになります。英語や大学での学びは単なるスキルではなく人生を豊かにするための手段と考えており、この専攻での学びは、学生一人ひとりが自己を見つめ直し、豊かな人生を切り開くきっかけとなります。
思いを届けるツールとしての英語を学ぶ
―印象に残っている授業はありますか?
羽生さん:どの授業も多くの学びを得られますが、その中でも「Research&Presentation」は私にとって大きな転機となりました。この授業は、自身で決めた研究テーマについて英語でプレゼンテーションを行うもので、英語を単なる学問ではなく、コミュニケーションの手段として実践的に学ぶことができます。

-
それまでの私は、発音や文法にこだわり、「正しい英語」を話すことを重視しすぎていました。原稿をつくり込み、完璧な準備でプレゼンテーションを行いましたが、担当の先生からは「もっと自分らしさを出していいんだよ」というアドバイスをいただきました。その時、英語は正しさだけを追求するものではなく、伝えたい思いを相手に届けるためのツールであるということに気づきました。この授業を通じて、私の学びの姿勢やコミュニケーションへの考え方が大きく変わりました。
自由×学び 田中ゼミの魅力とは
―田中ゼミの特徴を教えてください。
-
田中先生:私が担当するゼミナールでは、英語圏の歴史、文化、社会をテーマに、学生たちが多様な研究活動に取り組んでいます。最大の特徴は、学生が自由に研究テーマを選べる点にあります。決まった教材やカリキュラムに縛られることなく、学生たちは自分の興味にもとづいてテーマを設定します。たとえば、ファッション産業、環境問題、映画に描かれる差別問題など、幅広いトピックが取り上げられています。私自身も授業で多様な話題を提供し、それをもとに学生たちが「なぜそうなるのか」を深く考える機会をつくることを大切にしています。

そしてゼミナール活動の中心となるのは、学生たちが学期に2回行うプレゼンテーションです。各自が選んだ研究テーマについて発表し、その後のディスカッションを通じて内容を深めていくことで、それが卒業論文につながっていきます。プレゼンテーションの後にはほかのゼミ生から質問があり、そのやり取りを通じて新しい視点が生まれることも多くあります。また、質問者も深い考察を求められるため、発表者・質問者の双方が議論を通じて成長できる仕組みとなっています。
―田中ゼミの魅力を教えてください。
羽生さん:田中ゼミには決まった教材がないため、受動的に学ぶのではなく、自分の興味や関心にもとづいて能動的に学べる点が、一番の魅力だと感じています。
また、田中先生は、選挙制度の違いや世界の肥満率といった、普段の生活では意識しないようなトピックを持ってきてくれるので、たくさんの発見や気づきが得られてとても楽しいです。







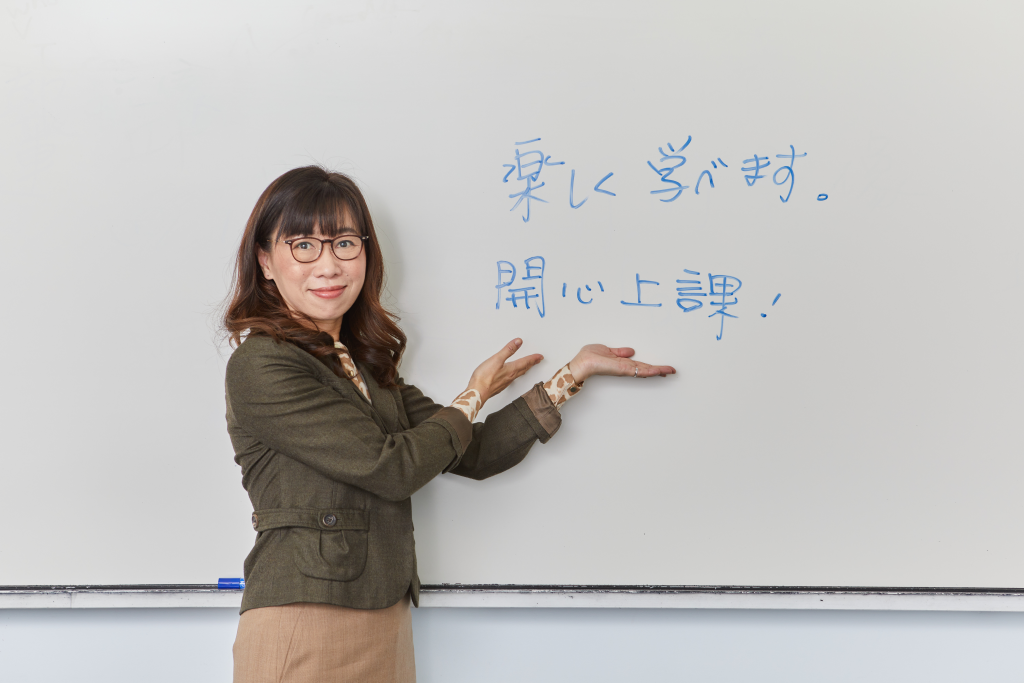

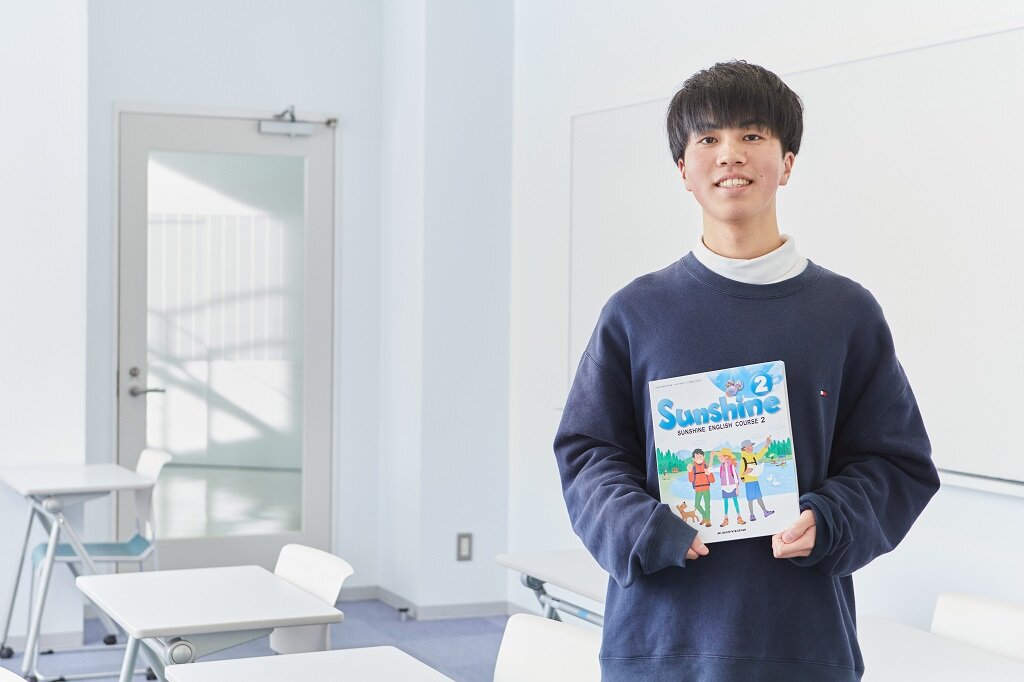



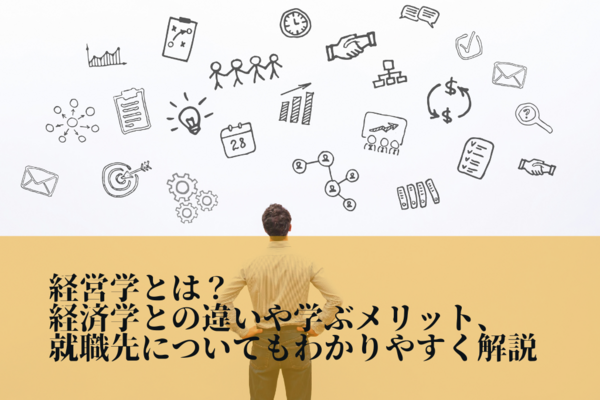
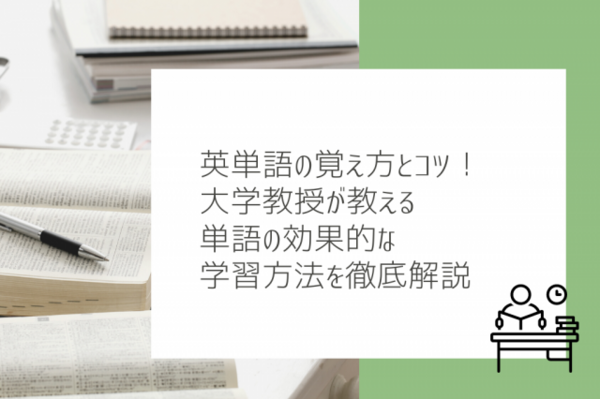
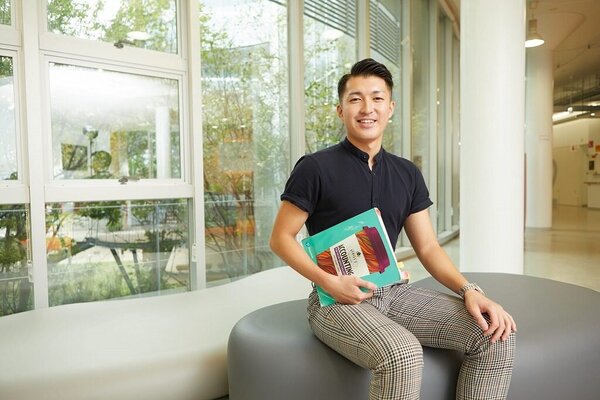











 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

