
外国語学部 外国語学科 英語・リベラルアーツ専攻では、英語を通じて文化や社会、国際的な問題を深く学べます。中でも、田中先生のゼミナールや田中先生が主導する外国人観光客サポートボランティア「ホスピタリTeeプロジェクト」では、語学力やコミュニケーション力以外にも幅広い教養を身につけ、価値観を広げることができます。後編では、「ホスピタリTeeプロジェクト」が始まったきっかけや、その活動に参加して得た学びについて伺いました。


※取材時、3年次生。
おもてなしの心を学ぶ「ホスピタリTeeプロジェクト」
―ホスピタリTeeプロジェクトの概要を教えてください。

-
田中先生:このプロジェクトが発足したきっかけは、麗澤大学の卒業生からの提案でした。当時、東京オリンピックの開催を控え、外国人旅行者が増える中、言葉の壁により日本人が困っている旅行者に声をかけられないという課題が浮き彫りになりました。そこで学生が「Need Help?」と書かれた「ホスピタリTシャツ」を着用することで、外国人旅行者との交流を促進できるのではないかと考え、私と外部の協力者と数名の学生で2014年に活動をスタートしました。
この活動は、外国人観光客にとっては、学生に手助けしてもらったことも、そして会話をする経験自体も旅行の思い出になっているはずです。一方で学生にとっては、積極的に行動することの重要性や「言葉が通じなくても気持ちは伝わる」というコミュニケーションの本質を体感できる貴重な機会となっています。
―ホスピタリTeeプロジェクトに参加したきっかけと感想を教えてください。
-
羽生さん:プロジェクトに参加したきっかけは、先輩がSNSでメンバーを募集しているのを見たことです。その頃、オーストラリア留学を控えていたこともあり、「少しでも実践的な英語に触れておきたい」という思いで参加しました。
印象的だったのは、奥手な私に対して先輩方が「一緒に楽しもうよ」と背中を押してくれたことです。言葉が通じなくても同じ空間に居ていいんだという安心感から「私も頑張って声をかけてみよう」と一歩踏み出すことができました。

この体験を通じて、英語を話せるかどうかではなく伝えたい気持ちを持つこと、積極的に行動することの重要性を学びました。英語が完璧でなくても、まず行動することで得られるものがあると実感し、その経験が自分に自信をもたらしてくれました。
言葉の壁を越え、異文化体験の幅を広げたい
―今後の展望を教えてください。

-
田中先生:まず、活動の多様化を進めていきたいと考えています。これまでは観光地での活動が主でしたが、今後は学内外の留学生や地域に住む外国人との交流も深め、異文化体験の幅を広げていきたいと思います。また、オンラインツールを活用し、海外の学生や団体との共同プロジェクトを実現することも目指しています。このような取り組みにより、学生たちは国際的な視野を持つだけでなく、デジタルコミュニケーションのスキルも自然に身につけることができるでしょう。
そして、プロジェクトの運営において、学生の主体性をさらに高めたいと考えています。これまでも「ホスピタリTシャツ」のデザイン(今年度新しく制作したTシャツは羽生さんのデザインによるものです)や活動内容の提案には学生たちが関わってきましたが、これをより一層強化し、学生が自らリーダーシップを発揮してプロジェクトを形づくる場にしていきたいと思います。
羽生さん:このプロジェクトを通じて私は、英語が完璧でなくても行動することが大切だと学び、言葉の壁を越えた交流の楽しさを実感しました。そんな経験を次世代の学生たちにも引き継いでいきたいと考えています。そのためにも今後は、新しいメンバーがもっと気軽に参加できるような環境をつくりたいと考えています。特に、英語に自信がない学生でも安心して挑戦できるよう、活動内容を柔軟に調整したり、先輩が積極的にサポートする仕組みを整えたりしたいと考えています。
教員と生徒の距離が近く、世代を超えた交流を楽しめる
―麗澤大学の魅力を教えてください。
田中先生:麗澤大学の魅力は、教職員、卒業生、そして学生の間の距離が非常に近く、世代を超えたつながりを感じられるところにあります。私自身も麗澤大学の卒業生であり、在学中には少人数制の学びの中で、教職員やほかの学生と家族のような関係を築きながら過ごしました。その経験が、現在教員として学生と向き合う上で大切な指針となっています。現代では学生が同年代との交流にばかり偏る傾向がありますが、麗澤大学では授業だけでなく課外活動やキャリア支援の場を通じて、教職員や卒業生との世代を越えた交流の機会が豊富に用意されています。この環境は、学生が自分の学びを深めながら広い視野を育むための重要な土台となっています。
-
羽生さん:麗澤大学の良いところは、温かくサポートしてくれる環境と、挑戦を後押ししてくれる文化です。入学してまず驚いたのは、先生方がとても親身になって学生一人ひとりと向き合ってくれることでした。授業でわからないことがあれば気軽に質問でき、進路の相談にも時間を惜しまず応じてくれます。この距離の近さが、学びやすさにつながっていると感じます。
また、少人数制の授業が多いため、学生同士のつながりも深まります。クラスメイトと一緒に意見を交わしながら進める場面が多いので、学問的な学びだけでなく、人間関係の構築力やチームでの協力の大切さも学べます。

自分らしさを見つけ、磨いていこう!
―最後に、高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
田中先生:大学は人生を大きく広げる場所です。麗澤大学は、皆さんが自分の興味や関心を深く掘り下げ、自分らしく成長できる環境を提供します。大学での学びは、単に知識を得るためのものではなく、将来に向けてどのように生きたいか、何を大切にしたいかを考えるための時間でもあります。
特に、私が大切にしてほしいと思っているのは、行動することです。失敗を恐れる必要はありません。何かを学ぶためには、まず一歩踏み出すことが大切です。麗澤大学では、少人数制の授業や課外活動を通じて、一人ひとりが自分らしく学べる環境が整っています。また、教員や先輩たちが皆さんを全力でサポートしますので、安心して挑戦してほしいと思います。

-
羽生さん:高校生の皆さんの中には、「本当にやりたいことって何だろう」「自分に自信を持てない」「周りの目が気になって行動に移せない」と悩んでいる人もいるかもしれません。私自身も、好きなこと・楽しいことって何だろう、とモヤモヤした気持ちを抱えながら日々を過ごしていました。
しかし、麗澤大学に入学してから、私の人生は大きく変わりました。麗澤大学は、ありのままの自分で良いと思わせてくれる、温かくて居心地の良い場所です。そして、やりたいことがあればどんな小さなことでも自由に挑戦できる環境があります。さまざまな挑戦をする中で、自分らしさが見つかり、本当にやりたいことに出会えます。
もし今の自分に自信が持てない、何かを変えたいと考えている人がいたら、ぜひ麗澤大学に来てみてください。ここでの経験は、きっと新しい自分との出会いにつながるはずです。







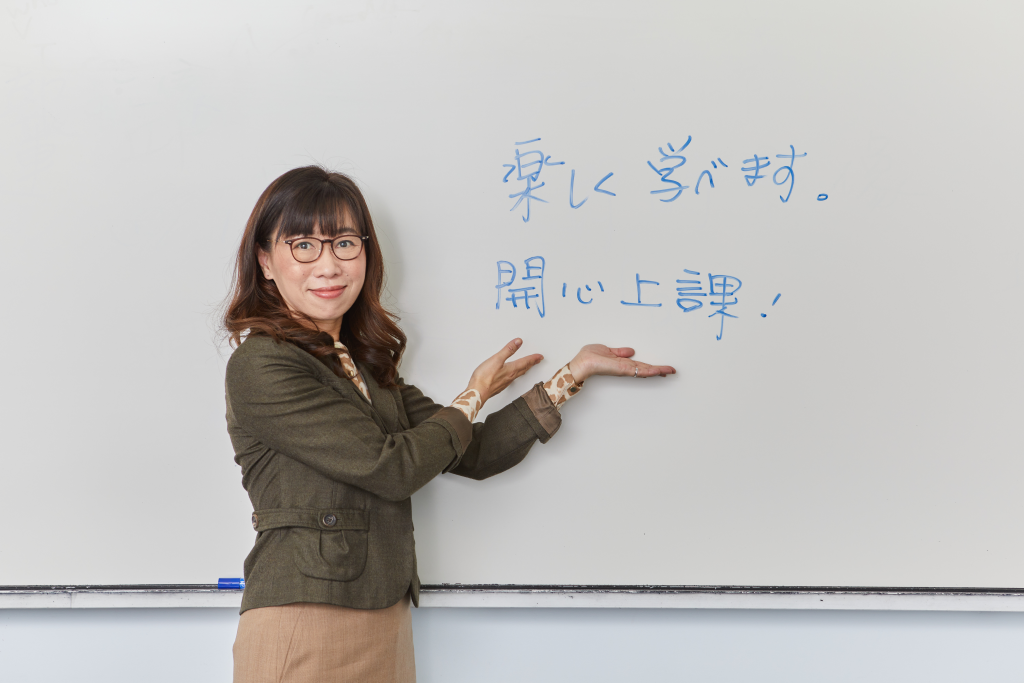

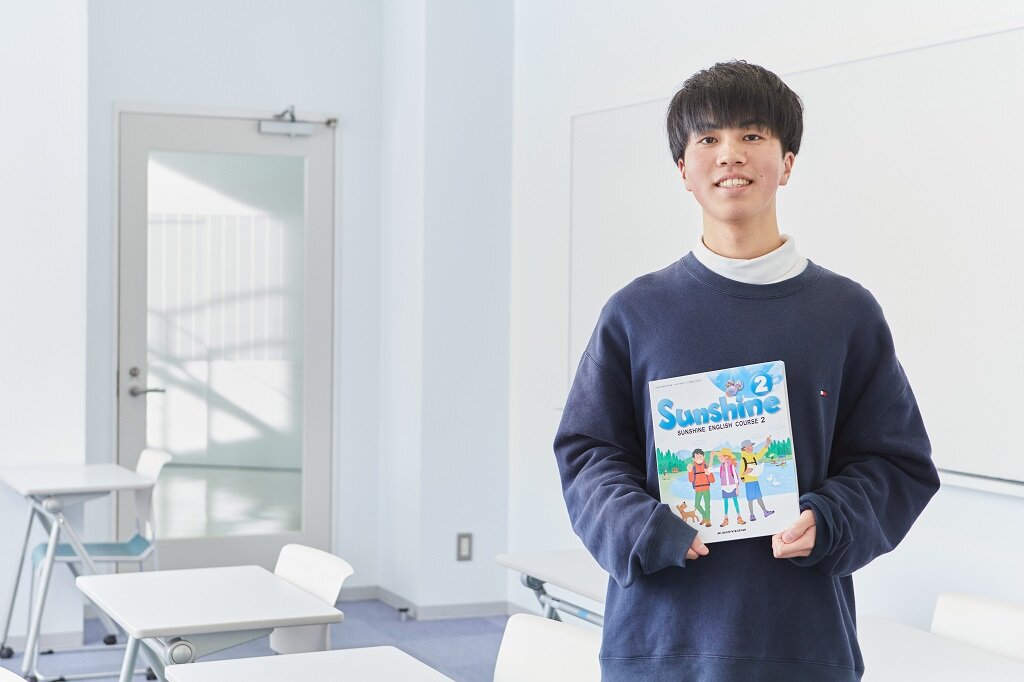



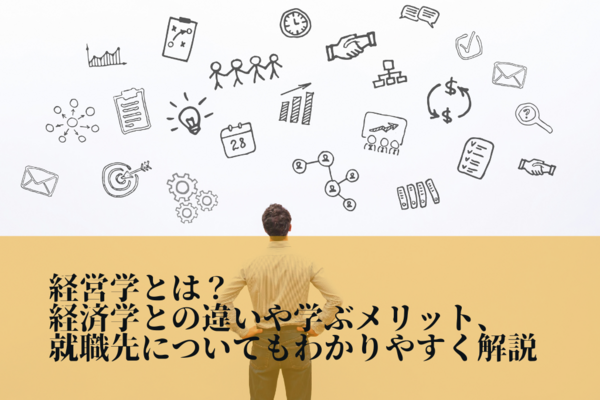
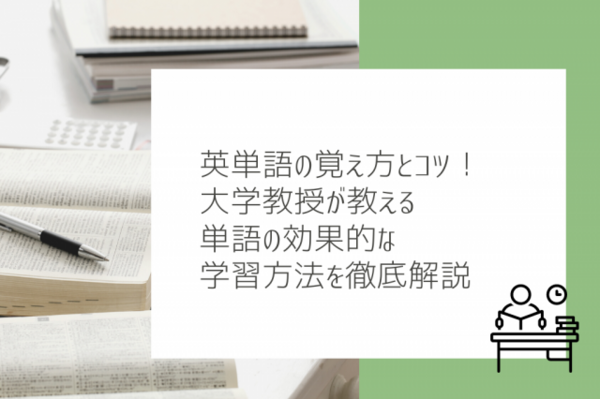
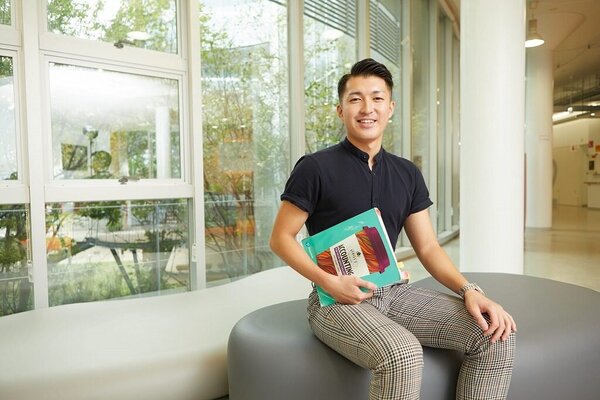











 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

