
今回ご紹介するのは、ミロシュニック先生による「Strategic Management(経営戦略論)」の授業です。プレゼンテーションやディスカッションなど、さまざまなアクティブ・ラーニングを取り入れ、授業はすべて英語で行われています。経営戦略論とは、一体どのような授業で、どのようなスキルを習得できるのでしょうか? 前編では、まずは授業の様子をのぞいてみます!

「麗澤大学VS.アメリカの名門イェール大学」大学の経営戦略を分析・プレゼンテーション
教室には、日本人の学生と留学生の計8名の学生が集まり、授業がスタート。ミロシュニック先生の授業は「反転授業※」を採用し、学生は事前に資料や教材を読んだ上で授業に臨んでいます。授業は先生の講義から始まり、そこでミロシュニック先生は、企業経営における「戦略」の重要性を強調します。

-
「企業の経営戦略は、人材など、利用可能なすべての企業資源を効果的かつ効率的に活用し、企業がより優れた成果を発揮するために不可欠なものです。企業の成功は、戦略にかかっています。企業の戦略には『Mission(企業の果たすべき使命や存在意義)』『Vision(企業の理想像)』『Objectives(到達目標)』などがあり、企業の成功には欠かせないものです。今日の授業では皆さんに、企業が成功しているかどうかを『Planet(地球・世界)』『People(人々)』『Profit(利益)』に対するウェルビーイングの観点から考えてもらいます。これらは、3つのP『3Ps』ともいいます。」(ミロシュニック先生)
早速チームでのプレゼンテーションが始まります。学生がアップルチーム、オレンジチームの2つのチームに分かれて、事前に準備してきたプレゼンテーションを行います。テーマは「Reitaku University VS. Yale University」です。私立大学という共通の事業形態である麗澤大学とアメリカの名門イェール大学の現状をデータに基づいて分析し、2つの大学のビジネスモデルと経営実績を比較します。
発表はクラスの8人全員が分担して行い、プレゼンテーションはもちろん、スライド資料もすべて英語です。途中、ミロシュニック先生が発表の内容に対して質問や補足をし、学生が内容を理解できない時には、日本語と英語のバイリンガルである大学院生のTA(ティーチング・アシスタント)が解説してくれます。
※反転授業:学生が教材や動画を使って事前学習し、授業中は復習や応用を中心に行う学習スタイル。
大学の経営は果たして成功しているのか? 3つの「P」から判断する
プレゼンテーションが終わるとミロシュニック先生は、「大学の戦略を分析することは、各大学の経営戦略が成功しているかどうかを見極めるために重要です」と言います。では実際、2つの大学の経営は成功しているのでしょうか? ここからは今回の分析の3つの視点「Planet(地球・世界)」「People(人々)」「Profit(利益)」から考えていきます。
「続いてイェール大学。世界のリーダーとなる人材の育成、社会への貢献を戦略の中心に据えています。Profit(利益)の観点においては、イェール大学は多くの利益を生み出しており、その潤沢な利益はイェール大学の大きな強みとなっています。Planet(地球・世界)の観点では、アメリカに貢献する人材を育成する質の高い教育を提供しています。」(ミロシュニック先生)
People(人々)の観点では、ミロシュニック先生はイェール大学は世界に大きな貢献を果たし、現にビル・クリントンやジョージ・ブッシュなど5人ものアメリカ大統領を輩出していることにふれます。しかし、人々への貢献という面においては、時に間違ったことが起きてしまったのではないか、と言います。
「この点において麗澤大学はより強い側面を持っています。何が正しく何が間違っているのかを教えるだけでなく、人々の幸福や世界の平和を目指す、麗澤大学の創立者・廣池千九郎(法学博士)が提唱した『モラロジー(道徳科学)』に基づいて、倫理的視点に基づき判断し行動できるよう、学生を育てているのです。」(ミロシュニック先生)
学生は授業を通して、企業の成功は利益を生み出すだけでなく、ステークホルダー(利害関係者)にとどまらず、人々と世界に貢献してこそ成功を達成できること、そのために、強固で適切な「戦略」が不可欠であることを学んでいきます。









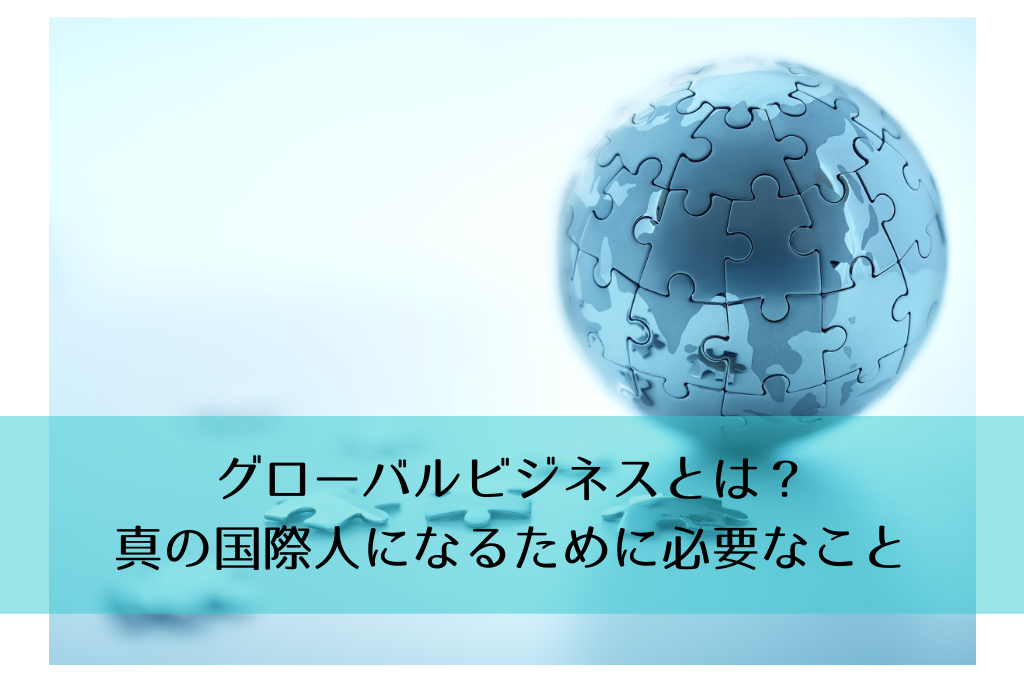



















 麗澤大学の最新情報をお届けします。
麗澤大学の最新情報をお届けします。

