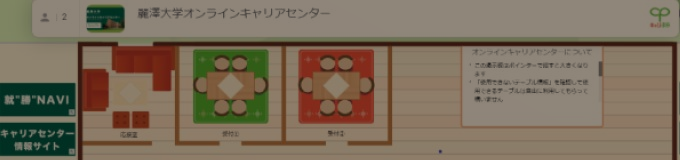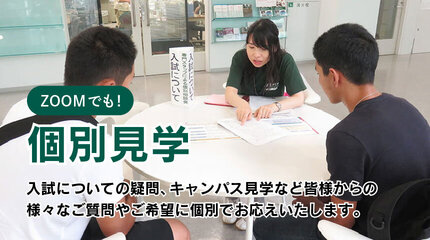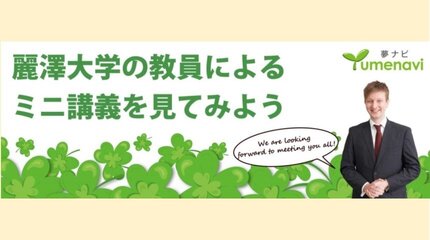お知らせ
【開催報告】Global Seminar Series No.5:「The Homeland ~故郷に帰還するシリア難民~」 小松由佳氏が語る 現地取材から見えたシリアの人々と今
2025年7月15日(火)、Global Seminar Series No. 5として、【「The Homeland ~故郷に帰還するシリア難民~」 小松由佳氏が語る 現地取材から見えたシリアの人々と今】を開催しました。
本イベントは、麗澤大学国際交流センター(黒須里美・河野洋)の主催のもと、株式会社C's CREATIVE(大坪祐三子氏)および今井尚氏による企画支援、さらに麗大麗澤会の後援を受けて実現しました。
国際学部の授業「国際社会学」「社会学概要」と連携した特別講義として、写真展と連動した二部構成にて開催され、同時に「Global Seminar Series No.5」として学内外に広く公開されました。
当日は、地域コミュニティの皆さまに加え、東京や岡山などの遠方からも一般来場者を迎え、最終的には延べ150名を超える参加がありました。
高校生や大学生をはじめ、幅広い世代が参加し、講義後の対話では世代や立場を超えた意見交換が活発に行われました。こうした交流を通じて、「大学が世界と世代をつなぐ知のハブとなる」可能性が大きく示されました。
今回で5回目となるGlobal Seminar Seriesでは、シリア内戦後の国家再建の過程や、500万人を超える難民の帰還と再出発の現実を、長年にわたり現地を取材し続けてきたドキュメンタリーフォトグラファー・小松由佳氏が語りました。
中東情勢が一見遠い世界の出来事として捉えられがちな中、今回の講演を通じて、「知ること」「考えること」を通じた"身近な国際社会へのまなざし"が生まれる機会となりました。
イベント実現には、地域と大学、実務家と教育現場が連携し、新しい学びと対話の場を共創するという強い意思が込められています。
会場には、小松氏が撮影した写真をはじめ、シリア現地から持ち帰られた日用品や、行方不明者の捜索を呼びかけるチラシなどが展示されていました。
それらは、内戦という過酷な現実にさらされながらも、かつての暮らしの温もりを今に宿しており、同時に残骸と化した姿で静かに佇んでいました。
そうした展示物のひとつひとつが織りなす空間には、まるで現地のかすかな息遣いが聞こえてくるような、張り詰めた緊張感と深い静けさが漂い、訪れた人々の心を揺さぶるような、強い感情が満ちていました。
第1部:「"生きていること"の意味を問う山岳から、シリアへ」
講義の前半では、登山家としてのキャリアからドキュメンタリーフォトグラファーへの転身、そして取材地としてのシリアとの出会いについて語られました。
世界で最も過酷とされるK2登頂に成功した経験を持つ小松氏は、「命のない環境に身を置いたからこそ、"生きている"という実感があった」と語ります。
登山を通して「風土と共に暮らす人間そのものへの関心」が芽生え、次第にレンズの向こうに広がる"人の暮らし"を見つめるようになったといいます。
その活動の中心地が、長年内戦が続くシリア。独裁政権下における厳しい取材状況や、言論の自由が制限される現地の実情にも触れ、「なぜ自分が現地で取材をするのか」という問いを常に抱えながら活動を続けていると述べました。
「私たちにできることは、知ること、考え続けることです。報道の内側だけでなく、報道の"外側"にある現実に意識を向け続けてほしい」。そんな静かな力強い言葉が、参加学生の胸に深く響きました。
学生との対話:問いかけから広がる共生の視点
質疑応答では、学生たちの率直な質問に対し、小松氏が丁寧に応答。
特に印象的だったのは、「言論の自由」と「共生のリアル」に関する問いへの回答です。
シリアでの取材では「アサド政権への忠誠を"行動で示す"ことが求められ、写真1枚の扱いにも命の危険が伴った」と語る小松氏は、「自由とは何か」「信条を貫くとは何か」という深い問いに学生たちを導きました。
また、宗教観や文化的背景の違いが夫婦間にも及ぶ体験から、「完全な理解は難しくても、共に存在しようとする努力が大切」という"共生"のリアリティを共有しました。
第2部:「難民として生きるということ」--レンズ越しの希望と現実
後半では、シリア難民の暮らしや価値観についての講義が行われました。
かつて日本からも多くの観光客が訪れ、アニメ文化が広く浸透していた平和なシリアの日常が、2011年の内戦で一変したことが丁寧に語られました。
現地では「ラーハ(休息)」を重視し、家族が何より大切とされる文化の中で育った人々が、突如として難民となり、自国に帰れない状況に置かれる。
小松氏の夫もその一人で、脱走兵として命の危険を冒してトルコに逃れたという現実も語られました。
「宗教や文化、価値観の違いを越えて共に生きるためには、"わかりあえない"という前提から出発する勇気と敬意が必要です」。
その言葉には、現地で暮らし、取材を続けてきた者だからこそ語れるリアルな知恵が詰まっていました。
参加学生の声:希望と問いを持ち帰って
「分断が進む社会に絶望しかけていたけれど、希望を持ち続けることの大切さを学んだ」
「遠い国の話ではなく、自分自身にも関係のある"共生"の問題だと感じた」
参加された方からは、そんな声が多く聞かれました。
本講義は、"現地の息遣いが伝わってくるようなリアルな視点"で語られる貴重な機会となりました。
報道やSNSだけでは見えてこない世界の現実に触れ、私たち自身の「知る責任」や「共に生きる覚悟」について考える時間となったことでしょう。
小松由佳氏の活動からは、「見る」「知る」「考える」ことの積み重ねが世界との確かな接点になるということをあらためて教えられました。
今後も、「Global Seminar Series」では世界で活躍する実践者の知見に触れ、グローバルな視座を育む機会を提供してまいります。
「※写真提供:今井尚氏」
【講師プロフィール】

-
小松由佳(こまつ・ゆか)/ ドキュメンタリーフォトグラファー
1982年秋田県生まれ。幼少時より山に魅せられ、2006年、世界第二の高峰K2(8611M/パキスタン)登頂。植村直己冒険賞受賞。次第に風土に根ざした人間の営みに惹かれ、写真家に転向。2012年からシリア内戦・難民を取材。著書に『人間の土地へ』 (集英社インターナショナル) 。第8回山本美香記念国際ジャーナリス ト賞受賞。
【参加をした学生の感想(抜粋)】
- 今回、初めてシリアの過酷さを学びました。子供の頃から爆弾について学んだりと日本にいては理解できないようなことばかりでした。
今回の講義を機に、そのような国がほかにもないか興味を持つところから始めようと思いました。 - 本日の特別講義で印象に残ったのは、小松由佳さんが「登山の道はいろいろあるけれど、自分にとって大切なのは自分が選んだその一つの道だけだ」と語った部分です。この言葉を聞いて、自分の人生にも当てはまると感じました。社会の中にはいろいろな「正解」や「成功の道」があるように思われますが、
本当に大切なのは他人の評価ではなく、自分が納得して選んだ道を信じて進むことだと思います。 - 本日の小松さんの講義は、シリアという国について深く考えるきっかけとなりました。
特に印象的だったのは、戦争で破壊された街並みと、その後少しずつ再建されていく様子を写した写真です。
崩れ落ちた家々と、そこに再び灯る人々の生活の明かりを比べると、シリアの人々の強さと、どんな状況でも未来を信じて生きる希望を強く感じました。 - 戦場にあった弾の痕跡の展示が印象に残りました。本来ならば触れることの無いものであるし、戦争の悲惨さが生々しく伝わる展示であったと思います。
このようなものを持ち帰ってくるということは、写真と同様に後世に伝えるための最も強い説得力があると感じました。
銃弾の跡があれほど悲惨なものなのに、あれが人間に向けられ、しかも大量の人たちがお互いに使用していたということに改めて驚きを隠せませんでした。 - 今回の授業で私は難民になることの過酷さと日本と中東との文化の違いを大きく実感しました。
今回の講義を通じてアサド政権の自国民たちに対する残虐行為やそこから難民となって自国を出ていくことの重みを知ることができました。 - 本日の特別講義で印象に残ったのは、小松由佳さんがら見た「写真に写らないものを見る力」の重要性だ。
シリアの荒廃した街並みの中にも、人々の暮らしや希望が確かに存在していた。
私は、報道では見えない現地の「日常」にこそ真実があると感じた。
目に見えるものだけで判断せず、その背後にある人々の声や背景に耳を傾ける姿勢が、これからの国際理解に必要であると考えている。