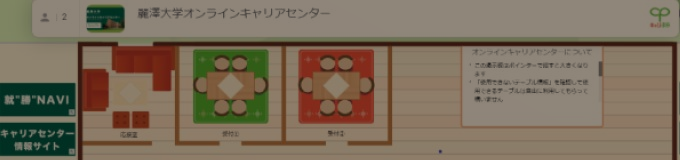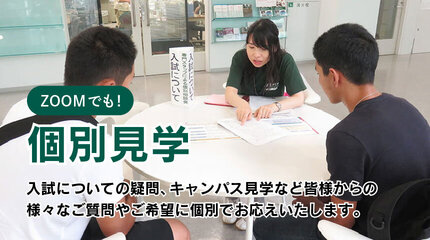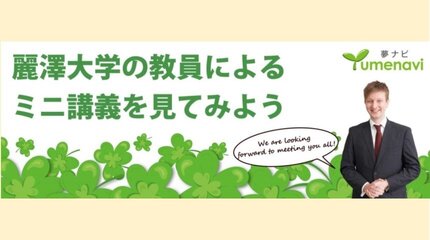お知らせ
【実施報告】麗澤大学と新潟県妙高市 包括連携に関する協定を締結
本学と新潟県妙高市(市長: 城戸陽二)は、両者が持つ資源を活用し、多様な分野において協働による事業等を推進することにより、地域社会の発展、市民サービスの向上及び人材の育成並びに学術研究の振興に寄与することを目的に、「包括連携に関する協定」を2025年7月31日に締結いたしました。麗澤大学が自治体と連携を結ぶのは、今回で13例目、北陸4県では初めてとなります。また、本学陸上競技部の夏合宿場所にもなっております。

【主な連携内容】
■人材の育成に関すること
■地域の国際化に関すること
■産業の振興に関すること
■まちづくりに関すること
■その他目的を達成するために必要な事項
【新潟県妙高市 城戸陽二市長 コメント】
妙高市は総合計画の中で、子ども・若者に視点をあてて「成長と交流とつながりの場づくり」を掲げています。昨年、1回目の高大連携を行った際は、大学生と地元の子どもたちが交流し、さらには地域の方も巻き込んでまちづくりを考えていくなど、これまでにない姿を見ることができました。この包括連携協定が名ばかりではなく、しっかり実の入ったものにしていくことが大事であり、この地をフィールドに学生が様々な知見を広げられる場所づくりも検討していきます。
【麗澤大学 徳永澄憲学長 コメント】
妙高市と麗澤大学が互いに連携し、それぞれの強みを生かしながら、人材育成、教育・文化・観光振興、そして地域づくりに寄与することにあります。これからの時代は、大学と地域の皆さまが共に未来を切り拓くことが重要です。次代を担う若者たちがつながり、新たな価値をともに創り上げ、地域の発展に寄与することで、ますます尽力をさせていただきたい。
今年で妙高市制施行20周年を迎える妙高市は、雄大な妙高山をはじめ四季折々に美しい自然景観に恵まれ、豊富な湧出量を誇る温泉や多くのスキー場など魅力的な観光地を有しています。本学と妙高市は、2024年度から高大連携プロジェクトを通じて連携を深めてきました。このプロジェクトは、妙高市、新井高校、そして大学(麗澤大学、筑波大学、松本大学、長野大学)の三者が協働し、若い世代の意見を生かした新しいまちづくりの実現と、地域の未来を担う人材の育成を目指して進められています。2025年度の取り組みは、7月29日から31日までの3日間、妙高市役所を拠点に実施されました。新井高校生36名と、大学生・大学院生のティーチング・アシスタント12名が参加し、「成長・交流・つながりの場づくり」を大テーマに掲げて活動しました。さらに、7つの小テーマ(農業、観光、新井高校、雪、グローバル、モビリティ、景観・空き家)に分かれて、地域課題の探求に取り組みました。各グループは、テーマに関連する葡萄農園やかんずり製造現場、新井駅、商工会、リゾート施設、タクシー会社などを訪れ、現地でフィールドワークを行いました。高校生の柔軟で創造的な発想に、大学生・大学院生の分析力や専門的な視点が加わり、ブレーンストーミングを重ねながら提案を形にしていきました。
最終日には、城戸市長をはじめとする妙高市の関係者を前に、新井高校生による成果発表会が行われ、活発な質疑と意見交換が交わされました。

ワークショップの様子
参加者全員で記念撮影
妙高市複合施設「まちなか+(ぷらす)」のオープンイベントにあわせて、10月4日(土)に「妙高高大連携まちづくりシンポジウム2025」が開催されました。本学からは、平野秀さん(経済学部3年)、渡邉ななみさん(国際学部2年)、桒谷はるなさん(工学部2年)が参加し、筑波大学、長野大学、松本大学の学生たちとともに活動しました。また、「高校生が大学生に日常を聞く」と題したトークセッションでは、桒谷さんと高校生が活発に意見を交わし、世代を超えた率直で温かな対話の場となりました。今回のシンポジウムでは、7月のワークショップで生まれた7つのテーマをさらに磨き上げ、妙高市の皆さまに向けて成果を発表しました。その中から選ばれた2つのテーマは、11月2日(日)開催の「麗澤大学地域連携シンポジウム2025」と、11月3日(月)開催の「筑波大学高大連携シンポジウム2025」で発表される予定です。

左から平野秀さん、渡邉ななみさん、桒谷はるなさん
クロストークの様子
【麗澤大学 地域連携センター長 大澤義明 コメント】
妙高市には、雪に包まれた静かな冬景色や、湯けむりの立ちのぼる温泉街といった原風景が息づいています。そして何より、人々の優しさがこの土地の魅力を形づくっています。その一方で、少子高齢化の波は確実に押し寄せ、「消滅可能性都市」として名を連ねるなど、妙高はまさに日本の将来を映す鏡のような場所でもあります。そんな地で、日本の未来を担う若い大学生たちが、地元の高校生や他大学の仲間たちと肩を並べ、地域の課題に向き合う姿には、心を動かされます。彼らにとって、それは単なる学びの機会ではなく、人と地域を結ぶ「生きた教育」の場になっているのだと思います。