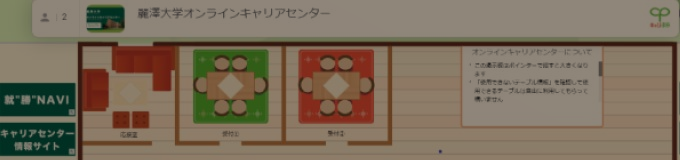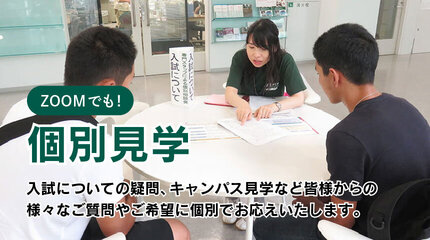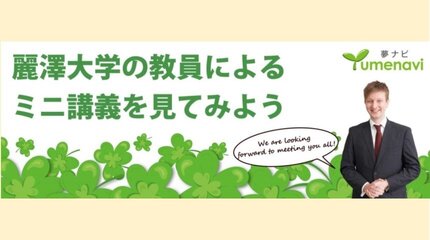お知らせ
【開催報告】「精神障害を抱える人の視点から考えるインクルーシブな防災」
2025年11月6日(木)、自主企画ゼミナール※「障害とコミュニケーション」は、一般社団法人 精神障害当事者会ポルケおよび本学と包括連携協定を締結している白井市の協力を得て、「精神障害を抱える人の視点から考えるインクルーシブな防災(担当:合﨑 京子 国際学部 准教授)」を開催しました。当日は教職員、学生、白井市民、行政関係者等が参加し、精神障害のある方の経験や課題に基づき、誰もが安心して避難できる防災のあり方について考える貴重な機会となりました。
※「自主企画ゼミナール」とは、学生自身がテーマを設定し、指導教員を選び、学習計画を立てながら主体的に学ぶ授業です。「障害とコミュニケーション」では、障害と社会の関係に関心を持つ学生が福祉施設の訪問や当事者との交流を重ね、より包摂的な社会の姿を探求しています。
本イベントではまず、一般社団法人 精神障害当事者会ポルケ 代表理事 山田悠平 氏より、東日本大震災や熊本地震の被災経験をもつ精神障害・発達障害当事者へのインタビュー調査の結果が共有され、災害時に当事者が感じた不安や、避難所で必要とされる支援の多様性が明らかになりました。あわせて、2022年に国連障害者権利委員会が日本に示した総括所見にも触れながら、山田氏は「『私たち抜きに私たちのことを決めないで』という理念のもと、当事者と共に防災計画を見直していくことが重要である」と強調しました。
続いて、東日本大震災や熊本地震で得られたデータや経験を基に制作された映像資料「共に防災意識を高めることを目的としたワークショップの動画」を上映しました。映像では、精神障害のある方が避難所などで感覚過敏を感じやすいことに配慮した防災グッズ(サングラス・マスク・耳栓など)の準備、プライベート空間を確保するための「カームダウンボックス」の活用方法、障害特性に応じた非常食への配慮、避難所で自身の障害をどのように伝えるかといった視点が示され、「日常生活の延長として防災を考える」ことの大切さが伝えられました。
後半には、一般社団法人 精神障害当事者会ポルケ 代表理事 山田悠平 氏、理事 相良真央 氏、有限会社Nikko レ・アーリ相談支援事業所 鈴木一基 氏、本学工学部の鈴木高宏教授、そして自主企画ゼミの学生全員が登壇し、合﨑准教授の進行のもと、地域共生社会の実現をテーマにクロストークが行われました。学生たちは授業や今回の学びを踏まえた疑問を投げかけ、「精神障害のある方のために自分たちにできることは何か」「今回のイベント会場の配置に不快な点がなかったか」、留学生からは「自国では精神障害者の防災対策が進んでいないが、何から始めればよいか」など、率直な問いが次々と挙がりました。登壇者らはそれぞれの立場から丁寧に回答し、活発な対話が生まれました。
最後には「障害をカミングアウトする悩み」に関する質問が寄せられ、山田氏は「怖がる必要はないが、カミングアウト後に周囲がどう反応するか分からない不安がある。精神障害のない人も一緒に考え、語りやすい環境をつくることが重要」と語りました。相良氏からは「『障害』という言葉だけにこだわらず、必要な配慮を少しずつ伝える"グラデーション"のような方法もある。対話を重ねながら、自分に合った言い方を模索することが大切」とのメッセージがあり、参加者は深く耳を傾けていました。
精神障害当事者会ポルケ 山田様(写真左)相良様(写真右)
本イベントを通じ、精神障害のある方の視点から防災を見つめ直すことで、地域の中で支え合うためのヒントが多く得られました。自主企画ゼミナール「障害とコミュニケーション」では、今後も当事者との協働を通して、誰ひとり取り残さない社会の実現を目指し、学びを深めていきます。