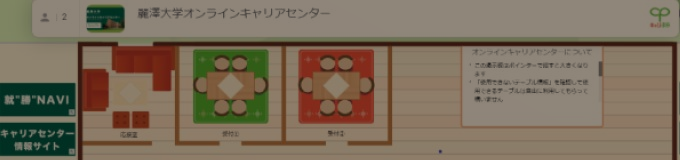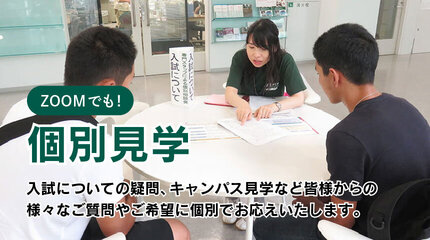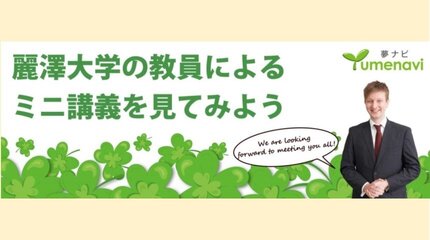お知らせ
【開催報告】特別講義「ロシアの視点から見るウクライナ侵攻 ー作戦と戦術の視点からー」
2025年11月17日(月)、国際学部の授業「国際情勢分析上級A」(担当:阿部亮子 准教授)において、拓殖大学 伊藤嘉彦先生による特別講義「ロシアの視点から見るウクライナ侵攻 ー作戦と戦術の視点からー」が実施されました。
伊藤先生からは、まず、ロシア側から見た、ウクライナ侵攻の政治的背景の説明がありました。ロシアが、南オセチア紛争(2008年)やクリミア併合(2014年)を成功体験と捉え、親ロシア政権と親欧米の間で揺れ動く不安定なウクライナ情勢と、NATO東方拡大に懸念を抱いていたと指摘がありました。
その後、ロシア軍の作戦についての解説がありました。2022年、キーウ攻略を目指したロシア軍の作戦は失敗し、その後、ロシア軍は東部3州の掌握を目指したこと、東部3州の攻略戦は、戦線が膠着しているように見えるが、ロシア軍は部分的に包囲戦を仕掛け、漸進しているという見方が示されました。
ただし、2022、2023年と比較すると、2025年の包囲と要塞の掌握に要する時間がかかっていることが指摘されました。ロシア側の兵力や機材の不足、欧米諸国のウクライナ支援がその原因であろうとの説明がありました。
最後に、「ウクライナや欧米からの視点だけではなく、ロシア側からの視点からも、この戦争をどのような形で終わらせるのか、皆さんに考えてほしい」と呼びかけがありました。ロシアがこのまま、東部3州を掌握したとしても、戦後復興や他国による承認など、課題が多いことも説明がありました。
授業後は、ドイツ留学を検討している学生に向けて、伊藤先生の留学先であったイェーナ大学の教育・生活環境を話してもらいました。伊藤先生が師事した、イェーナ大学のドイツ人の先生は、冷戦中に、東ドイツに留学した麗澤大学の学生達にドイツ語を教えていたそうです。麗澤大学は、西ドイツのみならず東ドイツの大学との交流でも、1986年から現在に
「国際情勢分析上級A」では、これまで、第一次世界大戦が社会や国際秩序に与えた影響、ベトナム戦争では、冷戦構造で米国の軍事力行使に限界が露呈したことなどを学びました。伊藤先生の特別講義を基に、学生は今後、ロシアのウクライナ侵攻をテーマに、グループプレゼンテーションを準備します。それを通して、現代の安全保障問題への理解を深めます。
麗澤大学では、国際学部、国際社会・国際情報(ISI)専攻で安全保障の学びが提供されています。自衛官や警察官、海上保安官など、国や地域の安全を守ることで社会に貢献できる人物の育成を目指します。