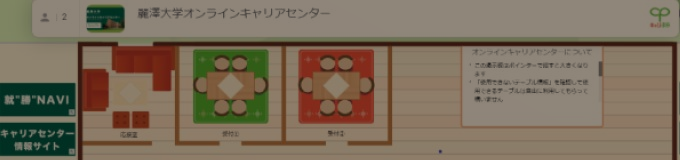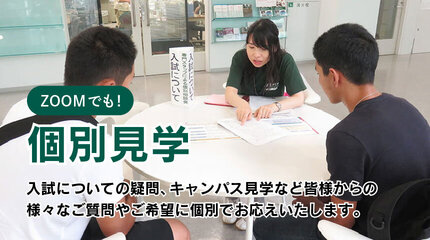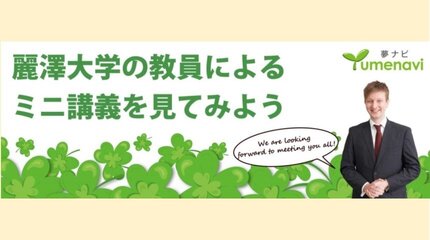お知らせ
【開催報告】国際学部の開講科目にて、ワークショップ「日本酒のユニバーサルデザインについて考える」を実施

2022年12月14日(水)、本学国際学部の山下 美樹教授が担当する上級専門科目である3.4年次生向けの「Intercultural Communication」の授業において、「日本酒のユニバーサルデザインについて考える」と題し、ワークショップを実施しました。今回のワークショップは、本学経済学部の吉田ゼミナールに所属する赤岩麻里さんと吉村俊也さんが取り組む「日本酒プロジェクト」と学部を超えてコラボレーションすることで実現しました。
赤岩さんと吉村さんが手掛ける「日本酒プロジェクト」とは、赤岩さんの地元である埼玉県秩父市の町おこしの為の行政プロジェクトがきっかけで始まりました。秩父は、日本酒、ワイン、ウイスキー、ビール等、様々なお酒が製造されている全国有数の酒どころであり、多くの酒蔵が軒を連ねています。特に日本酒の歴史は古く江戸中期頃から製造されています。しかし近年若者の日本酒離れが進み、需要が減ってきていると言われています。そこで秩父の日本酒を多くの若者に美味しく楽しんでもらいたいと、日本酒にフルーツ等を混ぜた「地方創生カクテル」を企画提案しました。そのカクテルは、来年にも南流山の飲食店でメニューとして提供されることが決まっています。
今回のワークショップは、留学生が多く受講するこのクラスで、留学生に日本の伝統酒である日本酒の魅力を知ってもらうとともに、留学生から日本酒カクテルについて感想や意見を聞き、名前を付けてもらうことで、日本酒の更なる可能性や新しい発想を知るという目的で実施しました。
ワークショップでは、まず初めに日本酒の歴史や種類などについて学びました。今回の授業に参加したのは、ドイツ、モザンビーク、インドネシア、タイ、韓国、ベトナムからの留学生10名と日本人学生3名で、日本酒を飲んだことのない学生も多くいました。また参加者からそれぞれの国でのお酒の文化や人々との関わりについても学び、異文化を知る大変良い機会となりました。
そして参加者全員で実際に秩父の「日本酒」と「どぶろく」に、赤岩さん達が用意した、キュウイ、ゆず、りんごのコンポート、さつまいものペースト等を好みに合わせてブレンドし炭酸水を加えて、日本酒のカクテルを作りました。お酒の飲めない学生は、ノンアルコール飲料で挑戦しました。参加者たちは、自分でブレンドした思い思いのカクテルのテイスティングを楽しみ、その後自分のカクテルのネーミングや評価、更にカクテルにあう料理も提案しました。
参加者からのネーミングを一部紹介します。
| ブレンドの種類 | カクテルのネーミング |
| 日本酒+ゆずシロップ | 「Summer breeze」 |
| どぶろく+かぼちゃペースト+メープルシロップ | 「Sweet Halloween」 |
| どぶろく+牛乳+メイプルシロップ | 「More and More」 |
赤岩さんと吉村さんは、日本的なネーミングが多い日本酒カクテルに、世界で通用するユニバーサルな名前が提案され、熱心に耳を傾けていました。またお酒にあわせる料理も、チーズケーキやクッキーなど多くのデザートが提案され、日本酒との意外な組み合わせに、興味深く聞き入っていました。
授業を担当する山下先生は、全ての研究は、相手、自分、第三者にとって良いものとなるようとなるよう意識して取り組んでいると述べ、今回の取組みも、留学生にとっては、日本酒にふれてもらい魅力を知ってもらう良い機会となり、赤岩さん達にとっては、プロジェクトを進める上での、新たなアイディアと視点、データの蓄積となり、そしてクラスで日本酒のユニバーサルデザインについて考えることで、アカデミックで有意義な研究になったと話しています。
赤岩さんが最後に「楽しかったですか」と聞くと、参加者全員がうなずき、留学生と日本人学生が一緒になって新たな日本酒の可能性につい考える、とても貴重な体験となりました。










 日本酒にブレンドする参加者たち
日本酒にブレンドする参加者たち