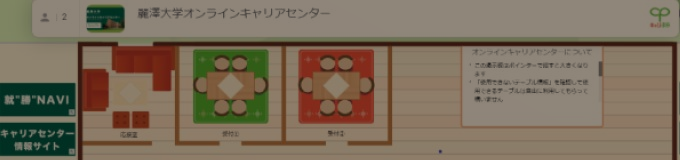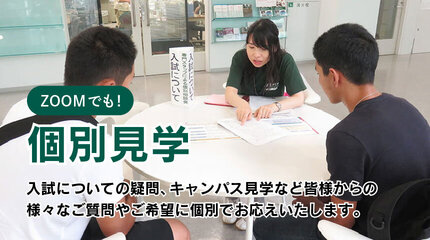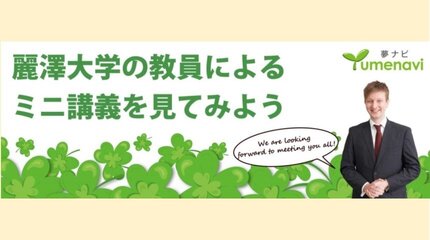お知らせ
【実施報告】「多言語・多文化環境で働く人々のためのケース学習ワークショップ」を実施
2022年6月~8月に計3回実施した「多言語・多文化環境で働く人々のためのケース学習ワークショップ」に国際学部金ゼミに所属する3年次生が参加しました。
本学の他に、韓国の国立ハンバット大学(Hanbat National University)、マレーシアのマラヤ大学(Universiti Malaya)、日本からは神田外語大学の学生や卒業生が参加し、延べ50名が集まりました。
以下が本ワークショップの概要です。
「多言語・多文化環境で働く人々のためのケース学習ワークショップ」
■参加者:日本、韓国、マレーシアの大学生や現職社員など
■企画運営:JKM 共同プロジェクトチーム(麗澤大学 金 孝卿 教授 、神田外語大学 古賀万紀子 専任講師、韓国 国立ハンバット大学 金義泳 助教授、マレーシア Universiti Malaya 木村かおり 上級講師)
■実施概要:
| ワークショップの内容 |
ビジネス・コミュニケーションのためのケース学習*体験 企業で生じているコミュニケーション上のトラブル事例「ケース」を使って話し合い |
| 実施日時 |
第1回 2022年6月25日(土) ポスター 第2回 2022年7月23日(土) ポスター 第3回 2022年8月20日(土) ポスター |
※全てオンライン開催
*ケース学習とは、事実に基づくケース(仕事上のコンフリクト)を題材に、設問に沿って参加者が協働でそれを整理し、時には疑似体験をしながら考え、解決方法を導き出し、最後に一連の過程について内省するまでの学習を指す。(近藤・金2010、近藤2015)
【関連文献】
近藤彩・金孝卿(2010)「「ケース活動」における学びの実態―ビジネス上のコンフリクトの教材化に向けて」,『日本言語文化研究会論集』6,国際交流基金日本語国際センター・政策研究大学院大学,PP.15-31.
近藤彩・金孝卿・池田玲子(2015)『ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 職場のダイバーシティで学び合う【解説編】』ココ出版
2021年度「ビジネス・コミュニケーション上級演習」「日本語教育上級演習C」などの授業で国立ハンバット大学、Universiti Malayaと交流したことが本ワークショップ開催のきっかけです。授業の枠を超えてより深く自由度を高めた交流に繋げたいという想いから、金教授が研究を続けてきた「ビジネスコミュニケーションの為のケース学習」を軸とした本ワークショップの開催が実現しました。
ワークショップでは、就職活動を控えた日本人学生や外国人留学生、日本で働く事に興味を持ち、日本語を使って働くことに期待を持つ韓国人学生とマレーシア人学生。3ヵ国の学生の共通テーマである「働くこと」をテーマとしました。
共通テーマである「働くこと」についてディスカッションを行い、異文化理解と国際交流を深めることで「働くこと」というテーマを超えたお互いの価値観や考え方を学んでいくことがワークショップの目標です。単に就職活動のHow toを学ぶのではなく、「何を大事に働いているのか」、「何故大事なのか」など、それぞれの価値観を共有し、新たな気づきを得ることを目指しています。
ファシリテーターは金ゼミの学生が務めました。初めは、多国籍の学生が集う中での進行に苦労をしている様子でしたが、日本語の使い方を工夫するなど、回を重ねるごとに上達していきました。本学国際学部日本学・国際コミュニケーション(JIC)専攻は、日本をあらゆる角度から学び、英語はもちろん日本語による発信力をつけることを学びの特徴としています。今回のワークショップを通じて、外から見る日本、また日本語を使いながら多角的に働くためのコミュニケーションを学んでいきました。

本ワークショップを企画した金 孝卿 教授は、「海外の方が日本の会社や組織で働く場合、コミュニケーションが上手くいかずに困ることがあります。それは日本人にとっても同じで、海外の方とのコミュニケーションに悩む場面があります。しかし、その考え方の背後には、彼らがこれまで歩んできた社会や文化、価値観があります。ケース学習を基にこのような事を共有し合うことで、お互いの行動やコミュニケーションを考え理解するきっかけになると考えます。今後は、このワークショップをきっかけに実際に韓国、マレーシア、日本のどこかで3ヵ国の学生が対面し議論や交流ができることを目指しています。そして、学生同士で見つけた共通テーマを基にディスカッションすることで異文化理解、国際交流を深めてくれることを願っています。」と述べています。
参加学生の声は以下をご確認ください。
【参加学生の声】
- 様々な国の文化が違うからそこから出てくる価値観の違いも感じる
ことができて新鮮だった。 - 自分だけでは考えつかなかった、
知らなかった意見を聞けて興味深かったです。 - 私はその職場で働く人がお互いに快適に働くことができるかを軸に
解決策を考えていましたが、他の人たちは「 自分のやりたいことをできる職場へ転職する」「 その職場から離れる」といったように、 環境から変えていく意見だったため驚きました。 日本人は仕事を変えたり、今いる環境から脱することが苦手というイメージがあったので、 このような結果になったのではないかと思います。 - The organisers and participants were nice enough to overlook my deplorable Japanese and managed to understand my points
コミュニケーション力を高める近道は、仲間(peer)とともに学び合うこと。
「ことば」は人と人とをつなぐ
日本語教育の研究者として活躍されている金先生。協働学習(仲間とともに学ぶ学習法)「ピア・ラーニング(Peer Learning)」を教育やビジネスの現場で活用すべく、研究・実践に取り組んでいます。