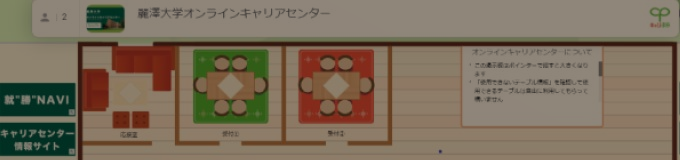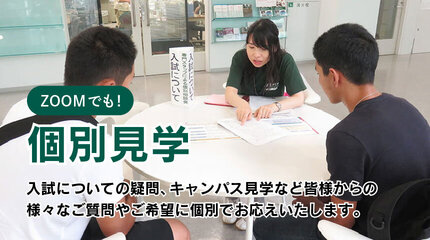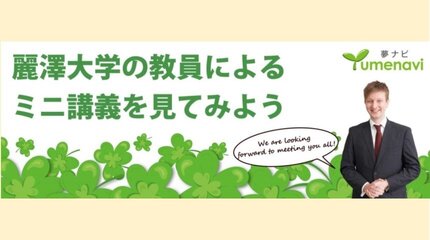お知らせ
【実施報告】広島でフィールドワークを実施
~自主企画ゼミ「戦争の記憶とサスティナビリティ」~
外国語学部の1年次科目「グローバルスタディーズ入門 B」(担当:花田太平准教授)で学び、近現代史に関心をもった10名の学生が、花田准教授、障がい学生支援課の半田タユ美氏とともに、6月29日から30日にかけて広島の平和記念資料館・平和公園などを訪れ、フィールド調査を実施しました。

以下、学生によるフィールドワークのレポートをご紹介いたします。
【 DAY 1 】
1日目は、平和公園・平和記念資料館を訪れ、その後、Human Dialogue Note Project*を行い、被爆体験者の方のお話を聞きました。
資料館には予想していたよりも多くの人々、とくに海外からの旅行者が多く訪れていて印象的でした。館内は原爆が投下される前後、投下から数年後、そして現代に至るまでの様子が写真や絵・遺品などとともにストーリー性をもって展示されており、被爆者の方の物語の世界に足をふみ入れた感覚がしました。視覚的な情報から当時の情景や当事者の感情を想像すると、胸が締めつけられる思いで数々の資料と向き合いました。
Human Dialogue Note Projectでは、複数のグループに分かれ、国籍を問わず平和記念資料館を訪れた方たちへのインタビューを実施しました。戦争について聞いてもいいのか、どんな返答があるのか恐怖感、不安感がありました。海外の方へのインタビューでは、私たち日本人の立場からは普段発せられない言葉や考え方も知ることができました。実際に広島に足を運び、人々と交流したからこそ聞くことができた生の声は、戦争や平和に対する新たな視点に触れるきっかけをもたらしてくれました。
1日目最後の活動として、被爆体験者の切明千枝子さんからご自身の戦争体験についてお話をうかがいました。まず、被爆体験前の生活などについて話されたあと、言葉を詰まらせながら被爆体験で仲間を失ったことを話してくださいました。「平和はあやういもの。油断すると風船みたいに逃げちゃうから、
*Human Dialogue Note Projectとは、資料館においてある「対話ノート」を実際に対面でインタビュー形式により実施するプロジェクトです。

【DAY 2】
2日目はグループを半分に分けて、それぞれ広島市立基町高等学校(普通科創造表現コース)と広島大学(大学院国際研究協力科吉田修ゼミナール)に足を運び対話セッションを行いました。
■基町高校
広島市立基町高等学校の生徒との対話セッションでは、実際に描かれた「原爆の絵」を見ながら、背景や絵に込められた想いなどを含めて紹介していただきました。被爆体験者の方と打ち合わせを重ね、8ヶ月という期間にも及ぶ制作過程。その中で、時には描き直しを行うこともあり、当事者が実際に見た風景や経験を再現することの難しさを改めて感じさせられました。また、「『原爆の絵』はアートではない」というお話が特に印象に残りました。体験者の方の目になり、手となるため、自分たちではなく体験者の方々の見たものを再現している、つまり自分たちが描いてはいるけれども自分たちの作品ではないのだ、とお話を通して感じることができました。

この内容は、基町高校のHPでも紹介していただきました。(外部サイト「基町高校」のウェブサイトに飛びます)
■広島大学
広島大学では、

【最後に】
今回のフィールドワークでは、世代や立場を問わず多くの方との交流を通して、「戦争」や「平和」について自分たちの立場からだけではなく、客観的に広い視野を持ち、深く考えることができました。私たちが日常で感じる「小さな平和」をかみしめることの大切さを感じました。今回だけで活動を終わらせるのではなく、これから先も私たちにできることは何かを考え続け、学内にとどまらず活動していきたいです。
英語コミュニケーション専攻3年 宮内みずき
英語・リベラルアーツ専攻3年 田中美鈴□
英語・リベラルアーツ専攻3年 橋本莉愛□
※本活動は「麗澤大学後援会自主活動支援」の助成を受けています。