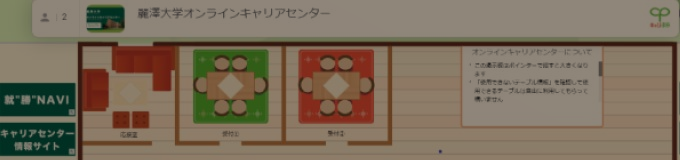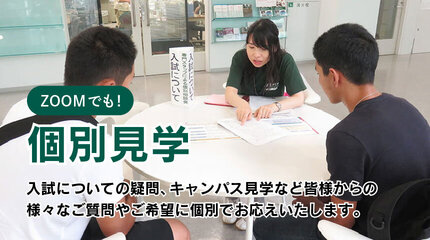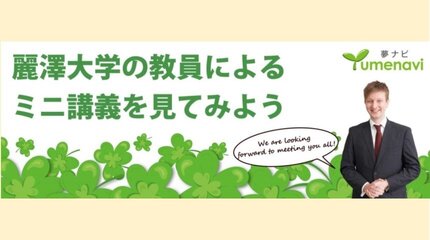学内の情報をデータで⾒ることができます。
大学について麗澤大学×SDGs
【開催報告】麗澤SDGsフォーラム2023

12月9日(土)、本学キャンパスで「麗澤SDGsフォーラム2023」が行われました。このフォーラムはサステナビリティ推進機構とSDGsフォーラム学生運営局が主催し、麗大麗澤会、麗大後援会の協賛で催されました。
 第2部学生プレゼンテーションコンテスト 出場者
第2部学生プレゼンテーションコンテスト 出場者
本学は、「三方よし」「道経一体」の理念を踏まえ、学内外の関係者が協働し、SDGsの達成に向けて行動する機会として「麗澤SDGsフォーラム」を開催しています。このフォーラムは2019年度より始まり、今回で5回目の開催です。
第1部シンポジウムでは前マウライ共和国特命全権大使 岩切敏氏に「SDGsに向けてのODAの役割 〜アフリカで考えたこと〜」と題して講演いただき、「ODA単独ではSDGsへの貢献は難しいが、ODAのレガシーを活用し、アフリカや世界に目を向け、1人ひとりがSDGsに貢献していくことが、SDGs達成の大きなヒントになる」とメッセージを頂戴しました。
続いて、京都大学経営管理大学院客員教授・麗澤大学客員教授の竹林一氏による講演「ワクワク社会をデザインする~Willを持った仲間と創る未来~」では、SDGs17の目標に加えて自分だけの「十八番(おはこ)の目標」を作ることで、誰かが笑顔になりワクワクする持続可能な社会の創造に貢献していくことが、これからの時代におけるイノベーションの秘訣であるとお話いただきました。
前マウライ共和国特命全権大使 岩切敏氏
京都大学経営管理大学院客員教授・麗澤大学客員教授 竹林一氏
第2部の学生プレゼンテーションコンテストでは、「あなたにとって"サステナビリティ"とは何ですか」をテーマに、アイデア・データ分析部門(5グループ)と実践部門(5グループ)に分かれてプレゼンテーションが行われました。TED風のステージで行われたプレゼンテーションでは、各チームがこれまでの学びを活かした大学生ならではのアイデアを発表しました。
審査の結果、以下の4チームに徳永学長から最優秀賞が、麗大後援会 阿部会長より後援会特別賞が贈られました。
【アイデア・データ分析部門】
最優秀賞:Friend of GPT (山口 捷)
Chat GPTを活用して、教育不足・アクセス・言語の壁の問題を解決し誰もが平等に学習する為の実践的アプローチを探る流れを提案
後援会特別賞:SDGsカフェ(小川玲音、高橋尚大朗、下里昂、米元未来)
コーヒーの焙煎からコーヒーかす廃棄におけるCO2削減に着目した「SDGsカフェ自販機」とコーヒーかす再利用商品を提案
【実践部門】
最優秀賞:戦争の記憶とサステナビリティ
(松本桜季、市村美冬、佐々木真子、川津せり、橋本莉愛、田中美鈴、羽生千夏)
対話的手法とVR(仮想現実)等の最先端技術を活用した疑似体験に着目し、被爆者や戦争経験世代と今の若者、そして未来の世代をつなぐことのできる「記憶の場」の創造を提案
後援会特別賞:ReiAppー麗澤大学生専用スマートフォンアプリの提案(合阪涼、渥美駿士)
麗澤大学学生がより情報を得やすくなることを目指し、地図機能・教科書や参考書のフリーマーケット機能・インフォメーション機能を備えたアプリケーションを提案
 アイデア・データ分析部門 最優秀賞 受賞者
アイデア・データ分析部門 最優秀賞 受賞者 実践部門最優秀賞 受賞チーム
実践部門最優秀賞 受賞チーム
 アイデア・データ分析部門 後援会特別賞 受賞チーム
アイデア・データ分析部門 後援会特別賞 受賞チーム 実践部門後援会特別賞 受賞チーム
実践部門後援会特別賞 受賞チーム
また、本学ならではのSDGsの学びを深める授業「SDGsと道徳」から選抜された2チームによるプレゼンテーションも行われ、地球を本来の姿のまま未来に残すためのアイデアや異なる価値観を持つ宗教においてSDGsが掲げる「誰ひとり取り残さない社会」の実現可能性について提言しました。麗澤中学・高等学校 SDGs研究会「EARTH」による活動紹介も実施され、中高生・大学生がそれぞれの視点からSDGsについて発表しました。
第2部と同時に開催された第3部 学生団体による自主活動紹介フェアでは、埼玉県横瀬町の名産品・どぶろくを活用した地域創生プロジェクトや同窓会「ホームカミングデープロジェクト」による展示、タイの民芸品販売など、サステナビリティをテーマにした15の団体による展示や物販が行われました。また、麗澤中学・高等学校 SDGs研究会「EARTH」によるフェアトレードコーヒーと紅茶の試飲会も行われました。
麗澤模擬国連団体による「全米模擬国連大会」出場報告
インドネシアの日本語教育期間でのPBL活動報告
 JAPANESIAによるミクロネシア連邦の環境問題啓発
JAPANESIAによるミクロネシア連邦の環境問題啓発 LINKRUによる言語と空間デザイン&学内ラジオの取り組み紹介
LINKRUによる言語と空間デザイン&学内ラジオの取り組み紹介
最後には参加者全員で交流会が実施され、それぞれが取り組むサステナビリティ活動について共有しながら、学部や学年、立場が異なる参加者同士で交流を深めました。本フォーラムでの経験や新しい出会いが、さらなるサステナビリティへの取り組みの促進に繋がり、持続可能な未来への一歩となることを期待しています。