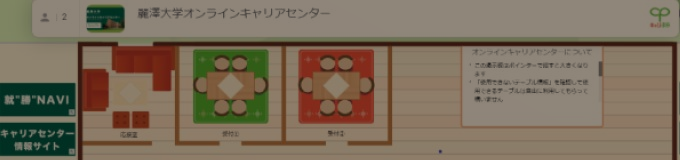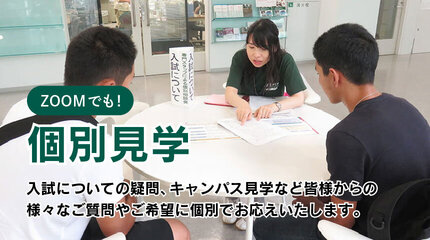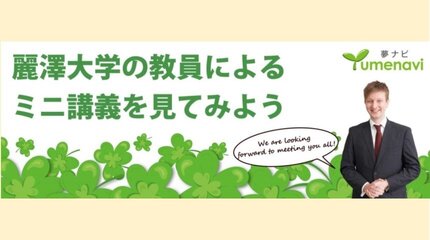学内の情報をデータで⾒ることができます。

・宗教社会学
・神社神道
・社会調査
・戦後の日本における社会変動と宗教
・過疎地域における宗教・神社信仰の変容
・海外における道徳教育の比較研究
・國學院大學大学院文学研究科博士課程後期 単位取得退学
・國學院大學大学院文学研究科博士課程前期 修了
・麗澤大学外国語学部日本語学科 卒業
・博士(宗教学)(國學院大學)
・修士(宗教学)(國學院大學)
・公益財団法人モラロジー道徳教育財団道徳科学研究所 主任研究員
・大正大学 非常勤講師
・麗澤大学外国語学部 非常勤講師
・國學院大學研究開発推進機構ポスドク研究員
・『次世代創造に挑む宗教青年:地域振興と信仰継承をめぐって』 共著 ナカニシヤ出版(2023.12.28)
・『過疎地神社の研究:人口減少社会と神社神道』 単著 北海道大学出版会(2019.09)
・『岐路に立つ仏教寺院:曹洞宗宗勢総合調査2015年を中心に』 共著 法蔵館(2019.07)
・『宗教とウェルビーイング:しあわせの宗教社会学』 共著 北海道大学出版会(2019.03)
・『みる・よむ・あるく 東京の歴史3』 分担執筆(第4節「大火を通してみる消防と社寺」)吉川弘文館(2017.12)
・『人口減少社会と寺院:ソーシャル・キャピタルの視座から』 共著 法蔵館(2016.03)
・『共存学:文化・社会の多様性』 共著 弘文堂(2012.03)
・『神道はどこへいくか』 共著 ぺりかん社(2010.11)
・「過疎地神社の不活動・準不活動化が地域社会に及ぼす影響―超高齢集落の調査事例から」『神道宗教』 第267・268号 単著(2022.10)
・「過疎地神社の現況と氏子意識―高知県旧窪川町の神社と氏子の調査」『國學院大學研究開発推進センター研究紀要』第13号 単著(2019.03)
・「神道と過疎化に関する研究史―広義としての社会変動の枠組みから」『モラロジー研究』第79号 単著(2017.05)
・「皇室における利他的実践―日本統治時代の朝鮮における災害救恤金・下賜金を事例に」『モラロジー研究』第78号 単著(2016.01)
・「過疎地域の神社神道の現状と課題―高知県の過疎集落神社を事例に―」『國學院雑誌』第116巻21号(特集号)単著(2015.11)
・「過疎集落における氏神信仰の継承―高知県高岡郡の旧桧生原集落を事例に」『モラロジー研究』第75号 単著(2015.07)
・「過疎地域の神社調査―高知県高岡郡旧窪川町を事例に」『國學院大學研究開発推進センター研究紀要』第9号 単著(2015.03)
・「過疎集落における氏神信仰の実態―高知県高岡郡の旧川口地区の氏子の語りから」『モラロジー研究』第73号 単著(2014.09)
・「過疎地域における神社神道の変容―高知県高岡支部の過疎地帯神社実態調査を事例に」『総合人間学』第8号 単著(2014.09)
・「過疎地域と神社をめぐる実態調査研究史」『國學院大學研究開発推進センター研究紀要』第7号 単著(2013.03)
・ブックレット『次世代につなぐ宗教青年たち:教化活動の継承と地域の創造』共著(2025.03)
・学会抄録「Report of the 6th Conference of the East Asian Society for the Scientific Study of Religion at Reitaku University from July 5th to 8th in 2024」『モラロジー研究』第91号(2025.02)
・特別講演「人口減少社会における信仰継承と課題」長野県神道青年会創立75周年記念講演会(於、四柱神社)(2025.02)
・公開講座「信仰継承の現代的課題」國學院大學院友学術振興会公開講座「國學院の古典」(2025.01)
・特別講演「人口減少社会における神社運営と信仰継承」神政連静岡県本部周知支部大会・神社庁周智支部神社関係者大会記念講演(2024.02)
・国際学会発表「Transformation and translocality at local communities caused by the Returnees and Migrants Focusing on Community revitalization and Faith Inheritance」ISSR 37th Conference.(Taiwan)(2023.07)
・国際学会発表「The Shinto Priest Returned Home and The Revitalization of Depopulated Village Communities Through The Faith Inheritance: A First Attempt of ‘Action Research’」ISSR 36th Conference(オンライン開催)(2021.07)
先生をもっと知りたい
教員プロフィール
これまで、私は人口減少・少子高齢化が激しい過疎地域の社寺を中心に調査研究をしてきており、2024年4月に麗澤大学経営学部へ准教授として着任しました。専門分野は宗教社会学で、主に過疎地域の社寺、中国少数民族の信仰、倫理・道徳教育の研究をしています。社会調査や地域活動を伴う場合も多く、当事者意識をもって研究したいと思い、専門社会調査士、准認定ファンドレイザーの資格も取得しました。担当科目は、ファミリービジネス・フィールドワーク、道徳経営基礎などです。学生の皆さんとともに切磋琢磨していけたら嬉しいです。
教職員への一問一答
- 好きな言葉(座右の銘)を教えてください。
- 好きな言葉は、「継続は力なり」「人事を尽くして天命を待つ」など、努力を続けることの大切さに関するものが好きですね。中でも、座右の銘とまではいきませんが、常に心がけているものとしては「有言実行」があります。論語に出てくる言葉で、「口だけ」の人間にならず、言葉にしたことを実現する大切さをダイレクトに表す言葉だと思います。信頼関係を築く、または自分を戒めるための指針にもなっています。
- 休日の過ごし方や趣味を教えてください。
- 基本的には家族と一緒に過ごしていますが、子どもたちの勉強をみてあげたり、公園で遊んだり、外食をしたりもします。
家事や育児を妻と分担してやっているのですが、週末は(無駄に)時間がかかる料理に挑戦したり、子どもたち(男の子三人)と将棋、オセロ、トランプなどのゲームで遊んだりしています。
- 大学4年間で「学生に訪れてほしい場所」はどこですか?その理由も教えてください。
- フィールドワークで全国の社寺をめぐっていますが、基本的に中山間地域に出かけることが多く、意外と観光地には行ったことは少ないです。
結婚してから子どもの長期休みを利用して家族旅行に出かけるようになりましたが、山梨県の山中湖に出かけた際の温泉もよかったのですが、翌朝目を覚ますと、目の前にそびえたつ富士山を見て胸がいっぱいになり、神々しさすら覚えました。その光景があまりにも印象的で、それからは毎年家族で行くようになりましたね。
おすすめは何といっても雪化粧の富士山!
学生のみなさんも、神々しさ、富士山の精気をいただきませんか?
- 大学4年間で「学生に読んでほしい本」は何ですか?その理由も教えてください。
- とくに大学生のうちに読んでほしい本でおすすめできるほどの情報はありません。基本的には学生本人の興味関心のあるものをたくさん読んでもらいたいと思っています。強いて言うのであれば、経営学部の教員として、若い世代の人々が持続可能な社会づくりに向けた取り組みを扱った、『次世代創造に挑む宗教青年』をおススメしておきます。
- 専門分野に興味を持ったきっかけは何ですか?
- 大学院に進学した当初は、「日本人の宗教性」と、漠然とした研究テーマしか思い浮かばず、たまたま「過疎化」に関する番組(番組名は忘れました)を観て、ふと「少子高齢化で地域から社寺がなくなったらどうなるのか」と疑問に思いました。指導教員に相談したところ「半年くらい過疎地域で暮らしてみたら?」と言われましたが、さすがに半年は無理で、小豆島に中長期滞在を繰り返すうちに、住民たちの生活が宗教・地域行事として社寺と密接にかかわっていることを知り、本格的に過疎地域の研究に興味を持つようになりました。
- 専門の研究は社会にどう活かされていますか?
- 人口減少・高齢化問題によって経済規模の縮小、社会保障制度や財政などに課題を抱えていますが、人口減少問題は地域における神社や寺院の運営にも大きな影響を及ぼしています。信仰を基盤とする社寺運営において、担い手不足や運営費用の確保といった課題に対し、地域活性化を通じて解決・改善する取り組みを調査研究し、その成果や情報を公開していくことで、同様の問題を抱えている社寺、地域または行政機関と協力できるところに生かされていると思います。
- 麗澤大学の好きなところはどこですか?
- 何と言っても、緑豊かな「自然」ですね。社会人となってはじめて勤務したところは窓のないコンクリートの建物でした。休憩時間に一階のカフェテラスでコーヒーを飲みながら眺める街路樹がせめての癒しでした。その後再びご縁があって学園に戻ってみると、大学生時代には何とも思っていなかった学園の緑が、改めて360度森ビューで、癒し空間になっていることに気づきました。学生のみなさんも空きコマ時間に学園内を散策したり、天気が良い日には友だちとランチしてみたりしてはいかがですか?